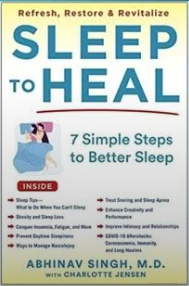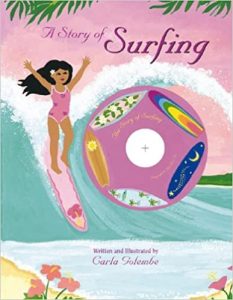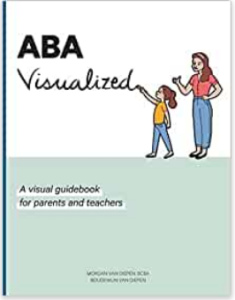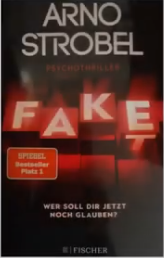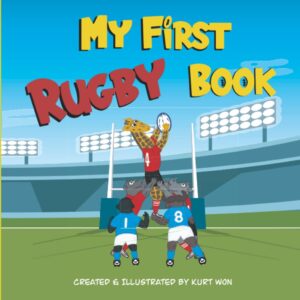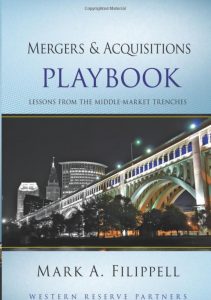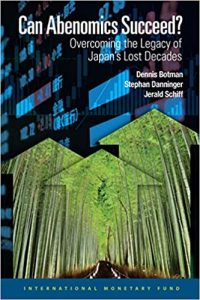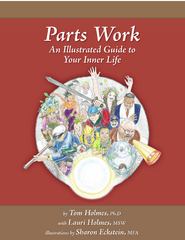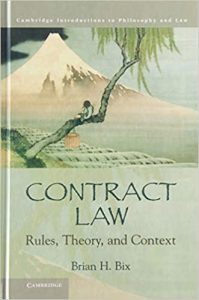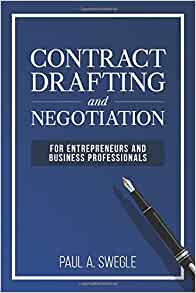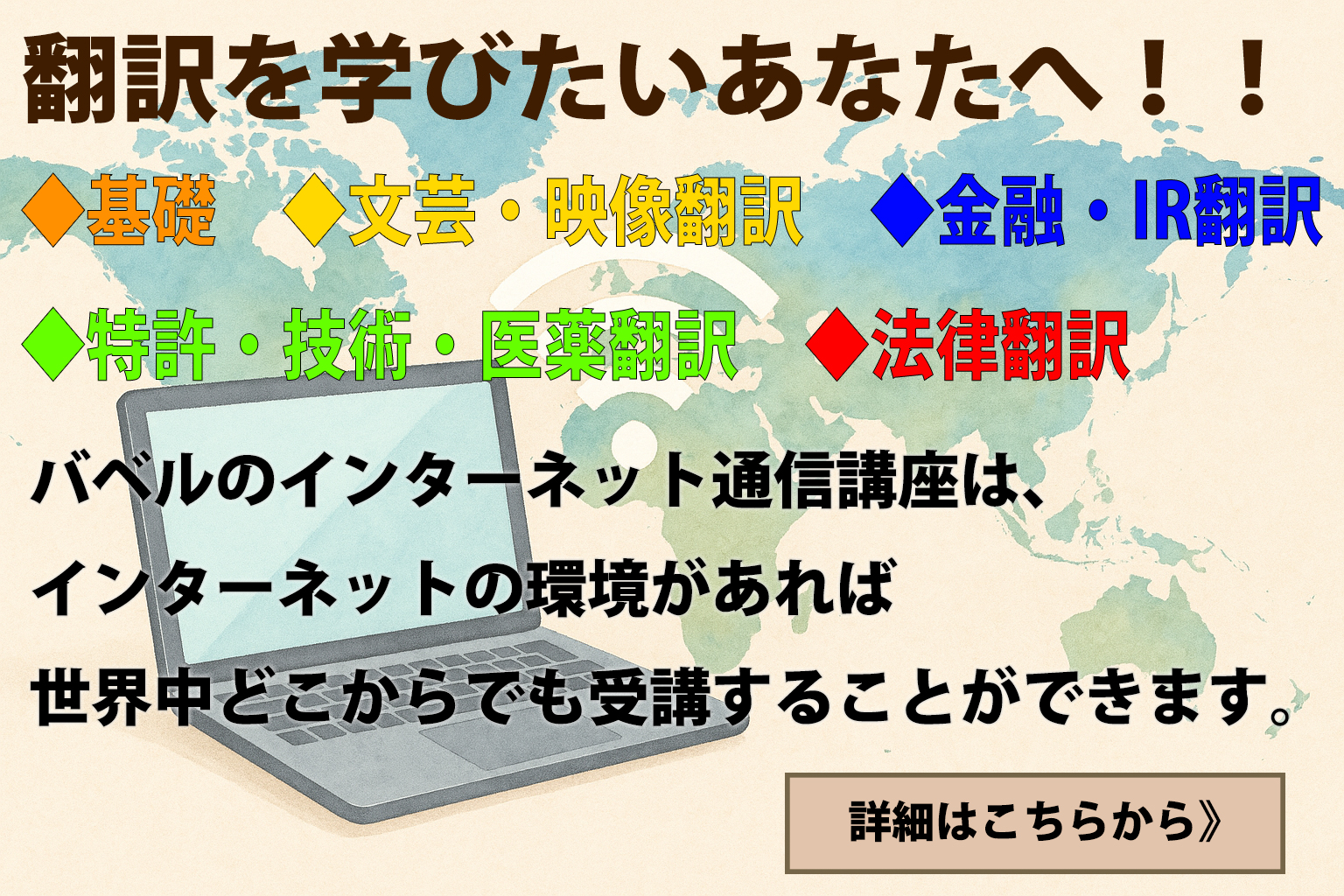#12 真実の口 (#2:奪われていく言論の自由:米国)
知求図書館 2月7日号WEB雑誌「今月の知恵」コラム

インフルエンサーのみならず、YouTuberや一般人など、多くの人が犯人捜しをしている。自分の携帯から撮った写真や動画を基に検証を行っている点が、まさしく現代という時代を反映している。まだテレビも全家庭に普及しておらず、新聞報道を100%信じざるをを得なかったケネディー大統領暗殺時とは大きな違いと言える。カーク氏被弾の瞬間の動画から、弾が発射された方角を推定したり、聴衆の中の“真犯人”がどのように狙撃したのかを解説したりする。さらに、それらをネット上で晒しているのだから、空恐ろしい時代である。正しい情報なのか、偽情報なのか、混沌としているのだ。様々な陰謀論が浮上する中、興味深いと感じさせるものもあった。FBIが提出した犯人の証拠(画像やE-mail)は、AIを駆使した偽証ではないか、と指摘したものである。E-mailの文章はAIに書かせたもの、犯人が逃走する様子を映したセキュリティー・カメラの映像は生成AIの合成だというのだ。犯人が、動機についてのコメントを恋人へ送ったとされる、“ショート・メッセージ”がFBIにより公開されたが、その文章が不自然というのである。現代の若者(Gen-Z)であれば使わない言葉が多用されていることから、どうやらAIに書かせたものではという疑惑を指摘する。AIに間違った指示を出した(英語で一単語をミスっただけ)故にこんな文章になったのではないか、という解説には舌を巻いた。AI能力の限界を把握していないとできない論法である。(真相は定かではないが)その偽装を見破る力もすごいが、(AIで証拠を偽装したのだとしたら)法治国家としてのFBIの権力は地についてしまう。まさしく、いたちごっこのような有り様なのだが、真相はまだ闇に包まれたままとなっている。
カーク氏が大学という場所で公開討論を行ってきたのには理由がある。リベラルな価値観が支配的とされる大学環境において、保守的視点を可視化し、健全な議論を通して相互理解を促進する為であった。各地の大学キャンパス内に仮設テントを立て、学生や教授など誰でもが彼と公開討論ができる環境を与えた。理路整然とした彼の討論スタイルは秀逸で、相手は論破されることも多かった。しかし、同時に、礼儀正しく相手の意見に耳を傾ける姿勢が特徴的でもあり、単なる論破ではなく「対話による説得」をゴールとしていた。「異なる意見を持つ人々と直接対話し、自由な言論空間を守るため」というのが彼の持論でもあった。
カーク氏の死後、その死を悼むどころか喜ぶ発言をSNSに乗せている人もあり、その行為には驚かされた。いかに反対思想の人でも、その死を喜ぶというのは人道に反している。バンス副大統領が、カーク氏の暗殺を喜んでいる人が近辺にいたら通報せよ、と呼びかけたのにも驚いた。それにより実際に解雇された人も多々いた、と聞く。権力を逆手に取った取り締まり方では、相互リスペクトを基本理念とすべき人間関係の本質が崩れてしまう。意見の違う反対派の命をねらう、口を封じる、圧力をかける、という行為は民主主義から大きく外れる、カーク氏が最も嫌悪していたことである。
ケネディー大統領暗殺の真相に触れた非公開機密文書が、60年以上も経た今年に公開となり、真実の口がようやく開いた。カーク氏の暗殺の真相も闇が深いだろう。その真実の口が開くことが、もしかしたら無いのかもしれないと思うと、幼子二人を残して31歳という若さで他界したカーク氏の死の無念さに胸がつまる。
-------------------------------------------------------------------------------
CNN's Tori B. Powell and Matt Meyer
記事紹介(CNN:10月18日2025年
Here's what we've heard from protesters across the country today
全米各地での、抗議者の声
Bill Nye, "The Science Guy" speaks at DC protest: "What's going on in our government is wrong”
ビル・ナイ「サイエンス・ガイ」、ワシントンD.C.の抗議集会で演説:「政府で起きていることは間違っている
2025年6月14日(トランプ大統領の誕生日)「No Kings Day」と称する抗議デモが全米各地で行われた。約2,700都市で開催され、推定500万人以上が参加したとされ、その後、50501ムーブメント(50州で50の抗議を同時に行う草の根運動)へも発展した。“No Kings“デモは、トランプ政権による権力集中へのボイコット運動で、強硬な移民政策、政敵への刑事訴追、司法・報道機関との対立への抗議内容である。抗議参加者は「王はいらない(No Kings)」を合言葉に、民主主義の擁護を訴える。まるで一国の王様のように振る舞うトランプ氏を“King(王様)”と揶揄し、「民主主義を守れ」「アメリカに王はいらない」という建国理念を再確認させる目的をも含むという。10月18日には、2度目のデモが再び全米各地で行われた。前回を上回る規模となり、推定700万人以上が参加、ファシズムや独裁政権を経験してきた背景をもつヨーロッパの国(スペイン、ドイツ)でも連帯デモが行われた。「民主主義の後退」や「権力の集中」への懸念が国境を越えて共有された証ともなっている。単なる反トランプ運動ではなく、民主主義の制度的崩壊への警鐘、アメリカの建国理念(王政拒否)を再確認する象徴的なムーブメントとなり、現代史上最大規模の抗議活動とも評価されている。
谷口知子
バベル翻訳専門大学院修了生。NY在住(米国滞在は35年を超える)。米国税理士(本職)の傍ら、バベル出版を通して、日米間の相違点(文化/習慣/教育方針など)を浮彫りとさせる出版物の紹介(翻訳)を行う。趣味:園芸/ドライブ/料理/トレッキング/(裏千家)茶道/(草月)華道/手芸一般。