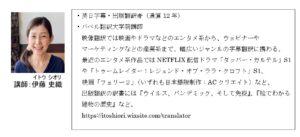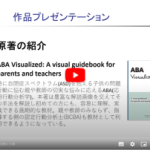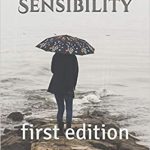ブックコミュニティ第17回
読書は対立の時代の救世主か?
アメリカでは、政治的な分断が日常生活の細部にまで影を落としています。選挙のたびに浮き彫りになる「赤い州と青い州」の対立は、いまや家庭内にまで深刻な亀裂をもたらしています。親子や兄弟姉妹の間で意見が対立し、避け合う光景は珍しくありません。そんななか注目されているのが、「ブッククラブ」を媒介とした対話の試みです。
米メディアWiredによれば、デンバーに住むある女性は、トランプ支持を続ける父親との関係を修復するために、ある提案をしました。それは、父親が娘の勧める本を三冊読んで理解する代わりに、娘は父親の通う教会に一ヶ月間通うという内容でした。互いに歩み寄り、対話のきっかけを作る「交換条件」として読書を選んだのです。この小さな試みは、政治的信念の違いをめぐる「ゼロサム」の構図を和らげ、相手の世界観を理解するための共通の場をつくり出しています。
こうした事例は、従来の「課題本を決めて意見交換する読書会」とは異なります。本は「交渉の媒介」であり、互いの世界を覗き込む手段なのです。日本でも世代間の価値観の違いはしばしば話題になりますが、アメリカのように宗教や政治が強く絡む社会では、その溝はさらに深いと言えます。だからこそ、読書という「第三の場」を介することに意味があるのです。
出版関係者にとって、この動向は二つの点で示唆に富みます。第一に、読書が「関係修復のツール」になり得ること。翻訳書やノンフィクションが、単に知識を与えるだけでなく、家族や友人の対話を促す役割を果たせるのです。環境問題やジェンダー論、歴史認識などは世代間で意見が割れやすい領域ですが、読書会を通じて読まれることで、対立を「言い争い」から「学び合い」へと転換できる可能性があります。
第二に、出版が「社会的セラピー」として機能し始めている点です。読書はこれまでも「癒し」と結び付けられてきましたが、近年は「関係の修復」や「対話の場づくり」という機能が前景化しています。本シリーズ第15回で取り上げたSilent Book Club のように、ただ一緒に読むだけの活動が広がっているのも、対立から距離を置きたい人々の心理を反映しています。
翻訳者にとっても、この現象は無縁ではありません。「どの本を翻訳・出版すべきか」という選択が、読者にとって「対話のツール」となるかを左右するからです。異文化理解を促す翻訳ノンフィクションや、歴史を異なる視点から描く小説は、分断社会において重要な役割を果たし得ます。翻訳者自身が「異なる言語文化の橋渡し」を担っていることを思えば、この「家族間の橋渡し」とは響き合うものがあります。
さらに視点を広げれば、読書による対話はマーケティングの観点からも注目されます。かつてブッククラブは「同じ趣味を持つ人々が集う場」でしたが、いまや「異なる立場の人が出会う場」へと変わりつつあります。出版社や書店が、意見の異なる人々が安心して参加できるフォーマットを提供できれば、それ自体が新しい社会的価値を持つでしょう。
もちろん限界もあります。強固な信念を持つ人を「説得」するのは容易ではなく、逆に反発を招く可能性もあります。読書会が「布教の場」と化してしまえば、関係修復どころか溝を深める危険もあるでしょう。それでも、読書を媒介とする試みが注目されている事実は、「対立の時代における読書の新たな役割」を浮かび上がらせています。
翻訳出版の現場では、「この本は誰かの心を開くかもしれない」という視点を加えることが、単なるビジネス判断を超えた意味を持つかもしれません。政治的・社会的に揺れる現代において、翻訳者や出版社は「物語や知識の翻訳者」であると同時に、「対話の触媒」を提供する存在でもあるのです。