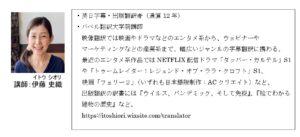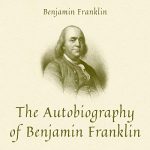ブックコミュニティ第16回
タイパ志向の新しい読書スタイル
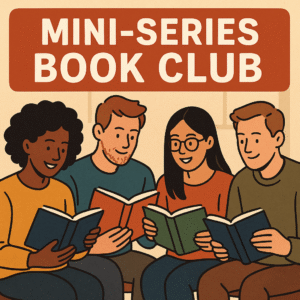 日本では、映画やドラマの倍速視聴や要約アプリの利用など、短時間で効率的に情報を得る「タイパ」志向が定着しています。この「短時間で成果を得たい」という価値観は、欧米の読書コミュニティでも同じように見られ、新たな読書スタイルを生み出しています。
日本では、映画やドラマの倍速視聴や要約アプリの利用など、短時間で効率的に情報を得る「タイパ」志向が定着しています。この「短時間で成果を得たい」という価値観は、欧米の読書コミュニティでも同じように見られ、新たな読書スタイルを生み出しています。
その代表例が「ミニシリーズ読破型ブッククラブ(Mini-Series Book Club)」です。通常2〜4週間という短期間を設定し、特定のテーマやシリーズ作品を集中的に読み進めます。例えばReese’s Book Clubでは、ベストセラーや話題作を、短期間でテーマに絞って紹介しています。またInstagram発の「Mini-Series Reads」では、インフルエンサーが中心となって読書の進捗を共有しながら、フォロワー同士の交流を活発化させています。
このブッククラブの魅力の一つは、テーマ設定の柔軟さにあります。参加者は「移民文学」「フェミニズム小説」「クラシック女性作家」「ミステリー短編」など多様なテーマから興味のあるものを選べます。1テーマあたり読む本は通常2〜3冊程度であり、無理なく参加できる量に設定されているため、完読の達成感を得やすく、読書継続のモチベーションも維持しやすいのです。
また、オンラインディスカッションが活発なのも特徴のひとつ。Slack、Zoom、Instagramライブなどを使って、参加者同士がリアルタイムで感想を語り合ったり、疑問点を共有したりしています。SNSと非常に相性がよく、個人の読書体験が自然に共有されやすい環境であるため、口コミ効果で新しい参加者も増えています。
さらに、人気プラットフォームでは、参加者が次回のテーマを投票で決定することもあります。このような参加型の仕組みが読者の主体性を引き出し、コミュニティの結束力を強める効果を生んでいます。
翻訳出版業界にとっても、この新しい読書スタイルは見逃せない動きです。ミニシリーズ形式は特に短編や連作形式の作品と相性がよく、従来は目立ちにくかった短編集や特定のテーマに沿った既刊の翻訳書を新しい文脈で紹介できます。また、英語圏でのトレンドや話題作を短期間で把握し、翻訳候補を迅速に見つけることにも役立っています。
プロモーションの柔軟性も魅力です。テーマごとの選書をSNSで紹介することにより、単独の新刊に限らず複数作品を同時にアピールできます。過去の翻訳作品を再注目させたり、関連テーマを設定して読書の幅を広げたりする戦略が立てやすくなっています。
読書体験が多様化する今、ミニシリーズ形式は読者と翻訳書をつなぐ新しい可能性を秘めています。テーマの選定、作品の再評価、読者体験の共有を積極的に進めることで、翻訳書市場の活性化や新たな読者層の開拓につながるものと期待されます。
今田陽子(いまた・ようこ)
BABEL PRESSプロジェクトマネージャー。カナダBC州在住。シャワー中もシャンプーボトルのラベルから目が離せない活字中毒者。