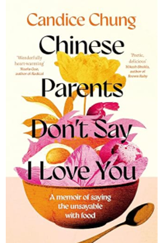新着動画
おすすめの記事
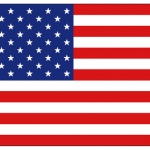
アメリカ

World News insights

World News insights

カナダ

日本翻訳史
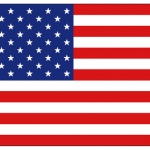
アメリカ

カナダ

カナダ