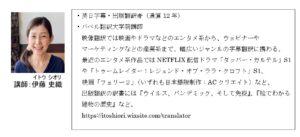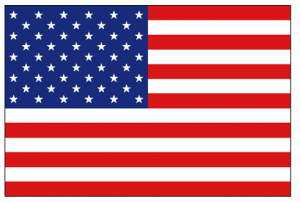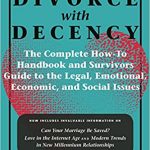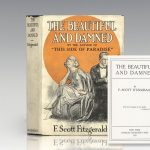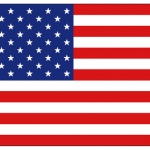2025年10月7日 第373号 World News Insight (Alumni編集室改め) 子どもに打つワクチンは本当に安全か? バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
問い直される「常識」
ワクチンは20世紀以降、感染症の流行を抑え、人類の寿命を延ばす役割を果たしてきた。天然痘やポリオが象徴的であり、「ワクチンは子どもの命を守る」という認識は、現代医療の常識ともいえる。しかし、この常識を根底から問い直す書籍が2023年に米国で出版された。それが『Vax-Unvax』である。本書は「接種者(Vax)」と「非接種者(Unvax)」の健康状態を科学的に比較し、これまでの理解を揺さぶるデータを提示している。
『Vax-Unvax』が示す衝撃
『Vax-Unvax』の特徴は、個別の症例報告ではなく、大規模な疫学的調査や統計分析を集約している点にある。参考文献は764件、グラフ119点、表17点に及び、専門家の批判を意識したデータ主導の構成となっている。
たとえば本書では以下のような結果が紹介されている。
• ワクチン接種を受けた子どもは、非接種の子どもに比べてアレルギー性鼻炎の発症リスクが有意に高い。
• コロナワクチンを2回接種した青年は、接種しなかった青年よりも心筋炎を発症するリスクが著しく増加する。
これらは一例に過ぎず、本書では発達障害、自己免疫疾患、アレルギー疾患など、従来は想定されにくかった関連性についても報告がなされている。
ワクチンの恩恵とリスク
ここで重要なのは、ワクチンが感染症予防に果たしてきた恩恵を否定するのではなく、その「副作用や長期的影響」について十分な検討がなされてきたのかを問う点である。感染症による死亡率は歴史的に劇的に減少してきたが、その一方でアレルギー疾患や自己免疫疾患は増加している。『Vax-Unvax』は、この現象にワクチンがどの程度寄与しているのかを追及する。
つまり本書の問題提起は、単なる「陰謀論」や「反ワクチン論」ではなく、科学的データを根拠に「リスクとベネフィットの再評価」を迫るものだといえる。
科学の難しさ――相関と因果
ただし、疫学データには常に解釈の難しさが伴う。接種の有無以外に、生活習慣、環境要因、社会経済的背景などが健康リスクに影響を及ぼすため、「ワクチンが直接の原因」と断定することは容易ではない。研究の質や統計処理の妥当性についても、医学界で活発に議論されている。したがって、ワクチンの安全性を考える際には「有害事象と疾患発症の相関」をどのように因果へと近づけていくかという科学的方法論の課題が横たわっている。
親の選択と社会の責任
では、子どもにワクチンを接種させるかどうかを判断する親は、何を基準にすべきか。公衆衛生政策は「集団免疫」を前提に設計され、社会全体の利益を重視する。しかし、親の立場からすれば、まずは「自分の子どもの健康」が第一の関心事である。集団の利益と個人のリスクとの間には、しばしば緊張関係が生じる。
『Vax-Unvax』のような書籍は、親が「自らの選択を科学的に裏づけたい」というニーズに応える一方、社会全体のワクチン政策に対する不信を招く可能性もある。このバランスをいかに取るかは、今後の大きな課題である。
日本における議論の遅れ
日本では、ワクチンの副作用に関する研究や報道は比較的限定的であり、接種推進のメッセージが優勢である。新型コロナ禍においても、短期間で承認されたワクチンの安全性については十分な議論が行われたとは言い難い。『Vax-Unvax』が日本語に翻訳された意義は、こうした一面的な議論に多様な視点をもたらす点にある。情報に触れることで、親や教育者、政策立案者がより多角的に考えるきっかけを得られるだろう。
「安全」という言葉を問い直す
「子どもに打つワクチンは本当に安全か?」という問いに、現時点で明快な答えは存在しない。安全とは絶対的なものではなく、常に「リスクと利益の比較衡量」の上に成り立つ相対的な概念である。ワクチンは感染症を防ぐ強力な武器である一方、長期的な健康リスクが皆無であると断言できる証拠もまだ不足している。
したがって私たちに求められるのは、従来の常識に盲従することでも、根拠のない不安に流されることでもなく、科学的データを吟味し続ける姿勢である。『Vax-Unvax』が示した数多くのデータは、そのための出発点となりうる。子どもにとって本当に望ましい選択をするために、今こそ「安全」の意味を問い直す必要があるだろう。