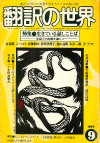2025年7月22日 第368号 World News Insight (Alumni編集室改め) 第2弾-見えざる“学知戦”の最前線 バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
ハーバードから東大へ、中国の影と留学生戦略の真実
2024年、トランプ前大統領がハーバード大学に在籍する留学生のビザ取り消しを指示した件は、単なる選挙向けのパフォーマンスではなかった。その裏には、米中対立の新たな舞台となっている「学術領域」がある。かつて冷戦時代に軍事・宇宙・通信をめぐるスパイ戦があったように、現代では「大学」や「研究室」がその最前線になっているのだ。この視点を鋭く警告する人物が日本にもいる。元産経新聞論説副委員長で、中国情勢に詳しいジャーナリスト、佐々木類(ささき・るい)氏である。彼は、ハーバード大学と中国共産党の関係が問題視される一方で、「実は日本こそ、より深刻な“無防備国家”ではないか」と訴えている。
東大・早稲田に集まる高レベル中国人博士課程留学生
佐々木氏の独自調査によれば、東京大学、早稲田大学、京都大学、さらには東工大や大阪大学といった、日本の最先端研究拠点において、博士課程に在籍する中国人留学生が急増しているという。特に理工系、人工知能、量子技術、宇宙開発、生命科学などの分野でその傾向が顕著だ。もちろん、学問の自由と国際交流の推進は、大学の基本理念である。しかし、佐々木氏はそこに潜む「制度の盲点」こそが最大のリスクだと指摘する。日本は“誰でも受け入れる”という開放型モデルを維持してきたが、そこに中国共産党の国家戦略が巧妙に組み込まれていると見ている。
「一朝有事の際は、政府の命令に従え」
衝撃的なのは、佐々木氏が明かす「誓約書」の存在である。中国政府は、国家奨学金制度を通じて留学生を支援する際に、「有事の際は中国政府の指示に従う」という内容を含んだ文書への署名を求めているというのだ。つまり、たとえ海外で学び、現地の大学に所属していても、必要とあらば本国から「指令」が下され、それに従わなければ処罰対象になる。言い換えれば、留学生たちは“学術の民”であると同時に“体制の民”でもあり得るのである。 これはもはや個々人の問題ではない。制度として「国家と個人の契約」が成立しており、その先にあるのは「知の帰属先」が母国であるという構図だ。中国政府が送り出す留学生は、教育の受益者であると同時に、「知識収集の代行者」でもある可能性がある。
すでに始まっている“静かな侵略”
こうした仕組みは、日本国内でも実例が報告されている。たとえば、ある旧帝大のナノテク研究所では、中国人博士課程の研究員が、日本人指導教員の指示で研究成果の一部を中国本土の大学にメール転送していた事例が確認されている。形式上は「学術交流」とされていたが、実態は国家主導の技術移転だった可能性が高い。また、日本の大手製造業グループが誇る次世代半導体技術について、中国本土の大学と共同研究プロジェクトを進めていた際、途中で研究資料の外部流出が発覚。その調査対象に含まれていたのが、研究所に出入りしていた留学生だった。これらの情報は、確たる証拠とともに公表されることは少ないが、佐々木氏を含む複数のジャーナリストや安全保障関係者は、「静かな侵略」が日本の技術基盤にじわじわと食い込んでいると警告する。
中国共産党の“留学利用”は国家プロジェクトだった
このような動きの背景にあるのが、中国政府の「千人計画(Thousand Talents Program)」をはじめとする国家的人材招致プロジェクトだ。この計画は、世界各国で教育・研究活動に従事している中国人研究者や留学生を対象に、母国への帰国と研究成果の“持ち帰り”を奨励する制度である。2018年には、米国でこの計画に関与したハーバード大学の著名な化学者チャールズ・リーバー教授が逮捕され、大きな波紋を呼んだ。中国から多額の資金を受け取りながら、それを申告していなかったことが問題視されたが、それ以上に問題なのは「研究機密が中国側に渡っていた」可能性だった。こうした流れが今、日本の大学や企業にも波及し始めている。国家の研究投資は、もはや単なる学術支援ではない。国益と安全保障に直結する「知的主権」の問題になっている。
日本は“防衛なき開国”を続けるのか
では、日本はこうした状況に対して、どのような対応をしているのだろうか。文部科学省や大学側は、「人権尊重」、「国際化の推進」という理念のもと、特定の国籍に対する差別的扱いを回避する立場を取っている。確かに理念としては正しい。しかし、現実には国境を越えた“情報戦”が繰り広げられており、そのなかで日本はほぼ「丸腰」の状態である。たとえば、入国審査において研究テーマや所属機関を精査する体制はほとんど整っていない。大学内に設置されたセキュリティポリシーも、情報漏洩リスクへの認識は十分とは言いがたい。民間企業の研究所ですら、共同研究契約の裏で機密保持の実効性が曖昧なままの例も散見される。
今こそ「教育安全保障庁(仮)」の創設を
ここまで見てきたように、教育と安全保障の接点が無視できない時代に入った。日本も、「教育の自由」と「国家の防衛」という二律背反の中で、現実的な調整を迫られている。そのためには、文科省、外務省、防衛省、経産省、警察庁などが縦割りで扱ってきた問題を統合する、「教育安全保障庁(仮称)」のような横断的組織の創設が急務である。研究機関の安全評価、外国人留学生へのリスク査定、共同研究契約のガイドライン整備、情報漏洩防止訓練の実施など、多層的な対応が必要だ。
学び合う時代の「信頼」には、覚悟が要る
国際交流を否定するつもりは毛頭ない。しかし、真の国際共存は、“無防備な善意”ではなく、“信頼に足る管理”の上に築かれるべきだ。ハーバードを取り巻く緊張と、東大を舞台にした沈黙の戦争は、表裏一体である。これからの日本は、「開かれた知」と「守るべき知」のバランスを取るために、曖昧な楽観主義を脱却しなければならない、のでは。