2025年4月7日 第361号 World News Insight (Alumni編集室改め) トランプ大統領の「一律関税」発表――日本とG7諸国の新たな試練本の未来を守るために バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
2025年4月2日、アメリカのトランプ大統領が発表した輸入品への大規模な関税措置は、世界経済に大きな衝撃を与えました。発表内容によりますと、すべての国や地域からの輸入品に対して、一律10%の関税を課すほか、特定の国々には追加でさらに高い税率を設定するとのことです。日本もその対象に含まれており、特に自動車産業に対しては厳しい課税が想定されています。
この突然の発表は、各国政府および世界の市場に混乱をもたらし、株価は2020年のパンデミック以来、最大の一日下落幅を記録しました。日本としては、このような状況をいかに受け止め、いかに対応すべきか、冷静かつ戦略的な判断が求められています。
日本の自動車産業に迫る深刻な影響
日本は長年、アメリカとの貿易において自動車を中心とした輸出に強みを持ってきました。実際に、日本製の自動車は年間130万台以上がアメリカ市場で販売されており、これは日本の対米輸出の柱となっています。
一方、アメリカの自動車は日本市場であまり売れていないのが現状です。その理由としては、左ハンドル仕様であることや、大型で燃費が悪いといった、日本の消費者ニーズと合致しない製品設計が挙げられます。
こうした実情を踏まえず、トランプ大統領は「アメリカ車が売れないのは日本の市場が閉ざされているからだ」と非難し、日本製自動車に対する報復的な関税の導入を進めています。
この追加関税が実際に適用された場合、日本の自動車メーカーは価格競争力を失い、売上や利益が大きく落ち込む可能性があります。自動車業界にとどまらず、関連する部品メーカー、運送業、小売業など幅広い産業にも影響が及ぶでしょう。国内外の経済アナリストの中には、日本のGDP成長率が最大で2%程度低下する可能性を示唆する声もあり、深刻な事態といえます。
世界各国の反応――分断か、協調か
このような強硬な関税措置に対して、G7各国をはじめとする多くの国々が即座に反応を示しました。以下に、主要国の対応を紹介いたします。
まず、カナダのマーク・カーニー首相は、米国の関税発表から数時間以内に報復関税の導入を発表しました。「我が国の労働者と産業を守るため、あらゆる対抗手段を講じる」との声明を出し、実際に複数のアメリカ製品に対する関税リストを準備しています。
イギリスでは、スターマー首相が冷静かつ実利的な対応を強調しつつ、総額1850億ポンドにおよぶ米製品に対する報復関税案を検討しています。対象にはスマートフォンや生活用品など、幅広い製品が含まれていると報じられています。
ドイツのショルツ首相は、今回の関税措置を「協調を損なう、根本的に誤った政策」と非難し、EU全体で強力かつ一貫した対抗措置を講じるべきであると主張しました。フランスも同様に、EUの一員としてアメリカに対抗する立場を明確にしています。
イタリアのメローニ首相は、「関税の応酬は両国の利益にならない」とし、誠実な対話による解決を呼びかけました。こうした慎重な姿勢は、事態のさらなる悪化を防ぐためのバランスを模索するものと考えられます。
そして、日本の石破茂首相もまた、今回の関税措置がWTOのルールや日米間の貿易協定に照らして整合性を欠く可能性があると懸念を表明しました。同時に、日本経済への影響を最小限に抑えるため、アメリカに対して冷静かつ粘り強い交渉を行っていく意向を示しています。
多国間連携による対応が鍵となる
このような状況の中、日本が単独でアメリカと対峙するのは得策とは言えないでしょう。むしろ、G7やCPTPP、RCEPといった多国間枠組みを活用し、国際協調の立場から、関税政策の見直しを求める姿勢が重要となるのではないでしょうか。
また、WTOへの提訴など国際的な法制度のもとで正当性を訴えることで、アメリカに対して一定の抑止力を働かせることも可能でしょう。アメリカ国内でも、上院少数党院内総務のミッチ・マコネル氏をはじめ、関税政策に懸念を示す声があり、世論調査でも70%のアメリカ国民が物価上昇を不安視していることが報じられています。こうした米国内の状況も視野に入れながら、日本は冷静な情報発信と外交努力を続ける必要があります。
対米依存からの脱却と持続可能な経済構造の確立を
今回の事態は、日本経済にとって大きな打撃であることは間違いありませんが、同時に大きな教訓でもあります。今後、過度なアメリカ市場依存から脱却し、アジア、アフリカ、中南米など新興国市場への多角的な展開を加速させる必要があります。
また、EVや水素エネルギー、AIなど新たな産業分野への投資を進め、より高い付加価値を生む製品やサービスの創出を図ることが、日本企業の競争力強化につながるでしょう。
サプライチェーンの多様化、国内回帰の促進、地域経済との連携強化など、長期的な視点からの産業構造改革も急務です。外的リスクに強い、持続可能な経済システムの構築が求められています。
試練を成長の機会へと転じるために
2025年4月2日に発表されたトランプ関税は、世界に新たな分断をもたらす火種となりつつあります。しかし、日本はこれまで幾度となく、外圧を乗り越えてきた歴史を持っています。1980年代のプラザ合意後も、国内産業の再編と技術革新を通じて新たな成長を実現しました。
今回もまた、日本には冷静な判断力と戦略的な対応力が求められています。短期的な動揺にとらわれず、国際社会と連携しながら、未来を見据えた持続可能な成長戦略を進めるべき時です。この難局をどう乗り越えるか。それこそが、今の日本の外交と経済政策に問われている最も重要なテーマであるといえるのではないでしょうか。







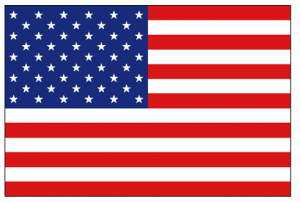


![第14回 【1】 イギリス書籍レポート[2]](https://babel.co.jp/gwg/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/englan-150x150.png)















