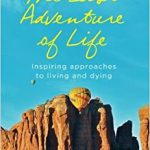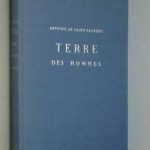東アジア・ニュースレター
海外メディアからみた東アジアと日本
第170 回

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教
中国の上場企業の4分の1近くが昨年7~9月期に純損失を計上し、利益率も2009年以来の低水準に落ち込み、多くの企業がコスト削減モードに入っているとメディアが伝える。こうした状況ではトランプ米政権が課す新関税が中国企業をさらに圧迫するとみられ、消費刺激策を含む政府の景気対策に期待が高まっている。
台湾の昨年通年の経済成長率は前年比4.3%増と好調だったが、第4四半期の成長率は1.84%増と3四半期連続で拡大が鈍化し、成長率の維持が台湾の課題となっている。他方、台湾の対米貿易黒字が昨年、過去最高に急増しており、貿易不均衡の一掃を目指すトランプ大統領を挑発するかもしれないとの懸念が高まっている。
韓国は昨年12月、尹錫悦大統領が戒厳令を突如宣布し、国会が尹氏の弾劾訴追案を可決。尹氏は職務停止となるという混乱状態に陥った。このため消費者・企業心理が落ち込み、経済は大きく減速した。政府は補正予算の編成や国内企業への支援策、輸出市場の多様化などを打ち出しているが政局の混乱収拾が鍵を握るとみられる。
北朝鮮の金総書記は、北朝鮮が社会主義の楽園であるという幻想を維持するために西側の情報やコンテンツの流入防止に注力している。最近、白頭山英雄青年衝撃旅団を組成しプロパガンダの中心的役割を与えた。衝撃旅団は体制維持のための青少年組織で構成員は現在30万人とされているが、さらに拡充されていくとみられ注目を要する。
東南アジアは激化する米中対立のはざまでチャンスを活かそうとしているが、参入企業が域内で経済価値を付加しない場合が多く、簡単には利益を手に入れられないとメディアが指摘する。とはいえ東南アジアの指導者に再工業化を達成する貴重な機会をもたらしており、これを単なる魅力的なスローガンで終わらせてはならないであろう。
インドは低迷し始めた景気の刺激策として政府が中間層への減税や規制改革を打ち出した。無税となる個人所得税の基準額を引き下げ、また大企業に対し賃上げに向けて圧力をかけている。インド準備銀行(中央銀行)も政策金利を0.25%引き下げ6.25%にすると発表し、景気下支えの姿勢を鮮明にしている。
主要紙社説・論説欄では、第2次トランプ米政権の発足に関連したメディアの論調を取り上げた。西側陣営に対して利益だけでなく価値観の擁護にも動くべきだと主張すると共に、トランプ関税は無視して米国を除く世界貿易システムの再構築を提言する。
§ § § § § § § § § §
北東アジア
中 国
☆ トランプ米政権との貿易戦争に脆弱な中国企業
中国全土の企業は、過剰生産能力と景気低迷の中で消費不振に苦しんでおり、手元資金を流出させていると、2月7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは伝え、ドナルド・トランプ米大統領が中国製品に対する新たな10%の関税を導入し、追加措置もあり得ると脅しをかけて圧力を強めている今、この問題のため中国は異例なほど脆弱な状況にあると警告する。記事はさらに以下のように報じる。
企業が過剰供給分を海外に売り払うなか、輸出は中国経済にとって数少ない明るい材料となってきたが、関税率が上昇して米国の買い手のコストが増大するとそれははるかに難しくなる。中国本土で上場する企業の4分の1近くが、データが入手可能な直近の四半期に当たる2024年7~9月期に純損失を計上した。ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)がA株市場に上場している中国企業の提出文書を分析したところでは、この割合は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)前の2倍超になっている。中国本土市場に上場している約5,000社で構成する、ファクトセット社の指数によると、中国の上場企業の利益率は最近、2009年以来の低水準に落ち込んだ。公式統計によれば、2024年の中国大手企業の利益は約3.3%減少し、3年連続の減益となった。規模の小さい家族経営企業の多くも苦戦している。
利益が圧迫される中、多くの中国企業はコスト削減モードに入っており、投資の延期や従業員削減、賃金の抑制を行っている。しかし、企業や消費者の支出減は、中国が同じ問題に直面し続けることにつながる。それは消費の伸びが強く求められる状況であるにもかかわらず、需要が低迷しているという問題だ。中国指導部は経済成長促進策として、製造業と輸出に目を向けている。しかし、国の補助金が一因となって増えた余剰生産能力は、一部業界の在庫のだぶつきを悪化させている。多くの企業は製品の在庫を削減しようと価格を引き下げているが、それでは利益がさらに削られるだけだ。そして、それはさらなるコスト削減へとつながる。
上記のように報じた記事は、トランプ政権が新たに課す関税は米国に製品を輸出する中国企業をさらに圧迫するとみられ、一部のメーカーは米国の顧客獲得に向けた競争力維持のために値下げを余儀なくされるだろうと述べ、具体的な中国企業の動きを次のように伝える。遼寧省に本拠を置く中国最大級の鉄鋼メーカーの鞍山鋼鉄は最近、効率化を試み輸出を拡大するなど、「損失の低減と制御のためのあらゆる方策」を講じたことを明らかにした。しかし鉄鋼価格は下落し続け、需要は低迷したままだ。同社は2024年の決算について損失が前年の2倍以上に増え、およそ70億元(約10億ドル)になるとの見通しを示している。電気自動車(EV)用電池向けの素材を扱っている天斉リチウムも投資家向けに赤字見通しに関する警告を出した。同社製品の価格低下を受けて、2024年決算の純損失が約10億ドル相当に達する見込みだという。純損失を出すか減益になると警告している他の中国企業の中には、太陽光発電用のガラスを生産しているフラットグラス(福莱特玻璃)、イリコ・グループ・ニュー・エナジー(彩虹集団新能源)、建材メーカーの天山材料、半導体メーカーの上海復旦微電子などが含まれる。太陽光発電市場に好不況の波があることが一部中国企業の黒字維持が極めて難しくなっている一因に挙げられる。中国政府は太陽光発電を重要産業分野に指定し、地方政府や金融機関に同分野の企業への補助金や融資の提供を促してきた。複数の企業の新規参入を受けて供給量が急増し、顧客獲得のための値下げ競争が起きた。値下げを渋ったり減産したりすれば、市場シェアを失うリスクがあった。
記事は最後に中国政府の対応について、以下のように報じる。
中国は過去に過剰生産能力を抑えるために痛みを伴う措置を講じたことがある。例えば1990年代の改革では企業を整理し、何百万人もの失業者を出した。今回はそのような措置は取られていない。中国指導部が昨年導入した措置は、大部分が差し迫った金融リスクの回避に重点を置いていたため、さらなる消費刺激策を期待していた投資家たちを失望させた。モーニングスターによると、2024年の中国A株ファンドからの資金純流出額は44億ドルとなった。2023年の流出額は26億ドルだった。中国の最高立法機関である全国人民代表大会(国会に相当)の招集を3月に控え、一部の企業は中国指導部が今年、より消費に焦点を合わせた刺激策を打ち出すことを期待している。
米国が新たに発動する関税は中国の悩みを増やすものだが、一部の投資家やアナリストは国内問題の方が差し迫ったものだと指摘する。中国本土の上場企業の売上高のほとんどは国内で得られたものだ。英投資会社アバディーンの中国株式部門トップ、ニコラス・ヨウ氏は「人々は関税について過剰に心配している可能性がある。力を入れる必要があるのは国内経済だ」と述べた。
以上のように、中国本土で上場する企業の4分の1近くが2024年7-9月期に純損失を計上し、利益率は2009年以来の低水準に落ち込んでいる。このため多くの中国企業がコスト削減モードに入っているが、国の補助金が一因となって増えた余剰生産能力が一部業界の在庫のだぶつきを悪化させており、多くの企業は製品の在庫を削減しようと価格を引き下げ、利益がさらに削られるという悪循環に陥っている。こうした状況では、トランプ政権が課す新関税は対米輸出する中国企業をさらに圧迫するとみられている。そうした業種として、鉄鋼、電気自動車(EV)用電池向けの素材や太陽光発電、建材、そして半導体メーカーなどが挙げられている。政府は過去において過剰在庫を抱えた企業を整理し、何百万人もの失業者を出したが、今回は今のところそのような措置を打ち出していない。指導部が昨年導入した措置は概ね差し迫った金融リスクの回避に重点を置くもので、消費刺激策を期待していた投資家たちを失望させたと記事は指摘する。そうした消費刺激策を含め中国指導部が今後、どのような景気対策を打ち出すか、注視したい。
台 湾
☆ 減速する経済への対応が課題
台湾主計総処が24日発表した2024年第4四半期の域内総生産(GDP)速報値は前年比1.84%増加で、第3四半期の4.17%増から伸びが鈍化したと、1月24日付ロイター通信が報じる。この数字は同社がまとめたアナリストの予想(2.0%増)を下回ったと述べ、季節調整済みの前期比年率では2.04%増だった報じる。記事によれば、輸出は前年比9.1%増加で第3四半期(8.1%増)から加速し、これは人工知能(AI)関連需要を追い風に半導体などが伸びたためである。
また24年通年の成長率は4.3%となり、14年ぶりの低成長だった23年(1.31%)から回復し3年ぶりの高成長となった。主計総処が昨年11月に示した予測の4.27%と一致した。アナリストは、トランプ米政権の関税政策や米国での生産拡大要求を背景に今年は不確実性が生じていると指摘。台新投資顧問のアナリスト、ケビン・ワン氏は台湾企業の投資計画に影響が及ぶとみている。「第4四半期の成長率が予想を下回った主な要因は輸入設備の大幅な増加で、それがAI関連、情報通信製品の輸出(前年比9.09%増)の伸びを帳消しにした」と述べた。
同じく同日付ブルームバーグは、2024年の台湾経済は、AIブームに乗った技術輸出に後押しされ、過去3年間で最も速いペースで成長したが、今年の見通しはドナルド・トランプ大統領の関税の脅威によって不透明になっていると以下のように報じる。
昨年の国内総生産(GDP)は前年比4.3%増となったと統計局は金曜日の声明で述べた。これは、ブルームバーグがエコノミストを対象に行った調査の推定値の中央値と一致したが、第4四半期のGDPは1.84%で3四半期連続で拡大が鈍化し、急速な成長を維持するという課題が浮き彫りになった。経済は人工知能で使用される半導体やサーバーなど、台湾が製造するハイテク製品に対する世界的な需要によって高成長を遂げてきた。先週、台湾最大の企業である台湾積体電路製造(セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー)は、四半期の売上高と設備投資がアナリストの予想を上回ると予測し、AIハードウェアへの支出が今年も底堅く推移するとの期待が強まっている。
しかし、トランプ氏のホワイトハウスへの復帰は、台北の当局者にとって懸念事項である。台湾の対米貿易黒字は昨年過去最高に急増した。それは、アメリカの貿易における不均衡をなくしたいと願うトランプ大統領を挑発するかもしれない。同大統領は選挙運動中に台湾が米国のチップビジネスを盗んだと非難し、中国からの軍事的脅威をかわす民主主義に不可欠な米国の保護のために台湾に支払いを求めたため、台北の当局者も警戒している。
以上のように、昨年通年の経済成長率は前年比4.3%増と好調だったが、昨年第4四半期の成長率は1.84%と3四半期連続で拡大が鈍化し、急速な成長を維持することが台湾にとって課題となっている。他方、台湾の対米貿易黒字が昨年、過去最高に急増しており、貿易不均衡の一掃を目指すトランプ大統領を挑発するかもしれないとの懸念が高まっている。
韓 国
☆ 最近の経済情勢
2024年第4四半期の国内総生産(速報値)が季節調整済みで前期比0.1%増加したと韓国銀行(中央銀行)が発表したと、1月23日付ロイター通信が報じる。報道によれば、成長はわずかにとどまり、ロイターがまとめた市場予想(0.2%増)を下回った。第3四半期も0.1%増だった。過去数十年で最悪の政治危機に陥るなか、国内需要が打撃を受けた。第2次トランプ米政権発足で外部リスクも高まっており、成長はさらに阻害される可能性がある。
12月、尹錫悦大統領の戒厳令宣布を巡り、国会が尹氏の弾劾訴追案を可決し、尹氏は職務停止となった。尹氏の職務を代行していた韓悳洙首相の弾劾訴追案も可決された。政治の混乱を受け、消費者・企業心理が落ち込んだ。中銀は尹氏が12月3日に戒厳令を宣布する約1週間前に第4四半期GDPが0.5%増加するとの見通しを示していた。中銀当局者は23日の会見で「政局不透明感により経済心理は大幅に弱まっており、第1四半期や通年のリスク要因として引き続き経済に影響を及ぼすだろう」と述べ、第1四半期の成長率も中央銀行が昨年11月に示した見通し(0.5%)を下回る可能性があると警告した。
また2025年通年の経済成長率について韓国銀行は1.6~1.7%との見通しを示し、11月時点の1.9%から下方修正した。ブログで12月の尹錫悦大統領の非常戒厳宣言に端を発した政治的不確実性と内需後退を理由に挙げた。2024年の経済成長率は2.0%か2.1%となる見込みで、2カ月前の予想2.2%を下回る。12月29日の航空機事故も影を落としたという。韓銀は、経済の成長軌道は現在の政治的不確実性の解消、政府の景気刺激策、次期米政権の経済政策に大きく左右されるとの見方を示した。
上記のような経済情勢について1月28日付ブルームバーグは、政治が韓国経済を妨害していると次のように論評する。韓国経済はもっと良くなるはずだった。インフレは順調に緩和しており、主要輸出国として韓国は世界的な成長率上昇の恩恵を受けることができた。アメリカ経済も好調で中国も景気拡大を下支えする重要な措置を講じている。政治が邪魔をしているが、これは大規模経済といえども自力で動くものではないことを思い起こさせる。
先月、尹錫悦大統領が戒厳令を短期間発動したことに端を発した長引く政治的行き詰まりは、まさに最悪のタイミングで経済への信頼を失墜させた。聯合ニュースによれば、検察は弾劾された尹氏を内乱罪で起訴し、尹氏は拘留を余儀なくされている。この政治上の大失態が安定しているとして知られる韓国の経済部門に影響を及ぼしているのだ。12月の失業率は1ポイントも跳ね上がった。これは先進工業国としては大変なことだ。国内総生産は2024年の最後の3ヶ月間、ほとんど上昇しなかった。確かに金利は低下しており、尹大統領が退任して後継者が現れれば、ビジネスが軌道に乗ることを期待する理由はある。
こうした状況のなか、崔相黙(チェ・サンモク)大統領代行が景気刺激策として追加予算の合意を求めたと2月12日付ロイター通信が伝える。大統領代行を務める崔財務相は12日、内需の鈍化と対外不安の高まりに苦しむ経済を支えるための補正予算について、国会内での迅速な合意を望むと述べた。過去数十年で最悪の政治危機がすでに弱体化している内需に打撃を与え、ドナルド・トランプ大統領の下で外的リスクが高まっている今年、成長をさらに低下させる恐れがあるためだ。野党「共に民主党」の党首が少なくとも30兆ウォン(約206億5,000万ドル)の追加予算を提案し、その翌日には与党「人民の力」の権成東(クォン・ソンドン)院内総務が、同党は追加予算の審議に反対していないと述べた。
エコノミストの間でも、中央銀行総裁の間でも、政府は経済を支えるために補正予算を編成するべきだという声が高まっている。崔氏はまた、政府は国内企業への支援策を準備し、輸出市場の多様化を図ることで米国の関税による国内への影響に先手を打って対応すると述べた。トランプ米大統領がバイオ医薬品分野も関税の対象だと発言したことを受け、政府はバイオ医薬品分野への支援を強化し、国内企業が米国の製造施設とつながるよう支援すると崔氏は述べた。
以上のように、昨年12月、尹錫悦大統領が戒厳令を突如宣布し、これを巡り国会が尹氏の弾劾訴追案を可決、尹氏は職務停止となるという混乱状態に陥った。これを受け消費者・企業心理が落ち込み、経済は大きく減速した。対策として政府は、補正予算の編成や国内企業への支援策、輸出市場の多様化などを打ち出しているが、中央銀行である韓国銀行は、経済の成長軌道は現在の政治的不確実性の解消、政府の景気刺激策、次期米政権の経済政策に左右されるとの見方を示している。なかでも政局の混乱収拾が鍵を握ると思われる。
北 朝 鮮
☆ 若者の教化に注力する金総書記
金正恩総書記は北朝鮮全土で絶対的な権力を享受し、自国民からは神格化されている。しかし、41歳の独裁者である金にとってある脅威が大きく立ちはだかっていると、1月23日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルが伝える。記事によれば、金正恩が特に懸念しているのは、情報統制国家である北朝鮮に外国メディアが入り込み、ハリウッド映画やK-POPアルバムを通じて北朝鮮国民が外の世界を垣間見ることができるようになることだ。金正恩が「危険な毒物」と呼ぶそのようなコンテンツを所持、配布することは、死刑を含む厳しい罰則が課される。危険にさらされるのは、北朝鮮が社会主義の楽園であるという幻想を維持する金正恩の能力である。そして、北朝鮮の最若年層ほど、イデオロギーの逸脱に脆弱な集団はない。だからこそ金正恩は最近、白頭山英雄青年衝撃(ショック)旅団にプロパガンダの中心的役割を与えているのだ。国の神聖な山である白頭山にちなんで名づけられたこの10代と20代のグループは、夏の洪水で壊滅した西側国境地帯の再建を支援したことで、国家的英雄として称賛されている。同国の国営メディアは4ヶ月の間に15,000軒の家、学校、病院を建てたと報じている。以上のように、金正恩総書記は北朝鮮が社会主義の楽園であるという幻想を維持するために彼が「危険な毒物」と呼ぶ西側の情報やコンテンツの流入を防止することに注力している。そのため金総書記は最近、白頭山英雄青年衝撃(ショック)旅団を組成しプロパガンダの中心的役割を与えたと記事は報じる。衝撃旅団は大規模な建設プロジェクトなどの肉体労働に従事し体制への忠誠心を養う準軍事組織のひとつである。
青年衝撃旅団の30万人のメンバーは、急遽動員され、自ら志願したと国営メディアは伝える。自らを「慈悲深い父」と呼ぶ金総書記は、先月の演説で新顔のメンバーたちに賞賛の言葉を浴びせ、肉体労働プロジェクトを遂行することで体制への忠誠を表現するよう呼びかけた。金委員長は国営メディアで、この建設作業は「若者を社会主義の堅固な擁護者、信頼できる建設者となるよう訓練する良い機会だ」と述べた。金曜日の国営メディアの報道によれば、最高人民会議は、「わが国家の精神」を示す「壮大な建設運動」に賛辞を贈った。ソウルのシンクタンク、世宗研究所のピーター・ウォード研究員は、「金正恩は、若者が集まって韓国のテレビを見たり、国家について異端的な考えを抱いたりするのを阻止するために、労働に従事させたいと考えている」と語った。
金正恩には課題が山積している。ロシアへの1万2千人の軍隊派遣に対する内外の反発を避けなければならず、また崩壊した経済を支えるために経済制裁に違反する行動に出ている。さらに北朝鮮指導者に再び接触すると宣言したトランプ米大統領と、あと4年間どのように付き合っていくかを決めなければならない。しかし、北朝鮮の若い世代を真の信者として維持することは、長期的な問題であるが、今すぐに対処しなければならない喫緊の課題である。北朝鮮の若者を洗脳することは、数十年にわたる政権の存続を保証するものである。プロパガンダ・キャンペーンを失うと国内が不安定になったり、指導者の決断に対する監視の目が向けられたりする可能性があると、安全保障の専門家たちは言う。
金正恩は1年前、韓国との平和統一の望みを捨て、韓国を北朝鮮の新たなNo.1の敵と宣言した。近年、金正恩はミニスカートのような韓国のファッションや韓国でボーイフレンドを短縮して呼ぶナムチンのような表現の使用も禁止しようと動いている。国境では射殺命令が出され、北朝鮮人の出国と外部からの情報の侵入を阻止するための障壁が築かれた。若い男性は少なくとも10年間は徴兵され、毎日教化教育を受ける。ロシアで戦う兵士たちの忠誠心は、捕虜となった兵士の尋問や殺害された戦闘員の遺書からみて高いようだ。しかし、それでもなお、女性や学齢期の青少年、そして病気、低身長、身体障害などの理由で徴兵資格のない男性が残っている。
白頭山英雄青年衝撃旅団は、過酷な条件下で大規模な建設プロジェクトを加速させるために、日常の仕事から引き抜かれた北朝鮮人で構成される数十の準軍事組織のひとつである。衝撃旅団はソ連などの社会主義国家で高度な機械の不足を克服するために組織された労働力である。2023年の韓国政府の報告書によると、ショックブリゲードには自発的に参加する者もいるが強制的に徴集され、広範な栄養失調に直面する者も多いという。労働環境は危険な場合もある。約2年前、北朝鮮の国営メディアは緊急手術にもかかわらず、記録的なスピードで巨大な温室を建設し、作業中に死亡したとする18歳の「処女の少女兵士」を称賛した。彼女は日記に日々の任務を果たせなかったことに対する金委員長への謝罪の言葉を書いていたと伝えられている。
2011年に脱北したチョ・チョンヒは、40年以上前に青少年衝撃旅団に徴兵された。当時17歳だった彼は、北朝鮮のソンブン制度(出身成分。家系を三代前まで遡って調査し、金日成や金正日への忠誠度の順に「3大階層51個分類」に分類されている)における社会的地位の低い出身だった。旅団に入ることは、労働党の党員になるための数少ない方法のひとつであり、社会的に高い地位を得ることができた。2021年、脱北者のチョ・チョンヒは、青年ショック旅団での生活を実体験している。工事は日の出前に始まり、しばしば深夜まで続いたとチョ氏は言う。トンネル掘削中に壁が崩れ落ち、背中を負傷したこともあった。仲間の中には死亡した者もいれば、足や手首を骨折した者もいた。鉄道工事現場に派遣されたとき、作業員たちは寒空の下、その場しのぎのテントで眠った。「休みは年に10日ほどでした」と現在61歳のチョーは言う。「週休2日制を知ったのは、韓国に来てからです」。
北朝鮮が若者の衝撃旅団に頼っていることは、この国の将来にとって何を意味するのだろうか。北朝鮮メディアは、白頭山英雄青年衝撃旅団が洪水に見舞われた平安北道(中国と国境を接する北朝鮮北西部)を支援するために派遣された後、その活動を徹底的に取り上げた。若者たちの活動については毎月更新され、彼らが愛国的で意欲的であると称賛された。ソウルにある北朝鮮研究所の金英洙所長は、「青年ショック旅団のメンバーは、どういう人物が徴兵されるかよって変わるが、その構成がどのようなものであれ、金正恩政権は、命令には盲目的に従うよう北朝鮮国民を教化するのに効果的な組織であると悟ったのだ」と語る。「若者のメンバーは変わっても、金体制への忠実さを証明する衝撃旅団の目的は変わらない」。
以上のように、金正恩総書記は北朝鮮が社会主義の楽園であるという幻想を維持するために彼が「危険な毒物」と呼ぶ西側の情報やコンテンツの流入を防止することに精力を注いでいる。そのため金総書記は最近、白頭山英雄青年衝撃(ショック)旅団を組成しプロパガンダの中心的役割を与えたと記事は報じる。衝撃旅団は大規模な建設プロジェクトなどの肉体労働に従事し体制への忠誠心を養う準軍事組織のひとつとされているが、ナチス・ドイツの体制維持に利用されたヒトラー=ユーゲントを思い起こさせる。衝撃旅団はまさに体制維持のための青少年組織と言え、構成員は現在30万人と報じられているが、今後さらに拡充されていくとみられ注目していきたい。
東南アジアほか
☆ 米中対立のなかで次の一手を考える東南アジア
ドナルド・トランプ米大統領が関税の脅威を振りかざし、中国の貿易黒字が記録的な10億ドルに迫るなか、東南アジアの国々は貿易とハイテクに関する緊張をどのように乗り切っているのだろうかと、2月6日付フィナンシャル・タイムズが疑問を提起する。記事は、東南アジアは経済的には相互につながっているが政治的には中立であることが多く、貿易摩擦のコストを軽減するだけでなく、それを活用する努力の実験場となっているが、そこから経済価値を引き出すのが予想以上に難しいと述べ、以下のように2つの問題を指摘する。
第1は域内で激化する競争である。タイやマレーシアのような国々は、かつては台頭する虎とみなされていた。しかし、1997年のアジア金融危機の後、中国が世界貿易機関(WTO)に加盟し、多くの外国投資を吸い寄せたため、東南アジアにはほとんど何も残されなかった。しかし、これが今、変わった。低関税でコスト競争力のある中国以外の製造拠点を求めているのは、欧米企業だけではない。中国企業も関税や規制を回避するためにオフショア組み立てを探している。そのため、投資は東南アジアに集中している。しかし、そこから付加価値を引き出すのは予想以上に難しいことが判明している。企業は税控除や補助金を要求する際に政府を翻弄することに長けており、多くの地域が同じビジネスをめぐって競合している。
第2は、規制緩和を求めて参入してくるメーカーが域内で経済価値をほとんど付加しない場合が多いことだ。マレーシアがデータセンター・ブームの恩恵を受けているのは、電力が余っていることもあるが、米国の輸出規制によって最近までAIチップの無制限な出荷が認められていたためでもある。これらのデータセンターの一部は国内市場にサービスを提供しているが、中には自国ではアクセスできない中国の顧客にAIクラウド・コンピューティング・サービスを提供しているところもある。マレーシアのデータセンターには250億ドルもの投資が行われている。しかし、地元企業にどれだけの価値がもたらされたのだろうか。マレーシアは余剰電力をデータセンターに売ることができ、建設業の雇用を獲得できる。しかし、データセンターの最大のコストは、内部のチップとサーバーである。クラウド・コンピューティングの利益は、データセンターの土地を所有する国ではなく、チップメーカーやソフトウェア・プロバイダーにもたらされることがほとんどだ。
東南アジアの政府関係者の中には、中国の製造工場が同地域に進出することに同様の懸念を抱いている者もいる。欧米企業が現地に工場を開設するのは、自国よりも安価な現地の労働力や部品供給を受けたいからだ。中国企業が進出すると、ほとんどの部品を中国から輸入するだけでなく、中国人労働者も輸入することが多い。東南アジア諸国は、中国企業に現地での購入を促し、技術を共有させることができるだろうか。中国は外国企業に技術移転を促すことで豊かになったので、中国政府は自国企業に課せられる技術移転義務に対抗する策を心得ている。中国はすでに電子機器の組み立てやEV技術の輸出規制を課している。中国はまた、専門知識の流出を遅らせるため特定の熟練労働者の海外渡航を阻止している。
東南アジアの再工業化は、この地域の指導者には魅力的なスローガンだが、中国はこれを競争上の課題と考えている。東南アジアの地元メーカーも自国に新たに建設された中国の工場を競争相手とみなすことが多い。しかし政府関係者はしばしば中国の投資を歓迎している。東南アジアの製造・組立拠点は、欧米のサプライチェーンと深く統合して成長してきた。例えば、日本の自動車メーカーは何十年もの間、タイの部品メーカーから部品を調達してきたし、マレーシアのチップ組立工場やテスト工場は、主に欧米の半導体企業にサービスを提供している。
しかし、中国企業の自動車やチップにおける世界市場シェア拡大は、中国メーカーが東南アジアのサプライチェーンと統合した場合にのみ、東南アジア経済に利益をもたらす。しかし、この地域のビジネスリーダーたちは、このようなことが起こるのはあまりに稀だと不満を漏らしている。中国の電気自動車大手は高度に垂直統合されており、そのサプライヤー・ベースは中国に偏っている。この地域の中小企業は、欧米のサプライチェーンに売り込むことを学んできた。彼らは、中国の巨大製造業に販売するチャンスはほとんどないと考えている。「象が戦えば、草が苦しむ」ということわざは、両大国に圧迫されていると感じている国々がよく引用する。
しかし、トランプ大統領の関税と中国のとどまることを知らない輸出増加への恐怖と並んで、東南アジアの国々も貿易戦争のチャンスを活かそうとしている。多国籍企業が中立の立場を求めるなか、世界最大の2つの経済大国を互いに翻弄することは明らかな戦略である。しかし、サプライチェーンのシフトから価値を引き出すことは、想像以上に難しい。
以上のように、東南アジアは激化する米中対立のはざまでチャンスを活かそうとしているが、簡単には経済的価値を手に入れられないと記事は指摘する。それは規制緩和を求めて参入してくるメーカーが域内で経済価値をほとんど付加しない場合が多いからであり、とりわけ参入してくる中国企業が部品も労働者も本国から輸入したり、本国政府の指導もあり、技術移転や専門知識の流出にも極めて慎重であったりするからである。また多くのデータセンターが東南アジアに建設されているが、データセンターの最大のコストは内部のチップとサーバーにあり、その利益はデータセンターの土地所有国ではなく、チップメーカーやソフトウェア・プロバイダーにもたらされるからでもある。とはいえ、記事が指摘するように米中貿易戦争は東南アジアの指導者に再工業化を達成する貴重な機会をもたらしており、これを単なる魅力的なスローガンで終わらせてはならないであろう。
インド
☆ モディ政権、経済活性化策を発表
インド経済は4年ぶりの低水準となる6.4%まで減速すると予想されているが、そうした経済の活性化のためにナレンドラ・モディ連立政権は2月1日、中間層への減税を宣言し、事業活動を促進するための措置を通年予算で発表したと同日付フィナンシャル・タイムズが伝える。記事によれば、委員会が組成され、ビジネスに関わる国の多様な規則、認証、ライセンス、許可を精査する。委員会は「原則と信頼に基づいた軽いタッチの規制の枠組みが、生産性と雇用を束縛から解き放つ」と宣言している。
インドのビジネス界の大物の何人かは、インド政府に対し、煩雑な書類作成やコンプライアンスの負担が事業運営の妨げになっていると訴えてきた。彼らは、投資を刺激し雇用を創出するために労働と土地市場の規制改革を提唱している。世界第5位の経済大国であるインドを活性化させるため、シタラマン財務相は中所得層のインド人と中小企業に対する優遇措置を導入した。これらの施策は、モディ首相とその政権の極めて重要な支持基盤である都市部の消費者の需要を喚起するものでもある。同財務相は2月1日、納税者が無税となる個人所得税の基準額を70万ルピーから1万2,000ルピー(1万3,842米ドル)に引き上げると発表した。
政府は、予算の前日に発表した経済調査の中で太陽光発電、先端バッテリー、電気自動車などの重要産業のサプライチェーンにおける中国への依存など、若者と経済が直面している課題を強調した。政府首席経済顧問(CEA)のV・アナンタ・ナゲスワラン氏が執筆した調査報告書は、インドの中央政府と州政府に対し、「今の道から抜け出し」、規制緩和を行うよう促し、さもないと「経済停滞とまではいかなくても、経済成長が停滞する高いリスク」に直面すると警告した。
また同調査は、大企業の賃上げ努力が不十分であることを非難した。ナジェスワランは前年の調査の序文で、インドの企業部門は「過剰利潤で溢れかえっており、雇用創出のる責任を真剣に負うべきだ」と述べていた。報告書は、今年度の実質GDP成長率を6.4%と予測し、2023~24年度の8.2%から低下するとした。政府は来る2025~26年度の成長率を6.3%から6.8%と予測している。今回の調査では、来年度の実質GDP成長率を政府予測どおりの6.3%から6.8%と予想しているが、これは前年度の調査での予測値6.5~7%を下回るものである。
上記のように報じた記事は最後に、進歩の真の阻害要因は中央政府と州政府自身であることがはっきりと明言されたのは、おそらく今回が初めてだろうと述べ、しかし、インドの庶民は悲観することはなく、国の強固なマクロ・ファンダメンタルズと強固で安定した金融システムのおかげで6%前後の比較的低い成長率でも、それを楽しみにしているとコメントする。
以上のように、政府は景気刺激策として中間層への減税や規制改革を打ち出した。無税となる個人所得税の基準額を引き下げ、また大企業の賃上げ努力が不十分だと政府調査報告書で強調し、大企業に対し賃上げに向けて圧力をかけている。なお中央銀行のインド準備銀行も2月7日、政策金利を0.25%引き下げ6.25%にすると発表し、景気下支えの姿勢を鮮明にした。政策金利の引き下げは2020年5月以来、4年9か月ぶりとなる。準備銀行はこれまで通貨安とインフレへの対応から高い金利を維持してきたが、去年12月の消費者物価指数が前年同月比5.2%上昇と目標の上限とする6%を下回り、マルホトラ総裁は「インフレの動向を踏まえ、金融緩和の余地が生じた」との表明していた。また同行も、今年度のGDP伸び率の予測を6.4%に下方修正し、昨年度の8.2%から減速する見通しを示したと報じられている。
§ § § § § § § § § §
主要紙社説・論説欄から
第2次トランプ米国政権の発足
米国で1月20日、ドナルド・トランプ第2次政権が発足した。以下は、米新政権の始動に関連する主要メディアの報道や論調である。メディアは、西側陣営に対して利益だけでなく、価値観の擁護にも動くべきだと主張すると共にトランプ関税に対しては、それを無視して米国を迂回した世界貿易システムの再構築を提言する。以下は、その要約である。
1月21日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは「Trump’s Inaugural of Optimism (【社説】トランプ氏就任演説が伝えた楽観主義)」と題する社説で、トランプ新大統領の就任演説について第1次政権発足時よりはるかに良いメッセージで2期目を開始したと論じる。すなわち、第47代大統領となったトランプ氏は大半の米国民が歓迎するとみられる希望と楽観主義のメッセージを伝え、「米国民の大虐殺」という表現を使った2017年の就任演説とは対照的だと述べ、実際の計画を示しているなら、4年後に成功した大統領として退任する可能性があると評する。2017年の演説は、トランプ氏が大統領に選出されたことへの民主党とメディアの抵抗に対し、それと同じ暗いトーンで応じ、その後4年間の憎しみと分断の土台となったが、今回の演説のトーンとメッセージは、米国が常に偉大であり続けてきたし、新たな試練に立ち向かう中でさらに偉大になるとの内容だったと述べ、これはイーロン・マスク氏の影響が大きく、スティーブ・バノン氏的な要素が大幅に減り、すべてが良い方向に向かっていたと論評する。
前政権の実績に関しては、トランプ氏はいつもの誇張表現で「何年もの間、急進的で腐敗したエスタブリッシュメント(支配層)が国民から権力と富を搾取してきた。米国社会の柱は崩壊し、見たところ完全な荒廃状態だ」と語ったが、政府がかつてなく大きな存在になる一方、公共の安全と基本的サービスを提供するという政府本来の義務に関して米国民を失望させることがあまりにも多かった、とするトランプ氏の言い分は正しいとの見方を示す。また、法廷に出された証拠で明らかになったように、バイデン政権はソーシャルメディア上で批判する人々を抑え込んでおり、こうした検閲体制が終わるのは今回の大統領選で得られた最良の結果の一つだと主張する。
また今回の就任演説で注目点として、米国の過去に存在した最高の要素と未来への希望を結び付けたことを挙げ、この2つを結び付けることは、米国の復活に不可欠だと強調する。米国の文化的・政治的指導者たちは長年にわたり、米国社会には「体系的な人種差別」がはびこっていると述べ、米国は自由の理念ではなく奴隷を所有する欲望によって建国されたのであり、ほとんどの場合において世界中に破壊を広げていると国民に説いてきたと指摘。これに対しトランプ氏は、これまでの米国を築いてきた「探検家、建国者、イノベーター、起業家と開拓者」を称賛し、「人種差別をしない、能力主義の社会」という米国の中核的価値観を思い起こさせたと評する。そのうえで、米国人は、より良い未来を形成するために、この国の根本的な良さ―—われわれが不人気な言葉を使えるのであれば、米国が国々の中でも例外的な立場にあるという例外主義―—を再び信じる必要があると提言する。
次いで社説は、トランプ氏の演説で恐らく最も重要だった部分は、政治的に動機付けられた訴追行為をやめるとの約束だったと以下のように論じる。トランプ氏は「国の強大な権力を武器にして政敵を訴追することは今後、絶対にない。われわれはそれが起きることを容認しない。私のリーダーシップの下、われわれは憲法に従った、公正、公平で偏らない司法を復活させる」と述べた。これ以上ないほど明確な発言であり、バイデン時代と比較すると新鮮に感じられる。選挙期間中たびたび訴えてきた言辞と違い、トランプ氏が本当にそうするのであれば、彼は政治的な行き詰まりに至るような報復の動きを回避することによって、この国と大統領としての自分を救うことになるだろう。
社説は最後に警戒すべき点として、国境警備(不法移民)問題とエネルギーの2つの問題についてトランプ氏による国家非常事態宣言の可能性を挙げる。非常事態宣言によってトランプは、行政権の行使と連邦政府のリソースの活用について大きな権限を手に入れるが、こうした宣言は真の緊急事態のためにとっておくべきものであり、トランプ氏はこの2つの優先課題の目標達成のために特別な権限は必要ではないと断じる。トランプ氏は、巨大な官僚機構の力の抑制を約束しているが、緊急事態宣言は官僚機構の力を逆に強めると批判する。ただし社説は次のように締めくくる。米国の民主主義は今日、脅威にさらされていると言われるが、大統領就任演説が一つの指標になるとすれば、おそらく多くの人々が考えているほど深刻な状況ではない。対抗勢力は権力の移譲過程に敬意を表し、トランプ氏の支持者は厳粛さと同時に喜びを示している。第2次トランプ政権は好ましいスタートを切った。われわれがほんの数カ月前に危惧していたよりも。
こうしたトランプ新政権に対して1月25日付フィナンシャル・タイムズは社説「How to respond to Trump 2.0 (第2次トランプ政権にどう対応するか)」で、アメリカの同盟国は、自国の利益に加えて価値観も守らなければならないと以下のように論じる。
トランプ氏は予想どおり大統領令やメモ、誓約、思索、そして過熱する言葉の嵐で2期目をスタートさせた。このようにアメリカ資本主義のアニマル・スピリットを全面的に解き放ったことで一部の伝統的な同盟国は狼狽しており、世界は今、トランプ第2次政権の下で吹き荒れるだろう旋風にどう対応するかを決めなければならなくなった。アメリカもまた、対処しなければならない大きな問題を抱えている。トランプ新大統領の就任から数日間は、返り咲きを確実にした問題、特に移民の削減と彼の支持者が「ディープ・ステート」と呼ぶ連邦政府の削減が焦点となった。
そのうえで社説は、トランプ氏が自分を大統領府に送り戻した有権者の懸念に耳を傾けるのは正しいが、同氏が下劣な本能に溺れ、民主主義の柱を弱体化させ始めたらどう対応すべきかと問題提起し、それには利益プラス価値観というシンプルな答えがあると述べる。例えば、トランプ大統領のパリ協定離脱は、EUが脱炭素化政策を遅らせる口実にはなり得ないし、米国内でも裁判所は、憲法修正第14条に規定されている出生権付き市民権の廃止を求めるなど、トランプ大統領の物議を醸す構想をめぐる大論争に備えるべきだと主張する。
さらに社説は以下のように論じる。トランプ大統領の発足に当たっての突撃姿勢は、ひとつの時代が終わったという感覚を広く浮き彫りにした。アメリカの同盟国は多国間秩序への脅威を強めているとして、うんざりした反応を示している。しかし、世界の他の多くの国々がトランプ大統領を好意的に見ており、内向きのアメリカを好んでいることに注意すべきだ。彼の構想の中には、望ましい結果をもたらすものもあるかもしれない。プーチンをウクライナの公正な和平交渉のテーブルに着かせるには、トランプ大統領の対ロ制裁強化の脅し以上のものが必要だろう。しかし、今週の大統領の露骨で予期せぬ警告は、正しい方向への一歩であり、彼がいかに予測不可能性を資産とみなしているかを思い起こさせるものだった。
もっとはっきり言えば、同盟国はトランプ大統領のいくつかの処方箋によって行動が必要不可欠となる可能性があるのだ。前任期にはNATO加盟国に国防費を増やすよう促したように、トランプ氏は今回、規制や官僚主義の緩和、減税を支持しており、EU指導者たちは大陸の競争力という問題に緊急に立ち向かわなければならなくなろう。それはまだ始まったばかりだ。トランプ大統領が中国や欧州と新たな貿易戦争を始めなかったからといって、来週にも貿易戦争が始まらないとは限らない。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は今週、本紙に対し、同首相や他の東アジアの指導者たちは、最初の混乱期が過ぎれば、世界貿易システムは無傷で存続すると考えていると語った。彼が正しいことを祈るしかない。
次に、トランプ新大統領の貿易や関税政策に関して1月16日付ワシントン・ポストは「There’s another way to fight a trade war (貿易戦争に対抗するには別の方法がある)」と題する社説で、中国その他の標的となっている国々は報復や譲歩に打って出るのではなく、アメリカ市場に代わる選択肢を見つけるべきだと以下のように論じる。
2018年、トランプ大統領が敵味方双方からの輸入品に関税をかけ始めた後、中国、メキシコ、カナダ、EUはケンタッキー州のバーボンを標的にし、同州出身の当時の上院院内総務ミッチ・マコーネルに鋭いメッセージを送った。中国とメキシコは豚肉にも狙いを定め、米国産豚の主要生産地であるアイオワ州のチャック・グラスリー上院議員に圧力をかけた。今回、豚肉にメスを入れることで、サウスダコタ州のジョン・チューン新上院院内総務にプレッシャーがかかるかもしれない。しかし、この方策はおそらく徒労に終わるだろう。実際、トランプ大統領の政治的本能を考えれば、大統領の怒りを買う可能性の方が高いだろう。譲歩でトランプをなだめようとする必要もない。スイス拠点の監視団体Global Trade Alertは、北米自由貿易協定を再交渉した後、メキシコとカナダに対して行った2018年のときのように、トランプによる新たな脅しと要求の再来は止められないだろうと警告する。実際、トランプに媚びへつらう国は、自らを「標的」に変えてしまう危険がある。
最良の策は米国を回避し世界貿易システムを再構築することだ。各国は米国のいじめに憤慨しているかもしれないが、より良い戦略は関税を無視することだ。海外の指導者たちは米国を回避する道を探し、世界貿易システムの再構築に取り組むべきである。トランプ大統領が課そうとしている関税は、主に米国を苦しめるものなのだ。大流行後のインフレにあえぐアメリカの消費者に対して輸入品の価格を押し上げ、輸入中間財のコストを引き上げて輸入鉄鋼を購入するデトロイトの自動車メーカーなどの輸出企業を含む米国企業に打撃を与えるだろう。ピーターソン国際経済研究所によると、トランプ大統領が外国からの全輸入品に10%ポイント、中国からの輸入品に60%ポイントの追加関税を課すと、他国からの報復の有無にかかわらず、アメリカの国内総生産と雇用が数千億ドル減少するという。
中国製品に対する関税引き上げは、中国が見返りに何もしなかったとしても米国の国内総生産(GDP)を現在のドルで1,650億ドル弱減少させるという。同様に、他のすべての国に対する新たな関税はGDPを3,600億ドル減少させる。他の国々が反撃に出れば、米国経済はより大きな打撃を受けるが、そうすることでこれらの国々は自らをも傷つけることになる。中国がアメリカ製品に60%の関税を課した場合、関税引き上げによる中国のGDPへの打撃は、トランプ大統領の任期中、報復なしの場合の8,200億ドルから9,800億ドルに増加する。メキシコの経済的損失は反撃した場合、反撃しなかった場合の360億ドルから670億ドルに増加する。
自分で自分の足をすくうよりも、中国がトランプ大統領の第1次政権時代に関税を課された際に取った行動を真似たほうがいい。他国からの輸入品に対する関税を引き下げたのだ。これによりアメリカの輸出企業は不利になり、中国経済は世界から安い輸入品を引き寄せて利益を得た。2018年以降、中国の対米輸出は激減しているが、輸出全体は持ちこたえている。その教訓は明確だ。米国が暴走するなら、他の国々は互いに緊密な貿易関係を築くのが賢明だ。このような戦略は、トランプ大統領が手を緩める可能性さえある。米国は大きな市場だが、世界の輸入の13%を占めるにすぎない。多くの国々は、米国へのアクセスを失ってもかなり簡単に埋め合わせできるだろう。そうすれば、トランプ大統領が始めようとウズウズしている貿易戦争の無意味で自滅的な性質を納得させられるかもしれない。
最後にトランプ新政権の対中政策などの外交安保政策について1月19日付ニューヨーク・タイムズは、「Biden Made a Global Push to Constrain China. What Will Trump Do? (中国封じ込めを世界的に推進したバイデン、トランプはどうするか)」と題する記事で、トランプと習近平には別の計画があるかもしれないと以下のように論評する。
大西洋問題で深い経験を積んできたバイデン政権は、中国が支配的なプレーヤーであろうとする太平洋にも焦点を当て、中国に対抗するための同盟関係の構築に注力してきた。しかしトランプ次期大統領は中国に対する異なるアプローチを示唆している。その就任式に習近平国家主席を招待、両者はすでに電話会談し、習氏は韓正副主席を式典に派遣することにしている。バイデン政権の中国に対する最後の活動は対照的で、バイデン氏は先週の日曜日、日本、フィリピンの首脳と電話会談を行い、自身が構築を支援した新しい三国間安全保障協定を固めた。ブリンケン国務長官は今月、最後の公式訪問で韓国と日本を訪れた。バイデン氏とその側近に言わせれば、トランプ氏に、米国の最大のライバルである中国に対するり研ぎ澄まされた競争力を手渡そうとしているのだ。バイデン氏の外交政策のなかでも、中国に対するアプローチは最終的に各要素が連続して一つの集合となるコンティニューム(連続的なもの。continuum)として歴史家に見なされるだろう。
ホワイトハウスのジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官はインタビューで、米国と中国は明らかに激しく競争しているが、それでも関係は安定的な要素を維持しており、この4年間で双方の関係管理は大きく進化したと述べ、中国共産党は現在、バイデンチームが提唱する 「管理された競争」という枠組みを受け入れていると語った。「われわれは管理された競争というわれわれの理論に固執していくだけだ」と述べる。トランプ氏がそれをどうするのかは不明だ。彼は独裁的な習近平を称賛しており、主に経済交渉のレンズを通して中国を見ている。イーロン・マスクを含むトランプ氏の億万長者アドバイザーたちは、中国とのビジネス取引を維持し、おそらく拡大したいと考えている。しかし、トランプ氏の外交安保政策担当補佐官のトップは、バイデン氏に近い。彼らは、米国は多くの側面をとおして、安全保障と経済のあらゆる手段を駆使して中国をけん制しなければならないと主張している。
アメリカの若者に人気のある中国のソーシャルメディアアプリ、TikTokの使用禁止をトランプ氏が実施するかどうかが、早期の試金石のひとつとなるだろう。バイデン氏は昨年、TikTokの親会社であるByteDance社が「外国の敵」と関係のない投資家に売却しない限り、国家安全保障上の懸念に基づいてTikTokを禁止する超党派の法案に署名した。ByteDance社は現在もTikTokを所有しており、ホワイトハウスは金曜日、禁止令の実施はトランプ氏次第であると発表した。トランプ氏は土曜日に、TikTokに禁止令から90日間の猶予を与えたいと述べ、同社の最高経営責任者は大統領就任式に出席する予定だと語った。
トランプ氏のチームにも関係する中心的な疑問は、バイデン政権が抑止と挑発の間で適切なバランスをとったかどうかである。中国が軍備増強を加速させ、この地域でより攻撃的になっているのは、裏庭でのアメリカの動きが原因なのだろうか。習近平主席は、首脳会談でバイデンの看板政策である人工知能の開発に必要な高度な半導体チップの輸出規制を封じ込めの一環だと直接批判した。2022年に第一弾を発表した後、サリバン氏はこれを「小さな庭、高いフェンス」を設けることで「基礎技術」をライバルの手に渡さないようにする政策だと説明した。一部の専門家は、この政策は裏目に出ており、中国がイノベーションを加速させることを実際に後押ししていると主張する。中国企業がアメリカの技術に依存しなければしないほど、アメリカの中国に対する影響力は弱まるというのだ。サリバン氏は、この批判は「時系列で間違っている」と述べる。
バラク・オバマ政権で中国担当ディレクターを務めたライアン・ハス氏は他の政策上の欠点を3つ挙げる。アジアに対する真剣な貿易アジェンダの欠如、臆病に見えた中国への対応、発展途上国よりも先進民主主義国とのやり取りに安住したようにみえる中国政策である。しかし全体としては、この政策はうまくいったと言う。「バイデンが大統領に就任したときよりも、アメリカは中国に対してより強い競争力を持つようになった」。
結び:以上のようなメディアの論調のなかで、まずトランプ氏の就任演説に対して一部のメディアが肯定的に評価していることが目を引く。ウォ-ル・ストリート・ジャーナル社説は、演説は希望と楽観主義のメッセージを伝え、これが実際の計画を示しているなら、トランプ氏は4年後に成功した大統領として退任する可能性があると述べ、第2次トランプ政権は好ましいスタートを切ったと評する。そうした見方の根拠として前政権の幾つかの欠陥を挙げ、大きな政府の下で政府本来の義務である公共の安全と基本的サービスの提供で米国民を失望させ、ソーシャルメディア上で批判派を検閲し抑圧したことなどを挙げる。これに対しトランプ演説は、米国の過去に存在した最高の要素と未来への希望を結び付け、「人種差別をしない、能力主義の社会」という米国の中核的価値観を思い起こさせたと指摘し、そのうえで米国が世界で例外的な立場にあるという例外主義を再び信じる必要があると強調する。希望的観測を込めていたとしても、注目に値する見方である。ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、ビジネス寄りの共和党系メディアであり、こうした見方を示したと思われる。ただし最後に例外主義に焦点を当てたのは、人権擁護の観点からとしても、過去における孤立主義的な米外交を彷彿させ誤解を呼ぶ恐れがあり、問題があるとも言えよう。
ウォ-ル・ストリート・ジャーナル社説はまた、トランプ氏が憲法に従った、公正、公平で偏らない司法を復活させると述べ、トランプ氏が本当にそうするのであれば、彼は政治的な行き詰まりに至るような報復の動きを回避することによって、この国と大統領としての自分を救うことになるだろうと論じる。同時に警戒すべき点として、不法移民対策とエネルギーの2つの問題についてトランプ氏による国家非常事態宣言の可能性を挙げ、宣言は真の緊急事態のためにとっておくべきものと諫めている。いずれも正論といえよう。社説はまた、この演説に対するイーロン・マスク氏の影響に言及している。これは新政権の今後の運営に与える同氏の影響への注意を喚起する指摘といえよう。
上記ウォ-ル・ストリート・ジャーナル社説は米国の国内問題に焦点を当てたが、1月25日付フィナンシャル・タイムズ社説は対外政策と内政の両方に言及する。トランプ氏はアメリカ資本主義のアニマル・スピリットを全面的に解き放ち、一部の伝統的な同盟国は狼狽しており、世界は今、トランプ第2次政権の下で吹き荒れるだろう旋風にどう対応するかを決めなければならなくなったと述べ、アメリカの同盟国は、自国の利益に加えて価値観も守らなければならないと主張する。同時に内政面でアメリカも大きな問題を抱えているとし、移民削減と肥大化した連邦政府の効率化を焦点の問題として挙げる。
利益プラス価値観というシンプルな答えに関連して、トランプ大統領のパリ協定離脱に触れ、社説はEUが脱炭素化政策を遅らせる口実にはなり得ないと念を押しているが、そのとおりであり、この助言は、脱炭素以外も問題にもあてはまるだろう。トランプ政権の規制や官僚主義の緩和、減税支持の姿勢がEUに対して競争力の強化という課題を提起するのは、その一例である。トランプ構想の中には、望ましい結果をもたらすものもあるかもしれないという見解は、些か突飛だがそうした柔軟な見方が必要なことは事実であろう。予測不可能性を売り物にするトランプ政権では、トランプ大統領の対ロ制裁強化の脅しなど何でもありである。それだけに、ここぞという問題が起きた際には立ち上がることが大事になる。米国の内政面でも出生権付き市民権の廃止をめぐる問題など大いに論議すべきであろう。
トランプ大統領の貿易や関税政策について論じた1月16日付ワシントン・ポスト社説は、トランプ関税の標的となった国々は報復や譲歩ではなく、アメリカ市場に代わる選択肢を見つけるべきだと論じる。きわめて注目に値する提言である。社説は共和党の有力政治家への圧力、あるいは譲歩でトランプをなだめようとする試みは怒りを買うか、徒労に終わると警告し、最良の策は米国を迂回し世界貿易システムを再構築することだと主張する。各国は米国のいじめに憤慨しているだろうが、より良い戦略は関税を無視し、米国を回避する道を探し、世界貿易システムの再構築に取り組むべきだと説く。
確かにトランプ関税はアメリカの消費者にとっては輸入品の価格を押し上げ、輸入中間財のコストを引き上げて自動車メーカーなどの輸出企業を含む米国企業に打撃を与える。現にピーターソン国際経済研究所は、全輸入品に10%ポイント、中国からの輸入品に60%ポイントの追加関税を課すと、他国からの報復の有無にかかわらず、アメリカの国内総生産と雇用が数千億ドル減少すると警告する。参考になるのは、トランプ大統領の第1次政権時代に関税を課された中国が取った行動、すなわち他国からの輸入品に対する関税引き下げである。これによりアメリカの輸出企業は不利になり、中国経済は世界から安い輸入品を引き寄せて利益を得たと社説は指摘する。因みに中国は今回、トランプ大統領の追加関税に強く反発しているものの、報復措置として世界貿易機関への提訴の他に追加関税の賦課は明確に打ち出していない。
1月19日付ニューヨーク・タイムズは、バイデン政権は中国封じ込めを世界的に推進したが、トランプはどうするかと問題提起する。バイデン政権は太平洋にも焦点を当て、中国に対抗するための同盟関係の構築に注力してきたと述べ、この4年間で米中関係の管理は大きく進化し、中国共産党は現在バイデンチームが提唱する「管理された競争」という枠組みを受け入れている、とのバイデン政権のサリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)の言を紹介する。そして、バイデン政権は、トランプ氏に米国の最大のライバルである中国に対するり研ぎ澄まされた競争力を手渡そうとしていると論評する。
バイデン政権が対中関係を一定の安定した状態に持って行ったことは確かであろう。
問題は、トランプ氏がそれをどうするかであるが、記事は、トランプ政権内に2つの勢力があると分析する。一つは、主に経済交渉のレンズを通して中国を見ているイーロン・マスクを含むトランプ氏の億万長者アドバイザーたちである。中国とのビジネス取引を維持し、おそらく拡大したいと考えている。もう一つは、トランプ氏の外交安保政策担当官など、米国は安全保障と経済のあらゆる手段を駆使して中国をけん制すべきだとするバイデン政権と同様の考えを持つ勢力である。前者は対中融和派、後者は対中強硬派といえるだろう。ニューヨーク・タイムズ記事は、中国のソーシャルメディアアプリ、TikTokの使用禁止をトランプ氏が実施するかどうかが、早期の試金石のひとつとなろうと指摘する。これについてトランプ氏は18日に、TikTokに禁止令から90日間の猶予を与えたいと表明している。いわば、当面は対中融和派の意向を体して動いていると思われる。しかし、対中関係ではその他にも関税や人工知能の開発競争、高度半導体チップの輸出規制などの大きな問題があり、広く動向を注視していく必要がある。また米新政権が中国以外のアジア諸国に対して、どのような貿易、安保政策を打ち出すのか、そして今のところ明確な指針を示していない対日政策が今後、どのような展開をみせるのか。いずれも目が離せない。
以上、メディアはトランプ第2次政権は希望と楽観主義の就任演説で順調なスタートを切ったとの見方やトランプ政策への柔軟な対応への呼びかけ、そしてトランプ陣営内での中国政策をめぐる融和派と強硬派の勢力争いの指摘など、注目すべき見方や分析を提示する。なかでも最も注目すべきは、利益プラス価値観による対応とトランプ関税無視の提言であろう。前者は、例えばトランプ大統領が民主主義の柱を弱体化させ始めた場合に米国民に対して出生権付き市民権の廃止を求めるなど、トランプ大統領の問題含みの構想をめぐる大論争に備えるべきだと訴える。トランプ大統領のパリ協定離脱は、EUが脱炭素化政策を遅らせる口実にはなり得ないと警告する。多国間秩序への脅威が高まるなか、EU指導者たちは大陸の競争力という問題に緊急に立ち向かわなければならないと迫る。
後者では、メディアはトランプ政策の眼目となっている関税政策に関連してこれを無視し、米国を迂回する世界市場の構築を呼びかける。カナダやメキシコなど友好国を巻き込んだ関税旋風が西側陣営内で吹き荒れるなか、きわめで示唆に富む提案である。鍵は、第1次トランプ政権で巧みに対応した中国が握っていると言えよう。中国が今回もそうした行動をみせるのか。中国が前回の経験を生かして巧みに動けは、トランプ関税は日本を含む西側陣営の結束を乱す一方で、中国を利する結果となる可能性がある。中国の動向と西側諸国の対応を注視していく必要がある。
§ § § § § § § § § §
(主要トピックス)
2025年
1月16日 中国政府、昨年の国内総生産が前年比5%増と発表。
19日 韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)、「非常戒厳」宣言を巡る内乱容疑で尹錫悦大統領を逮捕。現職大統領の逮捕は韓国史上初めて。
21日 トランプ米大統領、中国に対して2月1日に10%の関税賦課を表明。
24日 日本銀行、政策金利の0.25%利上げを決定。
シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)、2020年以来となる金融緩和を実施。今年のインフレ率と経済成長率が当初予想を下回るとの見通しを発表。
27日 中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席、2026〜30年の新5カ年計画をまとめる意向を表明。
28日 中国で春節(旧正月)始まる。今年は2月4日までの8連休。
31日 台湾当局、情報漏洩などセキュリティー上のリスクを理由として中国のディープシーク開発の生成AI (人工知能)のサービス利用を禁止。
2月 1日 インド政府、2025年度(25年4月〜26年3月)の予算案を発表。中間所得層の支援のため所得税減税や雇用対策を盛り込み、財政出動で景気刺激。
2日 中国商務省、トランプ米大統領の対中10%追加関税の決定に反発、世界貿易機関(WTO)への提訴と相応の対抗措置を表明。
4日 トランプ米政権、対中追加関税を発動、中国からのすべての輸入品に10%の関税を賦課。中国も報復措置を発表。
7日 インド準備銀行(中央銀行)、経済の減速が懸念されるなか、政策金利の0.25%引き下げを発表。およそ5年ぶりの利下げ。
石破首相、訪米。トランプ新大統領と初の首脳会談。トランプ米大統領、日本製鉄のUSスチール完全所有ではない投資案への支持を表明。
10日 トランプ米大統領、鉄鋼・アルミニウム製品に対する25%の追加関税の日本を含む全ての輸入品への適用を決定。
13日 インドのモディ首相、訪米。トランプ米大統領と会談。対米貿易黒字の削減や不法移民対策について協議。
トランプ米大統領、米輸入品に関税を課する全ての国に「相互関税」を課すと発表。
14日 台湾の頼清徳総統、防衛費を域内総生産(GDP)比で3%以上に引き
上げると表明。
15日 日米韓3カ国、独で開催中のミュンヘン安全保障会議にあわせて外相
会合を開催。第2次トランプ政権の発足後初。
主要資料は以下の通りで、原則、電子版を使用しています。(カッコ内は邦文名) THE WALL STREET JOURNAL (ウォール・ストリート・ジャーナル)、THE FINANCIAL TIMES (フィナンシャル・タイムズ)、THE NEWYORK TIMES (ニューヨーク・タイムズ)、THE LOS ANGELES TIMES (ロサンゼルス・タイムズ)、THE WASHINGTON POST (ワシントン・ポスト)、THE GUARDIAN (ガーディアン)、BLOOMBERG・BUSINESSWEEK (ブルームバーグ・ビジネスウィーク)、TIME (タイム)、THE ECONOMIST (エコノミスト)、REUTER (ロイター通信)など。なお、韓国聯合ニュースや中国人民日報の日本語版なども参考資料として参照し、各国統計数値など一部資料は本邦紙も利用。
バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座教授
前田高昭
PDF版