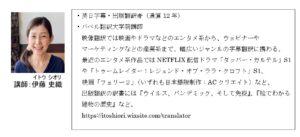2025年10月22日 第374号 World News Insight (Alumni編集室改め) リンガフランカの時代に、日本人はいかに英語と向き合うべきか
―Plain Englishが示す未来 バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
世界をつなぐ言語としての英語
いま、地球上にはおよそ八十億人の人々が暮らしている。その人々が話す言語は七千を超えるといわれるが、国境を越えて互いに意思を伝え合うとき、実際に使われている言語はほんの数種類にすぎない。
その中で圧倒的な存在感をもっているのが、英語である。最新の推計によれば、英語を母語とする人は約四億人(世界の五%)。一方、第二言語として英語を使う人は十億人以上にのぼり、合わせて十五億人(約二割)が英語を話す。つまり、世界の五人に一人が英語を使っている計算になる。もはや英語は「英語圏の言葉」ではなく、地球規模で共有される共通語=リンガフランカとなっているのである。
キングズ・イングリッシュの終焉と多様化する世界の英語
興味深いのは、その中心にあるはずの「キングズ・イングリッシュ(King’s English)」を話す人が、実際にはわずか二百万人(0.002%)ほどしかいないという事実だ。
伝統的な英国上流階級や教育機関で守られてきた古典的な発音と語法を使う人々は、いまやごく少数派。世界の英語は、すでに彼らの手を離れ、アメリカ、インド、シンガポール、ナイジェリア、そして日本を含むアジアの非ネイティブたちによって再定義されつつある。
このように、英語が多様な話者によって使われる言語になったとき、もはや「正しい英語」とは何かを一概に言うことは難しい。発音や文法の違いよりも、「相手に通じるかどうか」「誤解なく伝わるかどうか」が重要になる。
つまり、これからの英語教育で問われるのは、模範的なネイティブ英語をまねることではなく、誰にでも伝わる明快な英語を書く・話す力である。
Babel-Style Plain Englishという新しい道
ここで注目してほしいのは、バベルグループが提唱する「Babel-Style Plain English(バベル流プレイン・イングリッシュ)」である。これは、言語学博士ピーター・スケアー氏による「Plain Written English 80ルール」を基盤に、バベルが長年の翻訳教育を通じて体系化した“読みやすく、誤解されない英語”の実践法である。
Plain Englishとは、難解な単語や抽象的表現を避け、簡潔で、具体的で、文の構造が明確な英語を指す。それは単なる「やさしい英語」ではなく、論理的で、正確で、思いやりのある英語である。ビジネス文書、法令文、学術文、ニュース記事など、専門的な内容を誰もが理解できる形に書き直すための言語技術ともいえる。
「伝わる英語」とは何か
たとえば、次のような対比がわかりやすい。
• × Prior to the commencement of the meeting, participants are requested to confirm their attendance.
• ○ Please check in before the meeting starts.
前者は形式的で堅く、読み手の負担が大きい。後者は簡潔で、行動がすぐに理解できる。
Plain Englishは、単語を単純化することではなく、相手の理解を中心に置く書き方なのである。
“正しさ”より“伝わる力”へ
この考え方は、実は日本語にも通じる。私たちは長いあいだ、「正しい英語」を目標にしてきたが、そもそも正しさとは誰の基準なのか。キングズ・イングリッシュを完璧に話すことが、果たして国際社会で通用する英語力なのだろうか。むしろ、非ネイティブが多数派となった現在、“通じる英語”、 “伝わる英語”こそが、真の国際英語としての価値を持つ。
日本人にとってのPlain Englishの意義
バベルスタイルのPlain Englishは、まさにそのための教育体系である。
日本人が自らの論理・思考・感性を英語というリンガフランカを通じて発信するための、「第二の母語」としての英語を育てる。そこでは、発音よりも構成力、語彙力よりも伝達力と説得力が重視される。
英語の世界的な多様化は、日本人にとって大きなチャンスでもある。これまで「ネイティブではないから」と引け目を感じていた人々も、いまや多数派である非ネイティブ同士の対話では、誰もが平等な立場に立てる。重要なのは、文化の違いを越えて、自分の考えを論理的に説明し、相手を理解する力だ。その基盤にあるのが、プレイン・ランゲージ(Plain Language)の発想である。
ことばの民主化とバベルの使命
Plain Englishは単なる語学教育ではない。それは「ことばの民主化」運動でもある。
複雑な専門用語や権威的な表現を排し、あらゆる人が理解し、議論し、判断できる社会をつくる。それがプレイン・ランゲージの理念であり、翻訳教育を通じて“知の共有”を掲げてきたバベルの理念と重なる。
リンガフランカの時代、英語はもはや特定の国の所有物ではない。それは私たち一人ひとりが使いこなすべき「道具」であり、文化と文化をつなぐ「架け橋」である。そして、その橋をより強く、しなやかにするのがバベル流Plain Englishの精神―すなわち「明快に書き、誠実に伝える」という姿勢だ。
英語を“使って創る言語”へ
日本人がこれから英語と向き合うとき、私たちは“学ぶ対象”としてではなく、“使って創る言語”としての英語を意識すべきである。
バベルスタイルのPlain Englishを通じて、英語を自分の思考の延長として使い、世界に向けて日本の知と感性を発信する。それこそが、リンガフランカの時代における「日本人の英語」のあり方であり、「世界をひとつにする方法」であり、そしてーバベルの使命でもある。