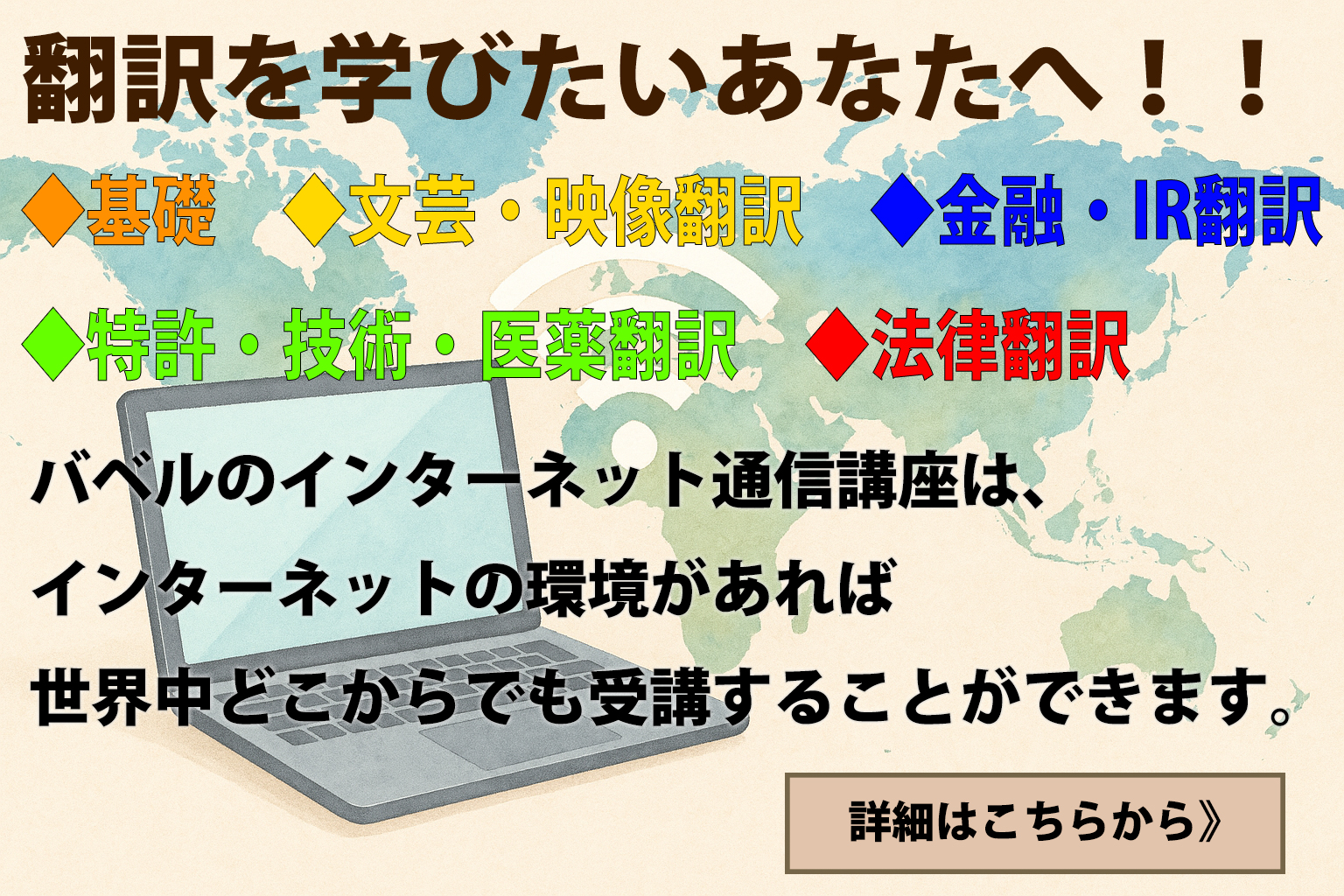2025年12月22日 第378号 World News Insight (Alumni編集室改め) AIが「正解」を出す時代に、経営が担うべき仕事 バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
今回は茂木健一郎の脳科学的世界観を紹介しよう。
AIの進化は、経営の前提を根底から変えつつある。かつて経営とは、「正しい判断を下すこと」、「最適解を見つけること」、「失敗を最小化すること」だと考えられてきた。しかし、茂木健一郎氏の脳科学的視点に立てば、その前提自体がすでに時代遅れになりつつあることが見えてくる。
「正解の時代」の終焉と“余白の価値”
AIは膨大なデータを高速で処理し、最適解や正解の確率を瞬時に算出できる存在となった。市場分析、需要予測、在庫管理、価格設定、こうした領域において、人間がAIに勝つ余地はほとんどない。だが、茂木氏が繰り返し指摘するように、人間の脳の本質は「正解を出す装置」ではない。むしろ脳は、曖昧さや余白、解釈の揺らぎを抱え込むための器である。
人間の思考は本来、直線的でも論理一貫的でもなく、遠回りや脱線、無駄を含んでいる。その「無駄」こそが、新しい意味や価値を生む源泉なのだ。AIが正解を出せる時代において、正解を求め続ける会議、過去データへの過度な依存、失敗を恐れる組織文化は、むしろ創造性を殺す。経営の核心は、「正解がない領域を、組織としてどう面白がれるか」、「余白を許容する文化をどう設計するか」へと移行している。
創造性とは「脳のノイズ」である
茂木氏は創造性について、「脳が生み出すノイズから生まれるものだ」と語る。ノイズとは、合理性から外れた思考、文脈の飛躍、予定調和を裏切る連想のことだ。AIは確率的に最も妥当な答えを出すが、意図的に“ズレる”ことはできない。
だからこそ、AI時代において人間が担うべき最後の領域は、創造性とひらめきである。経営の役割は、社員からノイズを排除することではなく、むしろノイズが自然に発生する環境を整えることに変わる。無駄な時間を許容すること、異質な人材を混在させること、専門の異なる者同士を衝突させること、雑談が生まれる構造をつくること、仕事の中に「遊び」を組み込むこと。これらは一見、非効率に見えるが、脳科学的には創造性を最大化する合理的な設計なのである。
好奇心という最強の生産装置
茂木健一郎氏が一貫して強調してきた概念が「好奇心」である。好奇心は脳内のドーパミン系を活性化させ、人間が最も高い集中力と創造性を発揮する状態をつくる。
経営に置き換えれば、最も生産性が高い組織とは、社員が「やらされている」のではなく、「やりたくて仕方がない」状態にある組織だ。自発的なプロジェクト、自由研究的なテーマ設定、職務記述書を超えた越境活動、こうした個人駆動の動きを止めない企業が、結果的に強くなる。会社が管理すべきなのは、社員の時間や行動ではない。好奇心を阻害する制度や評価軸を取り除き、好奇心が加速する報酬体系や仕組みを整えることこそ、経営の仕事となる。
AIとの共進化をどう設計するか
茂木氏はAIを「脅威」ではなく、「補助脳(Auxiliary Brain)」と捉える。経営の課題は、AIと人間を対立させることではなく、両者の役割分担を明確にし、共進化できる構造をつくることにある。AIには計算、管理、最適化を任せる。一方で人間は、意味づけ、物語化、価値の再定義に集中する。そのためには、全社員がAIを使いこなす基礎リテラシーを持ち、AIの判断と人間の判断が自然につながるインターフェースを設計する必要がある。AIを導入すること自体が目的なのではない。AIによって人間が「人間らしい仕事」に専念できる状態をつくることが、経営の本質となる。
「心理的安全性」から「心理的ワクワク」へ
近年、経営論では心理的安全性が重視されてきた。しかし茂木氏の文脈では、それだけでは不十分である。重要なのは、人がワクワクしている状態だ。ワクワクしている脳は、最も柔軟で、最も創造的で、最も学習能力が高い。経営者がつくるべきなのは、挑戦したくなるストーリー、未来を具体的に思い描けるビジョン、社員が自分ごととして関われる使命感である。
結論
AIは正解を出す。
人間は意味をつくる。
経営は「意味が生まれる場」を設計する仕事へ変わる。
AIが得意な領域を完全に委ね、人間が得意な領域を最大化する。そのために、好奇心と余白に満ちた「脳の場」をどう設計するか。それこそが、茂木健一郎的世界観から導かれる、AI時代の経営の核心である。