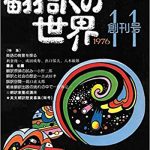東アジア・ニュースレター
海外メディアからみた東アジアと日本
第177 回

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教
中国関係では香港市場の本土化、中国のマンハッタン化が進んでいる。新規上場企業の大半は中国企業で、資金も上海・深圳経由の「ストックコネクト」を通じて流入、香港は中国投資家、企業の世界進出のゲートウェイとなっている。すべて本土政府のブループリントに則った共産党一党体制の枠内の動きとみられている。
台湾への侵攻に備えて中国がインフラ整備に乗り出している。事例として、東シナ海における水陸両用基地の建設、浙江省楽清湾の海軍施設での大規模な新埠頭の整備、福建省ヘリコプター基地の新設・拡張などが挙げられている。いずれも習主席による台湾侵攻の本気度を示す案件として注視していく必要がある。
韓国の現代自動車米国工場で多数の韓国人が拘束された。不法入国や就労禁止ビザでの入国、ビザの有効期限超過滞在などが理由とされる。メディアは、トランプ政権がアジア製造業の対米投資を促進する一方で、必要な人材の就労ビザを十分に発給していないためだと批判する。日本企業にとっても他人事ではない案件である。
北朝鮮の金総書記は、中国の習主席が主催した抗日戦勝利80周年式典と軍事パレードに参加。パレードでは習主席の左側に立ち、右側に立ったプーチン大統領と同格の処遇を受けた。また中露による北朝鮮の核保有国としての実質的認知など大きな外交成果を挙げた。トランプ米大統領による金総書記との会談の実現も難度を増してきたとみられる。
東南アジア関係では、タイで失脚したペートンタン・シナワトラ前首相の後任に、元保健相アヌティン・チャーンウィラクル氏が選出された。大麻合法化を実現した人物で、「大麻王」と称されていている。新首相の課題は、経済ではコロナ感染症の打撃からの脱却、19%の米国報復関税の克服、政治では4カ月以内の議会解散、総選挙の公約など重大である。
インドに対するトランプ高関税が中印を接近させ、中国を後押ししているとメディアが論じる。モディ首相は上海協力機構(SCO)サミット参加のために中国を訪れ、習近平主席との緊密な関係を強調、中印は「ライバルではなくパートナー」だと言い切った。サミットを主宰した習主席は米国の影響力衰退を演出している。
主要紙社説・論説欄では、トランプ関税と米国経済の現状に関するメディアの報道と論調を観察した。トランプ関税は米国と世界経済を危険に満ちた暗黒の炭鉱に投げ込んだと論じる。
§ § § § § § § § § §
北東アジア
中 国
☆「中国のマンハッタン」を目指す香港金融セクター
香港の金融市場は数年にわたる停滞を経て、中国政府の後押しにより世界的な地位を取り戻しつつあると、9月9日付フィナンシャル・タイムズが伝える。記事は冒頭で、香港の街が長引く取引の低迷から脱し、金融関係者が出入りする高級レストランへの需要も回復し始めていると述べ、香港の近況について概略以下のように報じる。
中国本土と香港政府が民主化運動を鎮圧し、不人気な法改正を押し通し、厳しい新型コロナウイルス対策によって多くの熟練移民労働者を追い出したことで、この旧英国領は世界的な金融ハブとしての役割を終えたと多くの人が見なしていた。しかし、香港は今、世界中から知識労働者を惹きつけ、税収の大部分を担う香港の金融業界が回復した。新規株式公開(IPO)資金調達額の世界ランキングでニューヨーク、ロンドン、ムンバイといった競合都市を上回り、ハンセン指数は世界で最もパフォーマンスの良い指数の一つとなっている。とはいえ、過去の好況サイクルとは多くの点で異なる。新規上場企業の大半は中国企業(多くは既に上場済み)だ。香港に流入する資本も、上海・深圳経由で本土投資家と結ぶ「ストックコネクト」を通じ、ますます中国資本が主流となっている。世界第2位の経済大国が香港に刻印を押し続けるなか、香港資本市場の「本土化」が進行中だ。
「本土政府は自らの目的に合わせて香港を再構築したと同時に、繁栄する金融センターとしての香港のイメージを維持するためでもある」と、モルガン・スタンレー・アジアのスティーブン・ローチ元会長は語る。「4~5年前まで私たちが想像していた香港とは、全く異なる都市であり金融センターだ」。しかし、漁村から交易拠点へ、繊維産業の中心地から製造業の拠点へと英国依存の植民地から中国の特別行政区へと変遷する中で、幾度となく自らを再発明してきた都市にとってこれは最新の転換点に過ぎない。また、このことは1950年代から1960年代にかけて、中国本土からの移民と米国主導の対中華人民共和国禁輸措置に後押しされた香港の急速な工業化の再現である。現在、香港の役割は外国資本や企業が中国に進出するための窓口というよりも、中国の投資家や企業が世界に進出するためのゲートウェイとしての側面が強くなっている。この役割は香港の「実体経済」の将来、そしてかつては同様の役割を担っていたもう一つの国際的な中国都市、上海の将来にも疑問符を残すことになる。「かつて私たちのスローガンは『アジアの世界都市』だった」とフセイン氏は言う。「そして、新しいアイデンティティは『中国の世界都市』だと思う」。
香港再生に向けた中国政府の実質的な青写真は、2024年4月に国家金融監督管理機関である中国証券監督管理委員会(CSRC)によって発表された。この文書は、習近平国家主席が掲げる「香港の際金融センターとしての地位を固め強化する」という方針に沿い、香港を活性化させる5つの施策を概説した。主な施策には、中国本土投資家が香港上場資産に投資できる「ストックコネクト」制度の拡大や、中国企業の香港上場促進などが含まれる。金融サービス業界を代表する香港議員ロバート・リー氏は「昨年から始まった真の起爆剤は、特に中国主要企業の香港IPOを促す5つの措置をCSRCが発表したことだ」と指摘する。
こうした政府方針に中国企業は耳を傾けた。慎重さが求められる世界的なIPO環境のなか、香港は今年上半期、上場による資金調達額で世界ランキングのトップに躍り出た。電気自動車用バッテリーメーカーのCATLは50億ドル以上を調達し、2023年以降で世界最大規模の上場を果たした。この取引は世界の注目を集め、再び資金を香港に呼び戻した。CATLをはじめ、江蘇恒瑞医薬や昨年上場した白物家電メーカーの美的集団など、大型案件の大半は上海や深圳に既に上場している企業が香港で二次上場するケースだった。その他にも、3月に55億ドルを調達した小米(シャオミ)のような大型株式売却を実施した企業もある。香港取引所のボニー・チャン最高経営責任者(CEO)は「中国本土企業はグローバル資本との接続と国際的な規模拡大のために香港取引所での上場を選択している」と述べ、アジアの他の地域からの企業にも一定の関心があると付け加えた。
香港の欧米系銀行の中には、深圳や上海で既に上場している中国企業の二次上場は、新規上場(IPO)ほどの業務規模や手数料、威信には及ばず、むしろ追加株式発行に近いと冷たい目で見る者もいる。それでも、香港のおける10億ドル規模の上場案件の復活は、欧米系銀行に十分な仕事をもたらしている。香港株式発行市場における上位3行の欧米系銀行のシェアは、前年の小規模な市場における26%から40%以上に上昇した。今年、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、UBSは、香港株式販売において中国のCICC (中国国際金融)とCITIC (中信)を表彰台から追い落とす可能性を示している。中国系投資銀行に比べて手数料が比較的高いにもかかわらず、こうした状況が生じている理由の一つは、国際系銀行が欧米や中東の投資家・ファンドとのネットワークを有し、大規模案件のマーケティングが可能だからだ。
例えばCATLの香港株式購入者には、米投資家ハワード・マークス率いるオークツリー・キャピタル・マネジメント、イタリアの実業家アグネリ家が支援する投資機関、クウェート政府系ファンドなどが名を連ねた。
こうした上場(株式売却)は、中国企業にとってのもう一つの変化、すなわち海外展開のための資金調達拠点としての香港の活用を示唆している。中国企業は膨大な資金を必要としていると、モルガン・スタンレー・アジア会長のロアチ氏は語る。中国企業、特に本土政府が重視する新技術分野の企業は、海外で急速に拡大しており、中国本土の資本規制の外で資金を調達・保有する必要がある。「中国本土の企業は、グローバル資本とつながり、国際的に規模を拡大するために香港取引所(HKEX)への上場を選択している」。中国本土は深刻なデフレサイクルの瀬戸際にあり、消費は低迷したままであるため、急成長企業は拡大ペースを維持するため海外の新市場を模索せざるを得ない。
アリババのような企業が海外資金を調達する伝統的な市場はニューヨークだったが、トランプ政権が国家安全保障やデータ問題を理由に中国企業を「上場廃止」する脅威をちらつかせることでその優位性は低下した。一方、資本規制下の上海は、金融当局が株式市場の自由化より安定を優先したため、代替国際金融ハブとして台頭できなかった。香港の資本規制不在と米ドルペッグ制、さらに香港上場中国株の割安感(いわゆるAHプレミアム)が縮小したことで、より多くの本土企業が香港市場に追随する動きが加速している。今年、中国資本が香港に流入する中、同市の取引高は記録を更新している。香港取引所(HKEX)のデータによると、取引高上位20日すべてが過去12カ月間に集中している。中国株への投資や米国株中心のポートフォリオ分散を目的に、香港市場に復帰する外国人投資家もいる。しかし香港市場での取引の大部分は本土からのものだ。中国本土投資家が香港上場企業に資金を投入したことで、香港株式市場への中国投資額は今年過去最高を記録。ハンセン指数は年初来約30%上昇し、世界でも最高水準のパフォーマンスを示す指数の一つとなった。香港市場は北京からの追加政策支援で後押しされている。
1月、中国人民銀行の潘功勝総裁は、香港での会議で中国が「香港に配分する国家外貨準備の割合を増やす」と述べた。これにより、中国の機関投資家は香港株式市場への資金投入が認められた。「資金が(香港に)流入することは、間違いなく政治的に正しい」と、ロータス・アセット・マネジメントの最高投資責任者で元中国証券会社トップのハオ・ホン氏は語る。中国投資家は、本土の証券取引所では入手できないアリババやテンセントなどのテクノロジー企業を買っている。今年の「ディープシーク・モーメント」は、中国テクノロジーへの世界的な関心の再燃を促し、その中でも国内での関心の高まりが最も顕著だった。本土政府当局は大手保険会社や投資信託に対し、国内株式市場への投資拡大を促している。平安保険などの企業はその後、香港上場の高配当利回りを国有銀行に数百億ドル投入した。香港議員のリー氏は「取引活動はまさに史上最高水準にある」と指摘。「取引所でこれほどの活況はかつて見たことがない」と語る。
中国資本と企業の香港流入に伴い、多くの場合、国内のトップ大学や大都市を離れて香港での職に就く多数のホワイトカラーの本土労働者も流入している。香港入国管理局のデータによると、2022年末に導入されたトップ人材誘致のための新たなビザ制度により、昨年は本土からの申請者39,010件が承認された。これは外国人向けの一般就労ビザ制度による承認件数35,058件を上回る。一等地の住宅賃料は、香港が国際的に知られる急騰水準まで回復している。香港は中国の金融改革と実験の多くにおける実験場となっており、特に中国政府が人民元の国際化を推進する計画の舞台として重要な役割を担っている。政府は2024年度予算案で、オフショア人民元の約75%が香港で取引されていると表明した。人民元の貿易決済・貿易金融分野での利用拡大に注力してきた。この分野の進展は緩やかだが、地政学的変化が中国通貨の普及を加速させる可能性があると、ゴールドマン・サックスのアナリストは最近のレポートで指摘した。「中国には資本規制があるため、人民元の国際化は典型的な通貨国際化とはやや異なるものになると見ている」と、ゴールドマン・サックスの中国チーフエコノミスト、許山氏は語る。「現実的な解決策はオフショア人民元市場の拡大だ。これは確実に香港に利益をもたらす」
香港はまた、オフショア人民元建て債券発行のハブとして中心的な役割を再確立している。2022年以降、中国企業と外国企業の双方が人民元の低資金調達コストを活用するなか、年間発行額は2014年に記録した過去最高を大幅に上回った。一方、香港の金融インフラは中国政府のニーズに応えるべく拡大中だ。香港取引所と金融管理局は3月、欧州のユーロクリアやクリアストリームに類似した新たな証券保管機関の建設計画を発表した。これにより中国は欧米金融機関への依存度を低下させ、ロシア式資産没収シナリオを回避できる見込みだ。デジタル資産分野では、香港ドル建てステーブルコインの認可を進めており、これは中国の厳しい資本規制下で将来的な人民元ステーブルコインの運用方法を試す実験と見られている。スタンダードチャータード銀行やJD.comなどが現地通貨準備を裏付けとするコインの運営を申請しているこのステーブルコイン試験運用(「サンドボックス」と呼ばれる)は、中国金融当局や規制当局の目には、香港全体に容易に適用可能なものと映るだろう。
とはいえ、香港の軌跡が右上の頂点へ一直線に進むとは考えにくい。欧米と中国の地政学的緊張が香港に波及する可能性を考慮し、欧米金融機関は過剰投資に慎重な姿勢を崩していない。アップルデイリー創刊者・黎智英氏の国家安全法違反裁判や、海外の香港デモ参加者への懸賞金制度の継続は、政治がビジネスの思考から決して遠ざからないことを改めて想起させる。「[香港は]今や全く別の世界だ。最終的に香港は中国のマンハッタンとなるだろう」
以上のように、香港の金融資本市場の「本土化」が進行している。新規上場企業の大半は中国企業で多くは既に上場済みである。資本も上海・深圳経由で本土投資家と結ぶ「ストックコネクト」を通じて流入し、中国資本が主流となっている。しかも今年上半期、上場による資金調達額で世界ランキングのトップに躍り出た。香港の役割は今や、中国の投資家、企業の海外展開のための資金調達拠点として世界進出のゲートウェイとしなってきている。これまでニューヨークがそうした役割を果たしてきたが、トランプ政権が国家安全保障やデータ問題を理由に中国企業を「上場廃止」する脅威をちらつかせたことで優位性は低下した。
中国人民銀行も香港に配分する国家外貨準備の割合を増やす計画で、中国の機関投資家による香港株式市場への資金投入が認められた。2022年末に導入されたトップ人材誘致のための新たなビザ制度により、多数のホワイトカラーの本土労働者も流入し、その数は外国人向けの一般就労ビザ制度による件数を上回っている。香港はまた人民元の国際化推進計画の舞台として重要な役割を担っている。本土政府は2024年度予算案で、オフショア人民元の約75%が香港で取引されていると表明した。デジタル資産分野では、香港ドル建てステーブルコインの認可を進めている。では香港はビジネス思考中心で一直線に発展していくのだろうか。この疑問に対して記事は、政治は決してビジネス思考から遠ざからないという見方を示す。香港は「中国のマンハッタン」化を進めているが、それはあくまで本土政府のブループリントに則った動きであり、共産党一党体制という万里の長城を超えられるものではないのだ。
台 湾
☆ 台湾侵攻に向けインフラ態勢を強化する中国
中国が東部沿岸地域で大規模なインフラ整備を進めていると、9月10日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルが報じる。記事は、海と空の施設の拡張が進んでおり、今後起こり得る台湾有事に向けた準備態勢の強化を示していると概略以下のように伝える。
本紙が分析した衛星写真やその他のオープンソース資料によると、こうした施設は水陸両用戦艦のための新たな大規模基地から空港にまで及んでおり、中国が台湾に侵攻した場合に中国の優位性を高めるとみられる。例えば、空港は台湾の前線の島々から5キロ程度の距離に位置し、数十億ドル規模のものである。ミッチェル航空宇宙研究所の上級常勤研究員で、これらのプロジェクトを詳しく追跡している米海軍情報部の元将校、マイケル・ダム氏は「全ては中国の唯一の軍事計画シナリオ、つまり台湾(侵攻)シナリオを支援するものだ」と語る。
これらの投資は、習近平国家主席の下で中国が台湾を奪取する能力と装備を整えるという包括的な取り組みを後押ししている。海峡を越えて台湾を占領するための侵攻は極めて複雑な軍事作戦となる。ただ習主席がそのような攻撃を実行する意図を持っているかどうかは、依然として未知数だ。米軍高官らは中国政府の意図についてここ数カ月で警告を強めており、同国は危険な道を進んでいると指摘している。中国は弾頭から戦闘機まで装備を近代化し、軍事演習を拡大し続けており、その一方でコンクリートの建設工事も進めているのだ。
5年前、中国は上海の主要空港の1つからほど近い、長江が東シナ海に注ぐ一帯の土地の整地を開始した。今日、この土地は主要な水陸両用基地となっている。長い桟橋、ヘリコプター用滑走路、兵舎、そしてバスケットボールコートやピックルボールコートが並ぶ大規模なスポーツ施設が整備されている。5月には12隻の水陸両用艦がここに停泊していた。その中には多数の揚陸艇があり、これには兵士、装甲車両、ヘリコプターを輸送可能な大型甲板の075型揚陸艦も含まれる。この艦艇群は合わせて約5,000名の兵員を輸送可能だ。燃料タンクはコンクリートで強化され泥で覆われている。「爆撃を想定している」と、現在隠蔽された燃料タンクを特定したダム氏は述べた。この防護は貫通弾頭には耐えられないが、巡航ミサイルは「跳ね返せる」と説明する。
ダム氏の調査によれば、基地には鉄道側線が設置される設計となっており、近く建設中の高速鉄道線と接続される見込みだ。列車は兵士や戦車を含む兵器を迅速に輸送し、水陸両用艦への積み込みが可能となる。この施設が台湾海峡に面していない点は利点となり得るとダム氏は指摘する。紛争時には同水域が市民も対象となり得る「無差別銃撃地帯」となる可能性が高いからだ。中国は侵攻艦隊を集中させる代わりに沿岸各地から分散して台湾へ向かわせる可能性がある。この手法では、部隊を適切な場所に適切なタイミングで展開させるため、より綿密な計画が必要となる。しかし、中国の敵対国が攻撃目標や時期、場所を決定する際その作業が複雑になるだろう。
シンガポールのS・ラジャラトナム国際研究大学院上級研究員のコリン・コー氏は、同施設の規模から戦時利用拡大を想定した建設と分析する。台湾北部の首都・台北を目指す侵攻艦隊の一部にとって、同施設は跳躍点として機能し得るとコー氏は指摘する。
台湾に近い浙江省楽清湾の海軍施設には全長1マイル超の新埠頭が整備され、多数の艦艇が展開可能だ。最近では戦車輸送艦、上陸用舟艇、タンカー、沿岸警備艇など約20隻が確認された。いずれも台湾有事において重要な役割を担う艦艇である。台湾の真向かい、中国福建省には新設・拡張中のヘリコプター基地が存在する。ここから出撃する陸軍ヘリコプターは、例えば台湾への兵員輸送や上陸部隊への火力支援を行う場合、台湾本島の南西海岸へ到達するのに極めて有利な位置にある。また同基地は、台湾海峡に浮かぶ重要な台湾諸島である澎湖諸島への攻撃支援も可能だ。紛争初期に澎湖諸島を制圧すれば、中国は決定的な優位性を獲得し、数十マイル離れた台湾本島への攻撃を持続させるための拠点として活用できる。
衛星画像で同施設を分析する情報コンサルティング会社「インテル・ラボ」のダミアン・サイモン研究員によれば、中国ドローンがこの飛行場を利用しているという。同基地はさらに拡張中で、最近の画像では少なくとも隣接する2区域で土地が整備されており、追加のヘリポート建設の可能性があると彼は述べる。
以上のように、中国は台湾有事に備えて軍事力の強化に励むだけでなく、侵攻作戦を支えるインフラ整備に乗り出している。長江が東シナ海に注ぐ一帯の整備と水陸両用基地の建設、同基地に鉄道側線を引き込み高速鉄道線と接続させ兵員や軍需品の輸送力を増強する計画、侵攻艦隊を集中させる代わりに沿岸各地から分散して台湾へ向かわせる可能性の検討、浙江省楽清湾の海軍施設における大規模新埠頭の整備、福建省におけるヘリコプター基地の新設・拡張などの案件が紹介されている。いずれも習主席による台湾侵攻の本気度を示す案件として注視していく必要がある。
韓 国
☆ 米移民政策の矛盾が引き起こした拘束事件
米移民当局はジョージア州にある現代自動車の工場で移民の強制捜査を実施し、約300人の韓国人を拘束した。これにつき9月9日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、トランプ米政権は移民法執行の厳格化を望むと同時に、アジア製造業大手に米国工場への投資を促したいとも考えており、専門家によると、これらの目標は現在、相矛盾していると報じる。それは、アジア企業が米国の工場を稼働させるのに必要な人材の就労ビザを十分に取得できないためであり、この矛盾が韓国人拘束事件で浮き彫りになったと以下のように伝える。
米国はジョージア州で移民の強制捜査を実施し、韓国・現代自動車の共同出資バッテリー工場の建設を支援していた約300人の韓国人を拘束した。拘束された韓国人は外交的な合意に基づいて間もなく帰国する見通しだ。専門家は、必要な人材がいないままアジア企業が米国工場を建設するには、長い時間と多くのコストがかかる可能性があると指摘する。トランプ大統領はソーシャルメディアでこうした懸念を示唆し、政府は外国人投資家が「世界クラスの製品を作るための優れた技術を持つ極めて賢い人材を合法的に連れてくる」ことを「迅速かつ合法的に可能にする」と述べた。
この問題の一因は米国の熟練技術者不足だ。これは製造業の雇用が長期にわたって減少し、生産が国外に移転したことに起因する。ワシントンのシンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)の7月の報告書によると、米国は半導体やバイオテクノロジーなどの先端産業を支えるのに必要な労働力が不足している。米半導体工業会(SIA)によると、半導体分野だけでも労働力の供給経路が拡大されない限り、2030年までに約6万7,000人分の技術職が充足できないままになるリスクがある。韓国、日本、台湾を中心とするアジア企業は、バイデン前政権とトランプ政権の双方の要請を受け、米国の製造業に多額の投資をしている。ジョージア州の現代自動車の「メタプラント」での韓国人労働者の拘束は、韓国政府と米国政府が貿易協議の最終調整をしている時に起きた。この協議で韓国は3,500億ドル(約51兆6,000億円)の対米投資に合意した。その見返りとして米国は、自動車を含む韓国からの輸出品の大半に対し、当初提案していた25%ではなく15%の関税を課すとした。
企業側は米国人労働者の採用と訓練に前向きだが、米国人だけでは工場を期限内に稼働させることはできないと述べている。そのため、大規模プロジェクトの現場に本国から何百人もの従業員が派遣されるのは一般的だ。米当局は拘束された人々について不法入国したか、就労が禁止されているビザ免除プログラムで入国したか、ビザの有効期限を超過して滞在していたと説明した。米国移民問題を専門とする韓国の弁護士は「米国側は現地で労働者を雇用できると言うかもしれないが、韓国企業は、予定通りに稼働させようとしている工場で人材を迅速に見つけて配置するのは難しいと主張している」と述べた。
ヤング・キム米下院議員(共和、カリフォルニア州)をはじめとするグループは7月、専門的な教育を受けた、あるいは専門知識を持つ韓国人向けに1万5,000件のビザを割り当てる法案を提出した。この法案は過去10年間にわたりさまざまな形で提案されてきたが前進していない。オーストラリアやシンガポールなどには、自由貿易協定(FTA)を通じて同様のビザ枠が設けられている。米国は専門分野のオーストラリア国民に年間1万件以上のE-3ビザを発給している。このビザは最長2年間の就労を認め、無期限に更新可能だ。元米通商代表部(USTR)高官で現在アジア・ソサエティ政策研究所(ASPI)に所属するウェンディ・カトラー氏によると、韓国は2012年に発効した米国とのFTA交渉時にオーストラリアやシンガポールに認められているような特別なビザ発給を強く求めた。韓国は最終的にこれを認められなかったが、ビザ免除プログラムには組み込まれた。カトラー氏は、投資が米国の優先事項となっていることから、「長期的な解決策が緊急に必要だ」と述べた。
以上のように、米移民当局が現代自動車工場で移民の強制捜査を実施し、数百人の韓国人を不法就労の疑いで拘束した。拘束された人々は、不法入国したか、就労が禁止されているビザ免除プログラムで入国したか、ビザの有効期限を超過して滞在していたという。これにつき記事は、米トランプ政権の政策の矛盾が露呈したと指摘する。トランプ政権はアジア製造業大手の対米投資促進を考える一方で、アジア企業の米国工場稼働に必要な人材の就労ビザを十分に発給していないと批判する。さらに背景に米国の熟練技術者不足があると指摘。半導体分野だけでも2030年までに約6万7,000人分の技術職が不足するリスクがあると報じる。韓国の他に日本、台湾などのアジア企業は米政権の要請を受け、米製造業に多額の投資をし、それを増やそうとしている。日本にとっても他人事ではないはずだ。
北 朝 鮮
☆ 地政学的地位を高めた金総書記の訪中
北京を訪問した金正恩総書記は9月3日、中国軍事パレードに出席し、その後、習近平国家主席と会談した。5日付ニューヨーク・タイムズは、金総書記は大きな外交的成果を得て北京を去ったと概略以下のように報じる。
金総書記の中国軍事パレード出席は、彼の地政学的な影響力の高まりと、北朝鮮が事実上の核保有国として受け入れられつつあることを示すものだった。金総書記が専用列車で北京に到着する前までに習主席とは5回の首脳会談を重ねていた。両政府によれば、そのたびに朝鮮半島からの核兵器撤去について協議したという。しかし6回目となる4日に開催された最新の二国間会談は、重要な点で異なっていたようだ。両政府が金曜日に発表した首脳会談の結果には、朝鮮半島の非核化に関する言及が一切なかった。この明らかな欠落は、金氏にとって新たな外交的勝利を意味する。
金氏は長年、2006年以降6回の核実験を実施してきた北朝鮮を世界最新の核保有国として認めるよう主張してきた。「中国は北朝鮮を核保有国として正式に承認しないが、今回の会談で非核化を強く要求しなくなったことが示された」と、ソウルにある極東研究所の李炳哲(イ・ビョンチョル)分析官は指摘する。「核兵器を既成事実として認めさせるという金正恩氏の戦略にとって、これは大きな進展だ」。アナリストらは、金氏の北京訪問は、北朝鮮を事実上の核保有国として中国とロシアに認めさせるのに貢献した、彼の地政学的な価値の高まりを浮き彫りにしたと指摘した。
金氏はロシアのウクライナ侵攻を兵士と武器で支援している。ロシアのために戦死した北朝鮮兵士は最大2,000人に上る。水曜日、ロシアのウラジーミル・V・プーチン大統領は北京で金氏と会談し、改めて深く感謝の意を表明した。ロシアと北朝鮮の関係が深まる中、習近平氏は水曜日に北京で行われた軍事パレードに金氏を招待し、再び自らの影響圏に引き戻そうとした。木曜日の首脳会談は6年ぶりだった。パレードは、中国の増大する軍事力と米国の一極支配に反発する世界的主導権を誇示するために企画された。観覧席では金氏が習氏の左側に、プーチン氏が右側に立った。
米国への敵意を共有する3人の指導者が連帯して立つ姿は世界中に中継され、金氏が国内外で展開する「新冷戦」論を後押しする効果をもたらした。「違法な核・ミサイル計画で国連安保理の全会一致の制裁対象となっている北朝鮮を、安保理常任理事国であるロシアと中国に受け入れられる存在へと変貌させたことで、金氏は外交的勝利を主張できる」と、ソウル・梨花女子大学の国際関係学教授、レイフ=エリック・イーズリー氏は語る。
北朝鮮と中国の国営メディアによると、木曜日の首脳会談で金氏と習氏は「国際情勢がどう変化しようとも」関係を強化することを誓約した。北朝鮮の主要国営紙・労働新聞は、木曜日の6ページにわたる紙面の前半を金氏の北京訪問に割いた。中国の新華社通信によれば、金氏は「中国との経済・貿易協力」の拡大も模索した。ロシアとの関係を強化しているにもかかわらず、北朝鮮は依然として対外貿易のほぼ全てを中国に依存している。
長年にわたり、中国とロシアは米国の目標である北朝鮮の核兵器計画の後退を共有していた。2016年と2017年に国連安保理が北朝鮮に厳しい経済制裁を課した際、両国は米国と共に賛成票を投じた。しかし米中の戦略的競争が激化し、ロシアのウクライナ侵攻を受けて協力関係は崩壊した。近年、ロシアと中国は国連安保理で拒否権を行使し、米国が北朝鮮に新たな制裁を課そうとする試みを阻んできた。これにより北朝鮮は核搭載可能な弾道ミサイルの実験を罰せられることなく自由に行うことができた。2024年、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、モスクワが北朝鮮の「非核化」構想を「決着済み事項」と見なしていると述べた。北朝鮮とロシア・中国の結びつきが強まる中、トランプ大統領が金正恩氏を交渉の席につかせるのは、2018年に初めて会談した時よりも困難になろうとアナリストらは指摘する。「米朝首脳会談の実現ハードルは今や高くなった」と、ソウル所在の北朝鮮大学校元学長、梁武鎮(ヤン・ムジン)氏は語る。
以上のように、金総書記は中国の習主席が主催した抗日戦勝利80周年記念式典と軍事パレードに参加し、習主席とロシアのプーチン大統領と会談した。軍事パレードでは習主席の左側に立ち、右側に立ったプーチン大統領と同格という栄誉に浴した。しかし金総書記の栄誉はそれだけにとどまらなかった。幾つかの大きな外交的勝利をも収めたのである。第1は、中朝両政府が発表した首脳会談の結果に朝鮮半島の非核化に関する言及が一切なかったこと、すなわち、北朝鮮が実質的に核保有国として認知されたのである。第2に、北朝鮮はまた国連安保理の常任理事国であるロシアと中国に受け入れられる存在とたこと、特にロシアとの関係では、ウクライナ戦争支援のために戦死した北朝鮮兵士は最大2,000人に上ると報じられている。露朝は今や血で結ばれた同盟、血盟関係に発展している。第3に、金総書記は最大の貿易相手国である中国との経済・貿易協力の拡大を協議する機会を得たことである。8月29日付ブルームバーグは、韓国銀行(中央銀行)の推計によれば、北朝鮮経済は昨年、2016年以降で最も高い経済成長率を記録したという。それは金総書記がロシアとの関係を深め、中国との貿易も拡大し続けているためだと報じる。韓銀の発表によると、北朝鮮の2024年の国内総生産(GDP)は推計で前年比3.7%増加し、これは重工業や建設分野での成長が背景にあり、3年連続のマイナス成長からプラスに転じた23年以降、回復基調が続いているという。北朝鮮を取り巻く地政学的環境は激変しており、記事が伝えるように、トランプ米大統領は金正恩氏を交渉の席につかせたいと考えているようだが、北朝鮮とロシア・中国の結びつきが強まるなか、その実現は難度を増し、実現できたとしても成果は期待できない状況となってきたと言えよう。
東南アジアほか
タイ
新首相に元保健相アヌティン氏を選出☆
タイ国会は「大麻王」として知られる元実業家で元保健相のアヌティン・チャーンウィラクル氏を首相に選出した。9月5日付フィナンシャル・タイムズによれば、同氏は大手建設会社を所有する家系出身の58歳。過去10年間タイ政界で「キングメーカー」として君臨してきた。保守派で王室支持派であり、必要な247票を大きく上回る311票を獲得した。またアヌティン氏は、大麻の非犯罪化支持で最もよく知られているが、同氏が引き継ぐのは不安定な政治・経済情勢だ。過去17年間で5人の首相が司法機関によって罷免されている。同氏も1年余りで3人目の指導者である。貿易と観光に依存するタイ経済は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、回復の勢いを取り戻せずに苦戦しており、第2四半期のGDP成長率はわずか2.8%にとどまった。さらに最大の輸出先である米国から19%の報復関税を課されている。
金曜日の投票は、タイ憲法裁判所がペートンタン・シナワトラ首相の倫理違反を認定し先週解任したことに端を発する。前任者の不動産王スレッタ・タヴィシン氏も昨年、倫理違反で同裁判所により解任されている。ミシガン大学の博士課程学生で政治アナリストのケン・マシス・ロハテパノン氏は「アヌティンの首相就任でタイの政治不安定期が終わることはない」と指摘。さらに「タイでは少数与党政権は稀であり、政策決定プロセスがさらに停滞する可能性がある」と述べた。議会第3党である「タイの誇り(ブムジャイタイ)党」のアヌティン氏は、最大野党である人民党の支援を得て首相の座を確保した。しかし合意の一環として、4カ月以内に議会を解散し総選挙を実施することを約束している。バンコクのチュラロンコーン大学政治学者ティティナン・ポンスディラック氏は、「タイは『選挙が危機を招く』例が繰り返されるパターンに陥っている」と指摘。「混乱は続いている」と述べる。人民党(旧ムーブフォワード党)は2023年選挙で最多得票を獲得したが、王室侮辱法改正を訴えたことで政権参加を阻まれ、党首は10年間の政治活動禁止処分を受けた。同党は金曜日にアヌティン氏を支持したが、新政権には参加しない。新たな選挙に加え、同党は軍部支持政権が起草した2017年憲法の改正に関する国民投票も求めている。「この合意の履行は非常に困難だろう」とロハテパノン氏は指摘し、「これまでタイの誇り党は憲法改正に特に強い関心を示してこなかった」と語る。
アヌティンの昇進は、父タクシン・シナワットの庇護のもと20年間タイ政界を支配してきたペートンタン・シナワトラのポピュリスト政党・プアタイ党にとって打撃となった。プアタイ党は金曜日、77歳の党重鎮チャイカセム・ニティシリを首相候補として推した。同氏は152票を獲得した。棄権は27票だった。アヌティン氏はペートンタンの首相在任10カ月間、副首相兼内相を務めた。しかし同時に、2014年のクーデターでペートンタンの叔母であるインラック・シナワトラを退陣させた元軍事政権指導者プラユット・チャノチャ政権も支持していた。アヌティン氏は新型コロナ禍の時代に保健相を務め、2022年のタイにおけるマリファナ非犯罪化を強く支持したが、その後は規制強化の動きを支持している。ペートンタンは、致命的な国境衝突直前にカンボジアのフン・セン前首相と交わした電話の内容が暴露されたことを受け、7月に職務停止処分となった。フン・センが流出したこの通話で、パエトンターンは彼を「おじさん」と呼び、緊張をエスカレートさせたのはタイ軍だと批判し、タイの主権を損なう行為だと非難された。彼女は謝罪し、その行動は交渉戦術だと説明していた。父親のタクシン・シナワトラ氏は億万長者の通信業界大物で、2001年から2006年まで首相を務めたが、軍によるクーデターで失脚した。その後15年間、汚職容疑を避けるため自ら亡命生活を送り、先月にはタイ王室を誹謗したとして起訴された別の事件で無罪判決を受けたが、4日深夜、以前の亡命生活の大半を過ごしたドバイに向けてタイを出国した。
以上のように、失脚したペートンタン・シナワトラ前首相の後任に、元保健相アヌティン・チャーンウィラクル氏が選出された。同氏は、大麻合法化を実現した人物として、「大麻王」と称されていている。相当うさんくさい人物とみられるが、保守派の王室支持派で過去10年間タイ政界の「キングメーカー」として君臨してきたという。年齢も58歳と働き盛りである。しかし、タイ経済は新型コロナウイルス感染症の打撃から未だ立ち直れず、米国からも19%の報復関税を課されるという苦境にある。政局も与党のタイの誇り(ブムジャイタイ)党は議会第3党で、最大野党である人民党の支援を必要としており、その一環として、4カ月以内の議会解散、総選挙を約束している。こうした不安定な政治・経済情勢にあるタイを、どうのように立て直すか。課題は大きい。
インド
☆ インドを中国に接近させたトランプ関税
トランプ米大統領によるインドに対する高率関税が中国を後押ししていると9月1日付英ガーディアンが社説で論じる。社説は、米政府はインドが屈服することを望んでいたが、ナレンドラ・モディ首相は、そうした米政府を脇に置いて中国を訪れ、習近平と和解したと指摘する。
トランプ大統領の帝王的な傾向は、米国が貢ぎ物を受け取ることができると期待して関税や制裁措置を行使することに見て取れる。しかし彼の最新の動き、つまり、かつて米国が奨励していたロシア産石油の購入に関連してインドに50%の関税を課すという措置は、服従ではなく、見世物のような結果をもたらした。この高関税により、モディ首相は7年ぶりに中国を訪問し、習近平国家主席が天津で開催した上海協力機構(SCO)サミットに20以上の国の首脳と共に出席した。歴史の転換点となっているのは、ワシントンではなく天津のようだ。
SCOは簡単に無視できる存在である。このブロックは矛盾の塊だからだ。インドとパキスタンは依然として敵対関係にある。中国とインドは、昨年10月の国境紛争を経て関係は改善しているものの、依然としてヒマラヤの国境を挟んで睨み合っている。ロシアと中国は中央アジアでの影響力を争っている。NATOとは異なり、SCOには拘束力のある防衛上の義務はない。SCOは、威勢はいいが実力のない、いわゆる「紙の虎」なのた。しかし地政学において見せかけは重要だ。モディ首相、習近平国家主席、プーチン大統領が笑顔で冗談を交わす姿は、米国の影響力が衰退する様を映している。トランプ大統領のインドに対する関税攻撃は、天津会談を重要なものにした。米国にとって中国に対するアジアのカウンターウェイトとされるインドの首相が、インドと中国は「ライバルではなくパートナー」だと明言したのである。
インドの計算は明快だ。農業分野の開放は米国の要求に応じない、石油購入量は米政府に決定させない、パキスタンとの停戦はトランプ氏が仲介したものではなくイスラマバード側が譲歩したものだ――こうした一線は越えられない。後退は弱さに見えかねない。モディ首相の視点では、米国に対してインドとのパートナーシップは当然視できないことを示し、インドが他国に友を求める方がはるかに得策なのだ。中国にとって利益は即座に現れる。トランプ氏は習近平氏に重要な多極的集会の主催者として振る舞う舞台を提供した。中国最高指導機関のメンバーで、いわば習氏の首席補佐官でもある蔡奇氏がモディ氏と会うために派遣されたのは、中国指導部が示す紛れもない親密さの表れだ。中国はSCOを国際舞台における米国の不在を際立たせ、他国に舞台を奪わせる場と見なしている。
SCOの影響は南アジアをはるかに超えている。ロシアにとって天津での握手一つ一つが制裁によって孤立した存在ではないことを強調する。トルコにとっては参加することでNATO加盟国としての曖昧な立場を維持する。またイランのためにSCOは今夏の米・イスラエル攻撃を非難した。この舞台が中国とロシアを非西洋陣営の指導者として正常化するほど、米国は将来の危機(特にウクライナ問題)において国際的な合意を形成することが困難になる。天津会議はユーラシアだけのものではなかった。サミット前夜の台湾をめぐるフィリピンとの小競り合いは、参加国に中国の最も越えられない一線を思い知らしめた。SCOは包括性を標榜するが、実質的に主導権を握るのは中国である。トランプ氏はインドに屈服を求めたが、結果的に中国に長期戦略の舞台を提供した。米国の影響圏を超えた体制構築だ。他国に余地が生まれるかは疑問だ。SCOが中国の戦争を代行することはないが、中国が孤立しないことを保証する。これがトランプ氏の自己陶酔的妄想が西側に課す高価な代償となるだろう。
以上のようにトランプ高関税はインドを屈服させず、むしろインドを中国に接近させ、中印関係を密接にし、中国を後押しする結果となった。現にモディ首相は中国を訪れ、習近平主席との緊密な関係を強調している。習主席は天津で開催したSCOサミットでインド、ロシア、北朝鮮を含む首脳会議を主宰し、米国の影響力が衰退する様を演出。そこでモディは、インドと中国は「ライバルではなくパートナー」だと言い切ったのである。今の米国はもはやインドとのパートナーシップを期待できない存在となり、インドが他に友を求めるのは当然のことになった。中国は孤立を回避し、それが保証されるような地政学的環境が誕生したのである。社説は、これはトランプ氏の自己陶酔的妄想が西側に課す高価な代償だと断定する。
§ § § § § § § § § §
主要紙の社説・論説から
トランプ関税と米国経済の現状ー炭鉱に投げ込まれた米国と世界経済
トランプ米大統領は4月5日と9日、米国と貿易取引を持つ各国に対して相互関税と称される前代未聞の高率関税を発動した。メディアは概ね、高率関税は将来の米経済と世界経済に対して悪影響を与えるとの見方を示した。以下は、こうしたメディアの報道と論調を要約したものである。(筆者の論評は末尾の「結び」を参照)
トランプ関税が発動された頃の4月7日付のウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、「Canaries in the Trump Tariff Mine (【社説】トランプ関税に潜む「炭鉱のカナリア)」と題する社説で、市場は高関税による危険を米政府に発信していると次のように論じる。関税という炭坑のカナリア(炭坑の有毒ガスの発生を人間より先に察知し、警告する)たちは、今後に訪れる経済的苦境を警告している。第1のカナリアは、ジャンク債市場での投げ売りで新型コロナウイルスが流行した2020年以来の大きさだった。米ドル建て投資適格債の動向を示す債券指数ICE・BofAのインデックスで見ると、高リスク社債を購入する際に投資家が求めるプレミアム(米国債利回りと比べた上乗せ幅)は、トランプ大統領の関税攻勢を受け、先週末の遅い段階で1ポイント拡大し4.5ポイントに達した。少なくとも、投資家が損失を回避しようとしている兆候で最悪の場合、関税とその影響によってデフォルト(債務不履行)が起きかねないとの不安を示すシグナルなのだ。
第2のカナリアは米ドルからの逃避だ。不確実性が高まると安全資産、すなわち通常はドル建て資産への逃避が起きる。しかし今回、ドルは対ユーロ、円、英ポンドで下落している。一段のドル安は不吉な前兆になるだろう。第3のカナリアは、ウォール街でのリセッション(景気後退)リスクに対する見方の変化だ。独立系の投資銀行アドバイザリー会社、エバーコアの友人らは、関税が成長への「相当な足かせ」になるとみて、今年の国内総生産(GDP)伸び率見通しを1%に引き下げ、年内リセッション入りの確率を40%に引き上げた。
それから4カ月後の8月に入ると、メディアは米国経済の現状について以下ように報じる。まず8月20日付ロイター通信は「S&P affirms 'AA+' credit rating for US (S&P、米国の信用格付け「AA+」を容認)」と題する報道記事で、有力格付け機関のS&Pグローバル・レーティングが、関税収入が減税と歳出法案の財政的影響を相殺すると予想し、米国の「AA+」の信用格付けを維持すると発表したと、概略以下のように報じる。
S&Pグローバルは19日、米国の「AA+」の信用格付けを維持した。ただし7月の米国の財政赤字は、関税収入の増加にもかかわらず拡大し、S&Pは赤字がさらに拡大した場合、格付けの引き下げの可能性があると警告した。トランプ大統領は議会で可決された「予算調整措置法案」を7月に署名し、同法案は成立した。法案は新たな減税措置を盛り込んだほか、トランプ大統領の2017年の減税措置を恒久的なものとした。S&Pは声明で「実効関税率が上昇するなかで、関税収入は減税と増税、歳出増を併せ持つ最近の財政法案によって生じうる財政の悪化を、おおむね相殺すると予想される」と述べた。
米政府は7月、トランプ氏の関税措置により関税収入が210億ドル増加したと報告したが、同月の政府予算赤字は依然として約20%増加し、2,910億ドルに達していた。公的債務の利子も金利と債務水準の増加により引き続き増加し、財政年度最初の10ヶ月間で1,013兆ドルに達した。これは、前年同期比6% (570億ドル)の増加である。2011年に米国政府の格付けを初めて引き下げたS&Pは、連邦準備制度理事会(FRB)が「国内のインフレ抑制と金融市場の脆弱性対応の課題に対処する」と予想し、米国の格付け見通しは安定的だと述べた。同機関は、2025年から2028年までの期間における政府の財政赤字がGDPの6.0%平均になると予測し、2024年の7.5%から、2020年から2023年までの平均9.8%から減少するとした。
しかしS&Pは、既に高い財政赤字がさらに増加した場合、今後2~3年で格付けを引き下げる可能性があると指摘した。「政治情勢が米国の組織機関の強度や長期的な政策決定の有効性、あるいはFRBの独立性に悪影響を及ぼす場合、格付けは圧力を受ける可能性がある」と述べた。ただし、S&Pは、持続的な経済成長と米国の財政構造の調整により、同国の債務負担の最近の増加が軽減される場合、米国の格付けを引き上げる可能性があると述べた。火曜日、S&Pの信用格付け維持発表に対し市場は反応を示さなかった。これは、5月にムーディーズが米国の公的信用格付けを格下げしたことに続く措置で、ムーディーズは債務水準の増加を理由に、トリプルAの米国格付けを1段階引き下げた。米国の公的債務は先週、記録的な37兆ドルを超えた。米国の金融サービス会社D.A. Davidsonの共同最高投資責任者兼投資管理研究部長であるジェームズ・ラガン氏は、S&Pの格付け維持はこれまで生み出された関税収入が有用だったと認めるものだと述べた。「税収入は有用だが、経済への負担にもなるため、今後その影響がどうなるかは分からない」と付け加えた。
上記のように米経済はトランプ高関税にもかかわらず、引き続き好調を維持している。しかし8月7日付エコノミスト誌は「(新たな帝国主義的優遇政策)」と題する社説で、トランプ氏は米国が勝利していると思っているだろうが。そうではないと主張する。
米国の新たな貿易秩序、すなわち帝国主義的優遇制度がルールや安定性、低関税という旧秩序に取って代わってきている。しかも関税は高くなっただけでなく、大統領の気まぐれで設定される。カナダとインドはドナルド・トランプを苛立たせたため、35~50%の関税を課される可能性がある。この脅威を回避するため、EU、日本、韓国はいずれも急いで米国と合意を結んだ。奇妙なことにトランプ氏は貿易赤字を窃盗と見なしているために10~41%の「報復的」関税を他の数十の貿易相手国に課し、これが8月7日に発効した。トランプ氏が主導権を握っているから米国が勝っているという魅惑的な考えが定着しつつある。世界は全面的な貿易戦争に陥ってはいない。中国を含むごく一部の国だけが報復措置を取っただけで、大半の国は屈服し、関税引き上げを受け入れ、自国市場を開放し、米国への巨額投資を約束した。金融市場さえも従順に見える。4月に大統領が「解放記念日」関税を発表した際には市場は大きく下落したが、今回は関税導入を平然と受け止めた。その間も関税収入は着々と入ってくる。
しかし、この考え方は根本的に誤っている。トランプ氏が始めたことは、米国に勝利どころか負ける結果をもたらすだろう。まず、高関税が米国ではなく貿易相手国を罰するという考え方である。イェール大学予算研究所によると、アメリカの実効関税率は18%まで上昇し、1月の約8倍、大恐慌期以来の水準に近づいている。トランプ政権ではこれは勝利なのだ。なぜなら米国の貿易相手国が高い関税を負担している一方で、米国税関は月間300億ドル近くを徴収しているからだ。これは貿易に対する根本的な誤解である。トランプ氏が関税を引き上げると、低価格での選択肢を奪うことで自国民を傷つけている。長年の経験が示すように関税は売り手よりも買い手に大きな損害を与える。外国の供給業者がトランプ氏の第一期関税導入後よりも大幅に値下げしているにもかかわらず、ゴールドマン・サックスのアナリストは、これまでの関税負担の実に5分の4が米国消費者と企業に押し付けられていると試算している。フォードやGMに聞いてみればわかる。両自動車メーカーは、今年第2四半期だけでそれぞれ8億ドルと11億ドルの関税コストを負担したと見積もっている。
では、市場の反応が鈍いのはなぜか。S&P500種株価指数は解放記念日時点より約10%高い水準を維持し、ドルは下落したものの、ここ数週間は反発している。市場を支えているのは米国における驚異的な人工知能ブームなのだ。これが大手ハイテク企業の予想収益を押し上げている。投資家はまた、関税コスト削減のための企業によるサプライチェーン転換を期待しているかもしれない。貿易協定の詳細は依然不明瞭だ。不穏な力学が働いている可能性もある。市場は関税の痛みが明らかになるにつれ、大統領が弱気になるのを期待しているかもしれないが、反応の鈍さがむしろ彼を強硬姿勢に駆り立てているのかもしれない。
代償を払うのは米国だ。長期にわたる景気拡大はすでに圧迫されている。2025年前半の成長率は期待外れでインフレ率は失望的に高かった。最近では雇用創出が鈍化し、経営者調査によればサービス業の活動は停滞寸前かもしれない。しかし関税の完全な影響は長期的に現れるだろう。トランプ氏は、原産国に関わらずほとんどの製品に同一関税率を適用する予測可能な多国間システムを捨て、商品の原産国によって関税率が変動し、絶え間ない交渉の対象となる二国間システムへと移行している。大統領はへつらわれると関税免除を検討し、不快に感じさせられると関税で脅すだろう。かつて米消費者は国内外の生産者が販売競争を繰り広げる中で選択肢に恵まれていたが、今後は成功する企業は最も革新的であるだけでなく、制度を巧みに操る能力でも評価される。ロビー活動に莫大な資金が投じられ、企業は不必要な不確実性に直面する。消費者は革新と選択肢を失う。しかし貿易が自由に行き交った今の実態と異なった世界は観察できないため、有権者は自らの損失に気づかないかもしれない。これがトランプ流システムが根強い理由の一つだ。将来の大統領が関税削減を望んでも、関税の盾に慣れきって国際競争力を失った米国企業からの猛烈なロビー活動に直面するだろう。多くの選択肢を享受できた可能性を知らなければ、消費者から変化を求める声は上がらないだろう。立法者もまた、明日の広範な繁栄を得るために今日の税収を犠牲にすることになれば、貿易障壁の引き下げに消極的になるかもしれない。このことはトランプ氏が引退してゴルフに熱中している後も長く続く可能性がある。
8月中旬に入ると、主要米企業が第2四半期の決算を発表し始める。その内容はおおむね好調だが、これに8月14日付フィナンシャル・タイムズが「Lessons from an upbeat US earnings season (好調な米国決算シーズンから得られる教訓)」と題する社説で、第2四半期決算は関税を乗り切る米国の能力を示す信頼できる指標ではないと概略以下のように警告を発する。
今期の決算シーズンのハイライトから判断すると米国企業は好調だ。S&P500種企業のほとんどが第2四半期決算を発表済みだ。ファクトセットによれば、81%がアナリストの売上高予想を上回り、同指数は3四半期連続で前年比2桁の利益成長を達成する見込みだ。この回復力は印象的だ。トランプ米大統領の「報復的」関税発動が8月7日までほぼ延期されたとはいえ、継続的な経済不安と自動車・鉄鋼・アルミニウムへの課税が第2四半期を通じて国内外の企業活動を抑制していた。バンク・オブ・アメリカの調査によると、欧州株価指数Stoxx Europe 600構成企業の第2四半期決算は、年間ベースでほぼゼロ成長に留まる見通しだ。
では、米国企業の堅調な業績をどう説明すべきか。第一に、関税の直接的影響を受ける産業はS&P500企業の利益の17%未満を占めるに過ぎないとドイツ銀行は推計する。それでも第2四半期の報告では、多くの影響を受けた企業がコスト削減や在庫積み増しから価格引き上げや代替サプライヤーの確保に至るまで、幾つかの緩和策を講じることで利益率を守り抜いたことが示されている。こうした幅広い対応策により、価格上昇や解雇が国内サプライチェーン全体に波及する影響が抑制され、ひいては広範な経済への伝染効果も抑えられた。第二に、シリコンバレーとウォール街の有力企業が第2四半期の全体的な収益性と需要を支えた。S&P500の時価総額の約3分の1を占めるITセクターは、年間20%超の利益成長を達成している。これは現時点ではトランプ関税の影響をほぼ免れている人工知能(AI)関連事業が牽引している。アルファベット、メタ、マイクロソフトはいずれも第2四半期に大幅な売上高・純利益成長を報告した。市場変動で取引部門が恩恵を受けた大手銀行も収益力維持の要因となった。
ただし米国経済の一部では緊張が顕在化している。素材・工業・消費財セクターの年間利益成長率は鈍化傾向にある。ゼネラル・モーターズは前四半期に関税コスト11億ドルを計上した。ナイキは輸入関税の影響で今年度のコストが約10億ドル増加すると見込む。S&P500種指数に組み込まれていない中小企業も打撃を受けている。ホワイトハウスの主張に反し、輸入業者がコスト上昇に直面していることは明らかだ。7月の米国関税収入は280億ドルと過去最高を記録した。今後数ヶ月で苦境はさらに深刻化する見通しだ。トランプ大統領の「報復的」輸入関税の大半は先週になってようやく発動された。基準となる関税率を設定することで、継続中の2国間交渉の不確実性が少なくとも低下することを期待する企業もあるかもしれない。しかし、多くの合意事項は依然として不明確なままで、大統領は合意の再交渉を行う前例があり、またホワイトハウスは特定の分野を対象とした課税を検討している。中国との交渉も月曜日、さらに90日間延長された。
関税の影響は直接的な影響を受ける産業を超えて広がる可能性がある。予防的備蓄が枯渇するにつれ、企業は多くのコストをサプライヤーや顧客に転嫁する必要に迫られる。ゴールドマン・サックスのモデルによると、輸入関税の負担は今後数か月でますます消費者に転嫁される見込みだ。これは銀行セクターを含む多くの企業に打撃を与える可能性がある。そうなればビッグテックは米国経済の重荷をさらに背負うことになる。第2四半期決算は米国企業の回復力を確かに示しているが、取締役会、投資家、ホワイトハウスは浮かれるべきではない。今後数四半期における関税下での米国経済見通しを理解する上で、今回の決算シーズンは発信音よりも雑音が多いといえよう。
また8月9日付ワシントン・ポストも「A growing disconnect between Wall Street and Main Street over tariffs (関税を巡るウォール街と一般社会との乖離拡大)」と題する社説で、トランプ大統領が握手で合意し、関税交渉を進めるなか、混乱の拡大は間違いない、と株式市場の動向から以下のように論じる。
ウォール街が関税ニュースの混沌とした鼓動に麻痺し、人工知能のゴールドラッシュに気を取られるなか、株価指数は過去最高値をうかがう動きを見せている。4月のパニック以来、株式市場は劇的に上昇している。延期が繰り返された「解放の日」の骨抜き版がようやく木曜日に到来し、60カ国以上の製品に新たな関税率が課されたにもかかわらずだ。しかし関税が想定より軽微だったからといって、成長を阻害しないわけではない。市場はトランプ大統領が導いた新たな世界貿易秩序のコストを完全には織り込んでいない。交渉継続中のカナダ・メキシコ・中国との一時休戦延長により、不確定要因は依然多い。
米政府高官が自国民への増税を自慢する様子は現実離れしているが、まさにそれが現実だ。月曜にはホワイトハウスの報道官が7月の関税収入290億ドルを称賛し、木曜日にはラトニック商務長官が月間500億ドルに達する見通しを表明した。こうしたコストはサプライチェーンを通じて企業と消費者に転嫁されるのは避けられない。イェール大学予算研究所によれば、米国人の輸入品に対する平均税率は現在18.6%に達し、1933年以来の最高水準である。長年、産業経済の先行指標となってきた重機メーカー、キャタピラー社が市場の歪んだ心理を如実に示してくれた。同社は表向きには、製造業を米国に呼び戻したいトランプ大統領の支援する企業像に合致する。しかし同社は月曜日、新たな関税により今年の純利益が13億~15億ドル減少し、第3四半期だけで最大5億ドルの損失が出ると警告した。それでもキャタピラー株は週間でわずか3%下落したに過ぎない。インフラ投資やAIデータセンターへの支出が関税の打撃を相殺するとの期待に支えられたためだ。
ウォール街と一般社会の間の乖離の一因は、経済のK字型構造にある。投資家層が頂点で繁栄する一方、底辺層は圧迫され続けている。関税は貧困層に不釣り合いな打撃を与える。月曜日に発表されたAP通信・NORC世論調査では、アメリカ人の53%が食料品代が生活における「主要なストレス源」だと回答し、成人の約3割が「買ったら後払い」サービスを利用していることが判明した。これもまた危険信号だ。トランプ大統領が先週、不都合な雇用統計を理由に労働統計局長を解任した決定は、経済の健全性に対する自信の表れとは言い難い。しかし市場は、新たな脆弱性の証拠が次々と明らかになる中でも概ね無反応だった。労働省が木曜日に発表したところでは、7月末時点で少なくとも1週間失業給付を受給している米国人の数は197万人に達し、2021年のパンデミック時以来の最高水準となった。今年上半期の経済成長率は年率1.2%で、2024年下半期の2.4%を下回った。
トランプ大統領が発表した貿易協定は握手以上の根拠に乏しい。細部よりも派手な見出しを狙ったように見える。正式な協定文は公表されていない。歴史的に貿易協定は弁護士チームが数ヶ月から数年かけて練り上げるものだ。それと比較すれば、今回の合意は杜撰極まりない。トランプ氏が「史上最大規模の合意」と称した発表後も、欧州連合(EU)、日本、韓国の交渉担当者は米国側と特例措置や免除条項をめぐり駆け引きを続けている。合意内容が確定していないため、予算編成を進める輸出入業者にとって不快なほど先行き不透明な状態が続いている。
トランプ大統領を合意に導いている「甘い誘い」の一つが、大統領が「署名ボーナス」と呼ぶ将来の米国投資約束だ。これらは既に発表済みの支出を含んだ、しばしば非現実的な巨額の投資額である。例えばトランプ氏はEUが6,000億ドルの新規米国投資を約束したと述べたが、EU側は企業が単に「関心を表明した」に過ぎないと説明した。トランプ政権はまた、欧州がトランプ大統領の任期終了まで毎年2,500億ドルの米国産エネルギー製品を購入すると約束したと発表した。現在の購入額700億ドルから大幅な増加となる。しかし欧州側はこれを保証したものではないと表明。専門家はこの目標は不可能だと指摘した。交渉当事者双方が合意内容についてこれほど異なる認識を持つ場合、合意は将来破綻するリスクを孕んでいる。元下院議長ポール・D・ライアン(共和党)は、トランプ氏の予測不可能な「気まぐれ」が続くと警告。さらに大統領が関税発動に1977年国際緊急経済権限法を発動した行為を最高裁が違憲とする可能性も指摘した。「市場は近い将来すべてが落ち着くと考えている」とライアン氏は水曜日、コロラド州アスペンで述べた。「しかし荒波が待ち受けている」。
アナリストによれば、米国経済活動に占める貿易の割合が4分の1であることが株式市場の回復力の一因だという。カナダやメキシコでは3分の2以上を占める。しかし最大の要因はAIブームだ。ハイテク株を除けば、S&P500種株価指数は横ばい状態が続いている。弱気材料は他にもある。証券報告書によると、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは前四半期に純額30億ドル相当の株式を売却した。同コングロマリットが株式の純売り手となったのはこれで11四半期連続となる。引退を控えた「オマハの賢人」は現在、後継者が資産を買い集めるための3,440億ドルの現金を蓄えている。バフェットは、その時が来れば資産がより手頃な価格になると考えているのだ。
結び:以上のようなメディアの論調や分析を次の3つの観点からまとめてみたい。第1は、トランプ関税の実態に関する分析と論議、第2はトランプ関税が米国経済に及ぼす影響、第3は市場、特に株式市場の動きとトランプ関税との関係である。
第1のトランプ関税の実態に関する論議でまず注目されるのは、トランプ関税が大統領の気まぐれで設定される米国の新貿易秩序だとの分析である。それは、ルールや安定性、低関税という、これまでの秩序に取って代わる帝国主義的優遇制度だと断定する。かなり過激な見方であるが、それが実態であろう。さらにメディアは、トランプ流の関税賦課方式について、これまでの多国間システムを捨て、商品の原産国によって関税率が変動し、絶え間ない交渉の対象となる2国間システムへ移行していると分析する。交渉を原則として取引(ディール)と見立てるトランプ外交の実態を端的に指摘していると言えよう。最も注目されるのは、その高関税を危険に満ちた炭鉱に譬え、炭鉱のカナリアという逸話を持ち出していることであろう。カナリアは有毒ガスの発生を人間より先に察知し、警告するとされる。トランプ関税という炭鉱に入ったカナリアたちが発する具体的な警告としてメディアは、第1に大規模な投げ売りによるジャンク債の急落、第2に米ドルからの逃避によるドル安、第3はウォール街筋による年内景気後退入りの観測の高まりを挙げる。そのうえで、こうした警告の結末は、ジャンク債の大量デフォルト(債務不履行)発生と不吉なドル安の進展であり、関税の足かせによる景気後退入りだと論じる。いずれも米経済、ひいては世界経済にとって悪夢となる結果である。
最後に留意すべきは、各国と米政府との合意内容は杜撰極まりないというメディアの批判であろう。合意発表後も、日本を含む交渉担当者は米国側と特例措置や免除条項をめぐり駆け引きを続けている。大統領が「署名ボーナス」と呼ぶ将来の米国投資約束も、発表済みの支出を含んだ非現実的な投資額としてやり玉に挙がっている。トランプ流の取引は将来破綻するリスクを孕んでいるのである。
第2はトランプ高関税が米国経済に及ぼす影響である。8月に今年第2四半期の米企業業績が発表されると決算内容は意外と好調であり、有力格付け機関、S&Pグローバル・レーティングも米国の「AA+」の信用格付けを維持すると発表する。これは関税収入がトランプ政権の減税政策と歳出法案による財政悪化を相殺すると予想してのことである。しかし、企業業績もS&Pの決定も時期尚早の判断と言えよう。貿易赤字を窃盗と見なすトランプ大統領が、数十の貿易相手国に課した高率の報復関税が発効したのは8月7日であり、影響はこれから出てくるからである。第2四半期決算は関税を乗り切る米国の能力を示す信頼できる指標とは言えないのである。さらにS&Pが、財政赤字が拡大した場合、格付けの引き下げの可能性があると警告しているのにも留意しておくべきだろう。実際、政府予算の赤字は依然として増大傾向にあり、公的債務も金利と債務水準の上昇により引き続き増加している。関税収入は経済への負担になり、今後の影響を見定める必要がある。また、この関連でFRBの対応も注視する必要があろう。
他方、トランプ関税に対して中国など一部の国が報復措置を取っただけで、大半の国はこれを受け入れ、自国市場を開放し、巨額の対米投資を約束していることから、メディアは米国は勝ち続けているのかと問題提起し、そうではないと断じる。米国の勝利とする考え方は根本的に誤っており、勝利どころか負ける結果をもたらすと主張する。その理由として、関税は売り手よりも買い手に大きな損害を与え、これまでの関税負担の5分の4が米国消費者と企業に押し付けられているとの試算を紹介。トランプ氏が関税を引き上げると低価格での選択肢を奪うことで自国民を傷つけていると指摘する。この指摘は、米自動車大手のフォードやGMが今年第2四半期だけで巨額の関税コストを負担したとの報道の裏付けもあり、説得力に富むと言えよう。
第3の市場、特に株式市場の動きとトランプ関税との関係についてメディアは、S&P500種株価指数が4月以降も高水準を維持し、米ドルもここ数週間は反発していると述べ、市場の反応が鈍いのはなぜかと問題提起する。そのうえで、株式市場を支えているのは、米国における驚異的な人工知能ブームであり、これがITセクターの収益を押し上げていると指摘する。ITセクターは現時点ではトランプ関税の影響をほぼ免れており、しかもその時価総額はS&P500の約3分の1を占め、年間20%超の利益成長を達成している。また関税コスト削減のための企業によるサプライチェーン転換期待という要因があると分析する。しかしメディアは、株価はいずれ崩壊すると警告する。目下、後継者のために現金をため込んでいる「オマハの賢人」の動きは、それを象徴しているのである。
より大きな問題は、市場の動きが一般社会と乖離しているとの警告であろう。メディアは、長期にわたっていた景気拡大の低迷、高インフレの進行、雇用創出の鈍化、サービス業の活動停滞予想などを挙げ、株式市場は活況を呈しているが、市民生活は脅かされていると警鐘を鳴らす。まさしく米国民が高関税の代償を支払い始めたと言えよう。素材・工業・消費財セクターの年間利益成長率は鈍化傾向にある。S&P500種指数に組み込まれていない中小企業も打撃を受け、投資家層が頂点で繁栄する一方、底辺層は圧迫され続けていると警告する。いずれも深刻に受け止めるべきだろう。関税は貧困層に不釣り合いな打撃を与えているのである。失業給付受給者数は197万人に達し、2021年のパンデミック時以来の最高水準となった。今年上半期の経済成長率は年率1.2%で、2024年下半期の2.4%を下回っている。しかも、関税の盾に慣れきって国際競争力を失った企業や選択肢の享受を知らない消費者からも高関税への抗議が起こらないまま、こうした現状が長く続く可能性がある。
以上のことから、要するにトランプ政権は3つの誤謬を冒していると言えよう。第1は、高関税による税収入の急増を賛美しているが、それは最終的に米企業と消費者が負担する結果になることについての認識がないこと。第2に、貿易秩序についての誤解、とりわけ貿易収支の赤字を黒字国による窃盗とみなし、報復行為に出ていること。第3に、株式市場の活況の原因に関する理解の欠如である。第1の結果、関税による被害を最も深刻に被る貧困層や中間層からの不満が爆発し、社会不安が拡大する危険がある。第2の結果、高率の相互関税を課されて各国の経済は低迷し、世界経済が不況に向かうリスクが高まる。第3は、米株式市場は、かつてのITバブルのような状況にあり、これが破裂すれば、高関税の負担を株価高騰で補填していた層、特に中間層が一挙にトランプ批判に転じる恐れがある。トランプ関税という炭鉱に投げ込まれた米国と世界経済には、まさに暗黒の前途が待っている。
§ § § § § § § § § §
(主要トピックス)
(主要トピックス)
2025年
8月15日 韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領、「光復節」の演説で 日韓関係を巡り 「過去を直視しつつ、未来へ進む知恵を発揮 すべき時だ」と主張。
18日 米韓両軍、朝鮮半島有事を想定した大規模合同軍事演習
「乙支フリーダムシールド(自由の盾)」を開始。
李在明(イ・ジェミョン)政権下では初めて。
19日 中国の王毅(ワン・イー)共産党政治局員兼外相、訪印、モディ 首相と会談。 国境問題の適切な管理と両国の協力拡大方針で一致。
22日 タイの裁判所、不敬罪に問われていたタクシン元首相に無罪判 決。 裁判による政治的な混乱は回避。
23日 韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領、訪米前に来日。
石破首相と会談。日韓国交正常化から60周年を迎え、安定的関係発展の方針で一致。
24日 韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領、トランプ米大統領と会談。 経済分野や対北朝鮮での協力を確認。
26日 韓国の保守系最大野党「国民の力」、新代表に張東赫(チャン ・ドンヒョク)氏を選出。
28日 インドのモディ首相、来日。石破首相と会談。
31日 上海協力機構、首脳会議、天津で開幕。 習近平国家主席の招待で31日からインドやロシア、北朝鮮の首脳が中国に集結。 イン ドネシアのプラボウォ大統領は国内の抗議デモのため不参加。
9月 3日 中国の習近平政権、日中戦争勝利80周年記念式典を挙行。軍事 パレードでハイテク技術を駆使した「新質戦闘力」を誇示。
4日 北朝鮮の金正恩総書記、北京で習近平席と会談。
中朝友好・協力関係の深化で合意。
5日 タイ国会、アヌティン前副首相兼内相を新首相に指名。
民主派の最大野党や一部与党の支持を得て賛成多数を確保。
中国の重慶市でスマート産業博覧会(スマート博)、開幕。
自動車産業が盛んな重慶市、天津市の両政府が共催。
7日 日本の石破首相、突如、退任を表明。日米関税合意が一つのタ イミングと説明。
9日 北朝鮮、建国77年記念行事、開催。金正恩総書記、演説で非核 化を求める動きをけん制。
10日 米中の国防相が初対話、首脳会談へ地ならし。
ヘグセス国防長官、「紛争望まず」と伝達。
12日 現代自動車グループ、米電池工場建設の大幅遅延を発表。
作業員の不法就労問題で米国のビザ(査証)規制の改善を要望。
ネパールでオリ首相が辞任、デモの若者らが支持するスシラ・ カルキ元最高裁判所長官(73)が暫定首相に就任。
ネパール初の「女性首相」。
13日 中国の習近平主席、トランプ米大統領を正式に北京に招待、
とメディアが報道。
15日 米韓の軍事演習、日米韓の共同訓練、開始。北朝鮮の金与正
(キム・ヨジョン)朝鮮労働党副部長、これに反発する談話を発表。
4日 北朝鮮の金正恩総書記、北京で習近平席と会談。中朝友好・協力関係の深化で合意。
5日 タイ国会、アヌティン前副首相兼内相を新首相に指名。民主派の最大野党や一部与党の支持を得て賛成多数を確保。
中国の重慶市でスマート産業博覧会(スマート博)、開幕。自動車産業が盛んな重慶市、天津市の両政府が共催。
7日 日本の石破首相、突如、退任を表明。日米関税合意が一つのタイミングと説明。
9日 北朝鮮、建国77年記念行事、開催。金正恩総書記、演説で非核化を求める動きをけん制。
10日 米中の国防相が初対話、首脳会談へ地ならし。ヘグセス国防長官、「紛争望まず」と伝達。
12日 現代自動車グループ、米電池工場建設の大幅遅延を発表。作業員の不法就労問題で米国のビザ(査証)規制の改善を要望。
主要資料は以下の通りで、原則、電子版を使用しています。(カッコ内は邦文名)THE WALL STREET JOURNAL(ウォール・ストリート・ジャーナル)、THE FINANCIAL TIMES(フィナンシャル・タイムズ)、THE NEWYORK TIMES(ニューヨーク・タイムズ)、THE LOS ANGELES TIMES (ロサンゼルス・タイムズ)、THE WASHINGTON POST(ワシントン・ポスト)、THE GUARDIAN(ガーディアン)、BLOOMBERG・BUSINESSWEEK(ブルームバーグ・ビジネスウイーク)、TIME (タイム)、THE ECONOMIST (エコノミスト)、 REUTER(ロイター通信)など。なお、韓国聯合ニュースや中国人民日報の日本語版なども参考資料として参照し、各国統計数値など一部資料は本邦紙も利用。
バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教授 前田高昭
PDF版






![第19回 カナダ絵本レポート[3]](https://babel.co.jp/gwg/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/singapol-150x150.png)