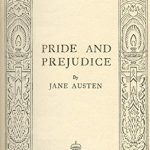東アジア・ニュースレター
海外メディアからみた東アジアと日本
第173 回

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教
中国は10年前にスタートさせた「中国製造2025」政策によって西側との技術格差の縮小に成功したとメディアが報じる。巨額の国家支援を通じて鉄道や電力設備、医療機器、再生エネルギー製品、造船、ロボット工学などで国際競争力を高め、今後も強化するのは間違いなく、米国を含む西側諸国のリスクとなっていると警告する。
台湾ドルが急騰している。これは米国との貿易協定に台湾ドル強化が盛り込まれるとの憶測から、台湾の生保がドル建て資産の為替リスクヘッジに動いたためとされる。台湾中央銀行は米当局による通貨高要求の噂を否定しているが、対米貿易戦争がアジア諸国の通貨情勢に影響を及ぼし始めている。
韓国で6月に実施される大統領選での与野党候補者が決まった。メディアは両候補の経歴や人となりを詳細に紹介。両者は分極化した韓国の正反対の立場を代表していると伝える。ともに分断された韓国の回復を誓っているが、その政治的な溝は埋まりそうにないとコメントする。
北朝鮮の労働者がロシアで国連の制裁措置を無視して大量に働いている。メディアは、そうした労働者を金総書記からの「贈り物」と表現する。戦争や出生率低下による労働力不足に悩むロシアにとって貴重な存在となっている。いまのところ極東地域に限られているが、モスクワなどの主要都市に拡大するのも時間の問題とみられる。
東南アジア関係では、中国に対する高率のトランプ関税を回避するためベトナムやタイやマレーシアなどを経由して米国に輸出する迂回取引が増加するなか、工場自体をベトナムに移す動きが加速している。雑貨品を生産する中小企業のみならず、中国のEコマースやソーシャルメディアまで巻き込む動きに拡大している。
先月、インドとパキスタンは過激派によるカシミールでの襲撃事件を契機に激しく対立したが、トランプ米政権の仲介で停戦に合意した。停戦は、たとえ微妙なものであったとしてもウクライナとガザでの戦争を終わらせるという選挙公約を今のところ実現できていないトランプ大統領にとっては勝利だとメディアは評する。
主要紙社説・論説欄では、トランプ関税をめぐる交渉で各国の先頭に立った日本の役割と責任に関するメディアの報道と論調を観察した。
§ § § § § § § § § §
北東アジア
中 国
☆ 西側との技術格差縮小に成功した「中国製造2025」政策
中国は、10年前に習主席の看板政策として国際競争力強化を目的とする大規模な産業政策「中国製造2025」をスタートさせた。5月7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、この政策は米国から保護主義的と批判されたが、西側との技術格差縮小で大きな成功を収めたことが新たな調査で判明したと伝える。調査は、米商工会議所の委託で米経済コンサルティング会社のロジウム・グループが実施し、5日に公表したものである。記事は、調査結果を受けて政府補助金の利用など競争力強化を目的とした中国の施策にどう対抗するかをめぐり、米国など各国で議論に拍車がかかりそうだと述べ、概略以下のように報じる。
中国政府が「中国製造2025」を発表したのは、習氏が2012年後半に実権を握った約2年後で、同政策は習氏の産業分野における野心の最重要事項になった。2018~19年の米中貿易戦争で米国政府は、中国は自国企業への政府補助金の支給や外国企業に対する技術移転の強要で競争をゆがめていると主張し、政策を転換させようとした。中国はトランプ氏をなだめるため、公に「中国製造2025」に言及することをやめた。だが習近平国家主席が打ち出したこの看板政策は続いていた。この間、2020年の米中貿易協定で最も重視されたのは、補助金を含む多くの米国企業の懸念事項への対応ではなく、米国製品の購入を増やすという約束だった。トランプ政権が中国との交渉を念頭に準備を進めているなかで、中国の国家主導の政策がもたらす新たな課題が調査によって明らかになった。調査によると、「中国製造2025」の下で行われた巨額の国家支援のおかげで、中国は鉄道や電力設備、医療機器、再生エネルギー製品などの輸入品への依存をなくすか減らすことができた。また中国企業は造船、ロボット工学などの分野で外国企業から市場シェアを奪い、国際競争力を高めた。
調査は、「中国製造2025」の実施当初から政府の支援がどのように強化されたかを詳細に記述している。優先分野の企業への税制優遇措置は2018年から2022年にかけて年平均で29%近く増加し、2022年に1兆3,000億元(約26兆5,700億円)に達した。これは企業の研究開発費全体の半分超に相当する。税控除などの優遇措置を受けている企業の割合は2015年から2023年の間に4倍以上になった。また調査は、入手可能な政府のデータを根拠に政府系ファンドを通じた投資が2015年から2020年の間に5倍以上になり、520億ドルに達したとしている。さらに中国当局は外国企業に生産や研究の拠点を国内に設立させる手段として、中国市場へのアクセスを利用するよう促している。こうした慣行は、スマートフォンや電気自動車(EV)などさまざまな製品のサプライチェーン(供給網)を中国が構築するために役立った。その結果、情報技術、高性能機械、医療機器、新素材など「中国製造2025」の対象になった全ての分野で輸入依存の「大幅な減少」が起きたという。例えば、医療機器市場に占める輸入品の割合は2015年には24%だったが、2023年には14%にまで低下した。また調査によると、民間航空機は中国企業が米国など西側のライバルにまだ後れを取っている数少ない分野の一つだ。中国航空機メーカーの中国商用飛機(COMAC)は今も、米国のボーイングや欧州のエアバスの民間航空機に対抗する航空機を製造するために外国製の部品に依存している。しかし調査によると、中国は国産の航空機エンジンの製造を進めており、こうした状況は今後数年で変わる可能性がある。
調査によって浮き彫りになったのは、米国を含む先進国が直面しているリスクだ。上述の米調査会社ロジウム・グループのアソシエイトディレクターで、調査の筆頭著者のカミーユ・ブルノア氏は「今の中国は2015年当時の中国とは大きく異なる。それは国家による異例の財政支援に基づく産業政策と大いに関係がある。中国が今後も格差を縮小し、競争力を強化することは間違いない」と指摘する。トランプ大統領は、中国との貿易協定が公正でなければならないと主張している。しかし政権に近い関係者によれば、トランプ氏が補助金の利用など中国企業を有利にする方策を巡って対決姿勢を示すかは明確ではない。ロジウムのパートナーで、調査の共著者でもあるダニエル・ローゼン氏は、中国政府の支援が家計より製造業に偏り、特に電池やEVといった分野で国内需給の不均衡が拡大していると指摘する。その結果、補助金を受けて製造された中国製品が世界市場にあふれかえり、他国と貿易摩擦を引き起こしている。トランプ政権は他国との貿易交渉を利用して中国を孤立させる意向を示しているが、米国政府が貿易交渉で具体的にどのような要求を提示したかはまだ明らかになっていない。ローゼン氏によると、中国の強みは市場の規模と、製品を短期間で商品化する能力だ。「米国が他国と連携すれば、規模で中国に匹敵するチャンスはある」とローゼン氏は語る。
以上のように、中国は10年前に習主席の看板政策として大規模な産業政策「中国製造2025」をスタートさせ、西側との技術格差の縮小に成功した。税制優遇措置、政府系ファンドによる投資などを通じた巨額の国家支援によって、鉄道や電力設備、医療機器、再生エネルギー製品などの輸入品への依存をなくすか減らし、造船、ロボット工学などの分野で外国企業から市場シェアを奪い、国際競争力を高めたのである。中国は今後も西側との格差を縮小し、競争力を強化することは間違いないとして記事は、米国を含む先進国がリスクに直面していると警告する。この問題に対する第2次トランプ政権の対応姿勢はいまのところ判然としていない。これから始まる米中関税協議の中でどのように議論されるのか、注目したい。
台 湾
☆ 急騰する台湾ドル
台湾ドルが米国との貿易協定を懸念して2日間で6.5%も急騰したと、5月5日付フィナンシャル・タイムズが報じる。記事は、生命保険会社が米国資産のヘッジ不足をカバーするために動き台湾ドルが急騰したが、台湾中央銀行は、米国が貿易取引の一環として通貨高を要求したとの主張を否定したと以下のように伝える。
生命保険会社がドナルド・トランプ米大統領との貿易協定に為替レートが含まれるかもしれないと懸念し、米国資産のヘッジに動いため、台湾ドルは2日間で過去数十年で最大となる急騰を記録した。月曜日の取引開始時に上昇幅を拡大した台湾ドルは、対グリーンバックでさらに2.5%上昇、2日間の上昇率を6.5%に伸ばした。4月に入ってからの総上昇率はほぼ10%である。
台湾の急激な為替変動は、アメリカの貿易戦争の影響がいかに世界経済に波及しているかを示している。台湾の輸出志向経済の競争力を損ない、台湾の生命保険会社が米国資産を保有することで損失を被る可能性もある。香港のBNPパリバのストラテジスト、ジュウ・ワンは「地元輸出企業はパニックに陥っており、地元の生命保険会社はヘッジ不足に陥っている。中央銀行は依然として唯一の買い手だが、市場を積極的にサポートしていないため、為替問題が貿易協議の一部であるとの憶測を煽っている」と述べた。これに対し、頼清徳総統は米国が通貨高を要求したとの憶測を打ち消そうとしている。台湾の対米貿易黒字は為替レートとは無関係であり、「台湾とアメリカの交渉では当然言及されない」と月曜日に地元メディアに提供したビデオメッセージで述べた。
台湾には170億ドルもの海外資産があり、その多くは生命保険会社が保有する米国債(国債や社債を含む)である。しかし、これらの保険会社の多くは為替ヘッジを行っていないため、米ドルが下落すると損失を被ることになる。アナリストによれば、市場が下落する中、そうしたリスクをヘッジしようと急いだことが、為替の動きを悪化させた可能性があるという。米国との貿易協定に台湾ドルの強化条項が盛り込まれる可能性があるとの憶測も通貨急騰を煽っている。
台湾の中央銀行はまた、米財務省が通貨高を要求していないことを改めて強調した。また、米国の関税交渉に通貨切り上げの要求が含まれる可能性があるとの主張については、「事実ではなく憶測」だと述べた。BNPのワン氏は懐疑的だ。「通貨評価が交渉のポイントであることを公式に認める国・地域はないが、市場の予想はそうでないことを示している。次期米経済諮問委員会(CEA)委員長に指名されているスティーブン・ミラン氏が論文のなかで示した新たな多国間通貨合意の枠組みであるマール・ア・ラーゴ合意で、米国の貿易不均衡の根本原因はドルの過大評価であると強調されたことを考えると、この見方は注目に値する。
世界的に競争力のある半導体部門に牽引され、台湾は米国にとって第7位の貿易相手国である。2024年の対米貿易黒字は740億ドルだった。世界最大の半導体受託生産会社である台湾積体電路製造(TSMC)の株価は月曜日、1.3%下落した。ドル安はTSMCの現地通貨ベースの利益に打撃を与えるだろう。
以上のように、台湾ドルが急騰している。その原因として、多額の米国資産を持つ台湾の生命保険会社が為替リスクヘッジのために動いたことが指摘されている。また台湾生保のそうした動きの背景には、米国との貿易協定に台湾ドルの強化条項が盛り込まれる可能性があるとの憶測が伝えられている。ただし台湾中央銀行は、米国が貿易取引の一環として通貨高を要求したとの噂を否定し、さらに頼清徳総統までも、台湾の対米貿易黒字は為替レートとは無関係であり、「台湾とアメリカの交渉では当然言及されない」とのメッセージを発信し、米国が通貨高を要求したとの憶測を打ち消そうとしている。だが、台湾は米国の第7位の貿易相手国で2024年の対米貿易黒字は740億ドルに達していると報じられている。米政府が米ドル安、台湾ドル高を要求しているとしても不思議はない。対米貿易戦争がアジア諸国の通貨情勢に影響を及ぼし始めていると言えよう。
韓 国
☆ 分断からの回復を誓う二人の大統領候補
尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領が非常戒厳(以下、戒厳令)の発動をめぐって失脚した後、次期大統領候補として野党「共に民主党」から李在明(イ・ジェミョン)、与党「国民の力」から金文洙(キム・ムンス)の2人が決まった。5月11日付ニューヨーク・タイムズは、この両人は尹氏の失脚をめぐって分極化した韓国の正反対の立場を代表しているが、ともに分断された韓国の回復を誓っていると概略以下のように報じる。
韓国の次期大統領選で激戦を繰り広げる2人の候補者は、大きな困難を乗り越えて今に至っている。李在明は10代の汗水たらして働く労働者で、家族は腐った果物で生計を立てていた。金文洙は反政府活動のために投獄され、拷問を受けた。両者とも、大統領選の行方を左右しかねない政治的・法的混乱から数週間を生き延びた。月曜日に始まる6月3日の大統領選挙に向けた公式キャンペーンを控えて、李氏と金氏はともに当選すれば国民統合を追求すると公約しているが、政治的な溝は埋まりそうにない。選挙戦は政策というよりも、尹氏と彼の右派政党である「国民の力」に対する国民投票として戦われている。
同党は、内乱罪で裁判にかけられている尹氏との関係を断ち切ってはいない。その代わり、尹政権の元労働大臣である金氏を大統領候補に選ぶことで、さらに右傾化している。12月の国会で尹氏の閣僚が戒厳令の発動について謝罪を求められたとき、金氏だけが起立して頭を下げることを拒否した。ライバルである李氏(60)は、選挙前の調査でリードしている。前例のない89.77%の得票率で「共に民主党」の大統領候補指名を勝ち取った後、彼は言った。「私は反乱と後退の古い時代を終わらせ、希望の新時代を開くよう命じられた」。
李氏と金氏(73)はともに、大統領選に出馬するための最後のハードルをクリアしなければならず、ここ数ヶ月韓国政治を覆っている不確実性に拍車をかけている。選挙法違反の刑事告発を受けている李氏は、ソウル高裁が判決を選挙後まで延期するまで、その出馬資格が脅かされていた。他方、金氏は小選挙区で勝利したが、与党指導部は同氏の立候補を取りやめさせ、李氏より有利だと主張する韓徳洙前首相兼大統領代行に交代させようと動いた。金氏は党幹部に対して法的措置をとり、彼らを「怪物」と呼び、「政治クーデター」だと非難した。週末、党員たちは金氏の立候補を復活させることを決議し、韓氏は選挙戦から身を引いた。金氏は、李氏が大統領に当選し、その党が国会で多数を占めれば李は左翼の巨人となり、韓国は米国との同盟を犠牲にして中国と北朝鮮により友好的になるだろうと警告した。「彼はすでに独裁者だ」と言い、李氏を北朝鮮や中国の指導者と比較している。「金正恩と習近平以外に彼の党の89.77%の支持を得る者がいるだろうか」。
6月の選挙は、尹氏の戒厳令によって解き放たれた政治闘争の延長線上にある。京畿大学の政治学者であるソン・ドク・ハム氏は、「進歩派にとっては、暴動を終わらせることが選挙の主要テーマだ。しかし保守派を突き動かしているのは、李在明が当選すれば、超ワンマンの大統領となり、彼らの陣営を崩壊させるだろうという恐れである」。しかし李氏の生い立ちは、韓国の多くの人々の共感を呼んでいる。彼が10代の頃、家族8人でソウル南部のスラム街にある半地下の小屋に引っ越してきた。両親はゴミ集めと公衆便所の掃除で生計を立てていた。小学校卒業後、彼は野球グローブ工場やその他の労働搾取工場で働いた。左腕はプレス機で潰され、後遺症が残った。
「父の汚れた荷車を後ろから押しながら、通学する少女たちを見たとき、恥ずかしくて街角に隠れてしまった。しかし、私の惨めな人生は、困難を乗り越え前進する力を与えてくれた」。中学や高校には通わなかったが、李氏は大学入試に合格した。人権派弁護士、市長、州知事、国会議員、韓国最大政党の党首、そして2度の大統領候補となった。政治家としてのキャリアを頓挫させかけた刑事告発や、命を狙われたこともある。
市長時代、李氏は学校の制服や産後ケアの無料サービスを提供した。知事時代には、若者の就職や学費のために現金ボーナスを支給した。パンデミック救済金を全住民に配った最初の知事でもある。また同氏は攻撃的な一面も持っていた。パンデミック(世界的大流行)の最中、人口の多い京畿道で、対人間の距離を取って感染を防止するソーシャルディスタンスを厳格に実施した。これは 後に中央政府も採用した措置である。風光明媚な渓谷から不法飲食店を駆逐してもいる。李氏は2度目の大統領選に出馬するため(2022年に尹氏に敗れた)、政治的復讐をせず、国民統合のために働くと約束することで、中間層の有権者へのアピールを拡大しようとしている。彼はイデオロギーよりも効率と現実主義を強調した。親中・反米」という保守派の非難に対抗するため、李氏は自国の米国との同盟関係や、地域の安全保障のための米日の3国間協力の重要性を強調している。しかし、保守派のライバルは彼を冷酷な「ポピュリスト」と呼び、納得していない。
他方、金氏は保守派の支持を集めるために選挙で人気のある人物に対するそのような疑念を利用している。金氏は1970年代から80年代にかけての有名な進歩活動家である。反政府活動のためにソウル大学から2度追放された。労働組合を作るために労働者に変装した学生活動家たちを率いた。軍の諜報員による拷問を受けながらも、逃亡中の仲間の活動家の居場所を明かすことを拒んだ。創設に貢献し国民統合を追求すると公約しているが、政治的な溝は埋まりそうにない。6月の選挙は、尹氏の戒厳令によって解き放たれた政治闘争の延長線上にある。労働運動は、今でも強力な左翼政治勢力である。しかし、金氏は破天荒でもあった。民主化後の1990年代、多くの元活動家が民主党に入党したのに対し、保守陣営に入り議員や州知事になった。その後、ソ連圏の崩壊を目の当たりにして「革命主義者」「反米主義者」であった自分を捨てたと語っている。金氏は尹氏の戒厳令は間違いだったと呼んだ。しかし尹氏を極端な措置に駆り立てたのは、国会における左翼野党の妨害戦術だと非難した。当選すれば、韓国を米国にとってより信頼できる同盟国にし、北朝鮮に対する抑止力を高めると述べた。自分も民族融和のために働くと語った。
以上のように、記事は6月の大統領選は尹全大統領と彼の右派政党である「国民の力」に対する国民投票として戦われていると評したうえで、与野党の候補者の経歴や人となりを詳細に紹介する。李候補については、極貧の生い立ちと共に人権派弁護士、市長、州知事、国会議員、韓国最大政党の党首、そして2度の大統領候補となったが、その間、政治家としてのキャリアを頓挫させかけた刑事告発や命を狙われたこともあると、その有為転変ぶりを紹介する。金候補につては、投獄や軍の拷問にも耐えた有名な進歩活動家で「革命主義者」「反米主義者」だったが、ソ連圏の崩壊を目の当たりにして自分を捨てた破天荒な人物だと評する。そして、両人は分極化した韓国の正反対の立場を代表しているが、ともに分断された韓国の回復を誓っていると報じる。しかし、記事が指摘するように、その政治的な溝は埋まりそうになく、大統領選が尹氏の戒厳令によって解き放たれた政治闘争の延長線上にある以上、李候補の優勢は変わらないとみられる。
北 朝 鮮
☆ 大量の労働者をロシアに送り込む金総書記
労働力不足を補いたいロシアでは、低賃金で長時間働く北朝鮮労働者がロシア企業に好まれている。だが、その存在は制裁違反でもあると5月7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルが概略以下のように報じる。
金総書記はプーチン大統領と同盟関係を深める中で、ウクライナ戦争の継続に伴う負担が増大するプーチン氏を支援するために兵士と武器を供給してきた。その金氏からの最近の「贈り物」は労働者だ。労働力不足はプーチン氏を悩ませる大きな問題であり、出生率の低下に戦争が重なり状況は悪化した。西側の推計によると、戦闘で死亡したロシア人は数十万人に上り、加えて多くの国民がロシアから国外に脱出した。労働力不足は現在の150万人から2030年までに240万人に拡大する可能性があるとロシア労働省はみている。
国連安全保障理事会は、北朝鮮からの出稼ぎ労働者の雇用を禁止している。だがロシアと北朝鮮は、核兵器開発を巡る金政権への制裁措置と同様、こうしたルールを無視してきた。そうした状況のなかで現在、北朝鮮の労働者がロシアに大量に流入している。低賃金で文句も言わずに1日12時間働く姿勢が現地の雇用主に好まれている。韓国の情報機関は4月30日に議員らへの説明で、北朝鮮がロシアに派遣した労働者は約1万5,000人に上るとした。労働者の多くは学生ビザで入国したとみられている。ロシア統計によると、入国した北朝鮮人の数は2024年に前年の12倍に急増した。北朝鮮労働者が派遣される先はいまのところ主にロシア極東地域に限られているものの、ロシアの産業界幹部や当局者らの間では、労働者がすぐにでも首都モスクワなどの主要都市で働くことを期待するとの声が広がる。
プーチン氏はロシアと北朝鮮の友好関係を「戦場で培われた」ものとして称賛している。ロシアの労働力不足は、たとえ北朝鮮からの労働者が急増したとしてもそれだけでは埋められないほど大きい。ただ、プーチン氏が産業拠点としての発展を目指してきたロシア極東地域では、金政権の貢献は極めて大きくなるとみられる。ロシアは長年にわたり、ロシア極東の復興に取り組んできた。木材や鉱物、石油が豊富で中国の投資家からも関心を集めている。この地域の人口減少を食い止めるため、無償で土地を提供するなどしてきたが成果は限定的だった。ロシアは金政権に対する国連の制裁を順守していると主張する一方で、北朝鮮に対する制裁緩和を提唱している。プーチン氏は昨年6月、北朝鮮出稼ぎ労働者の雇用を禁止する国連の措置を批判し、その数週間後には平壌を訪問、金氏と相互防衛に関する協定を交わした。プーチン氏はロシア国営メディアで北朝鮮を「隣人」と形容し、「人々が好むと好まざるとにかかわらず、われわれは関係を発展させていく」と語った。
北朝鮮からロシアへは以前も労働者が派遣されてきた。数十年にわたり数万人が送り込まれ、大半は建設や木の伐採に従事した。脱北者らは、労働者の賃金の90%以上は金政権の懐に入るものの、手元に残る100~200ドルは毎月数ドル相当を稼ぐのが精いっぱいの北朝鮮では大きな金額であることに変わりはないと語る。北朝鮮労働者の雇用を禁止する国連の措置が2019年後半に発効したことを受け、当時ロシアで働いていた3万人のうち数千人が帰国した。ロシアの労働力には打撃となった。ロシアでは、ここ数年の間に中央アジアの旧ソ連諸国からの移民労働者に頼る姿勢が強まった。こうした労働者はロシアで働くほうがはるかに多く稼げ、送金を通じて母国の経済を支えている。ただロシアにとって北朝鮮労働者が魅力的であることに変わりはなく、それには2022年のウクライナ侵攻開始以降、北朝鮮がプーチン氏を大々的に支持する希少な存在になったことも大きく影響している。
モスクワにある建設会社で取締役を務めるアンドレイ・オルロフ氏は、国連の禁止措置以前には数十人の北朝鮮人を雇用していたと話した。当時は北朝鮮人の仲介者の助けを借りて労働者を募集していた。最近、オルロフ氏はこの仲介者とモスクワで面会したという。両氏はレンガを積んだりコンクリートを流し込んだりできる労働者について話し合った。オルロフ氏は人手不足に対する不満を訴え、数年前の2倍の賃金を要求する労働者もいるとした。両氏の間で合意が成立し、50人の北朝鮮労働者が近く派遣されることになった。オルロフ氏は夏までに労働者が到着すると見込んでおり、最終的に300人以上を雇う考えだとしている。規制違反がないよう弁護士を雇う計画だという。「数は多いに越したことはない」とオルロフ氏は語る。北朝鮮の熟練労働者の雇用に関し、ロシア市場で自社がけん引役となる意欲を示すとともに、制裁措置にかかわらず両国が何らかの合意を結ぶことを期待していると話した。
ロシア建設業界の主要労働組合によると、業界では労働力不足への対応の一環として北朝鮮人を雇用している。ロシアによる制裁逃れに関する2024年3月の国連報告書では、ロシア国内では約120社が北朝鮮人を雇用していることが示された。ロシア側では、報告書で特定された企業の多くはすでに活動が停止しているか、情報は古いとしている。ロシアのマラト・フスヌリン副首相は北朝鮮の労働者について、ロシアが支配するウクライナ東部の一部地域を含め、戦争被害地域の再建を支援する可能性を示唆している。北朝鮮のタイル職人は1人でロシア人2人分の仕事をこなせると同氏は話した。北朝鮮労働者による多大な貢献が見込まれるロシアの極東地域では、両国の関係深化を示す兆候が至る所に見られる。列車は定期的に国境を越えて運行し、北朝鮮の複数都市に向けて毎日複数の便が出発し、国境を流れる豆満江では新たな橋の建設が進められている。地元メディアは9月、人手不足などで遅延が続いた主要都市の学校建設を支援するために北朝鮮の労働者が招かれたと報じた。
以上のように、ロシアでは国連の制裁措置を無視して大量の北朝鮮労働者が働いている。記事は、そうした労働者を金総書記からの「贈り物」と表現する。戦争や出生率の低下による労働力不足に悩むロシアにとって、それだけ貴重な存在となっていると言える。国連の北朝鮮労働者雇用禁止措置が2019年後半に発効したものの、その数は現在1万5,000人に上り、多くは学生ビザで入国し、しかも2024年に前年の12倍に急増しているとされる。派遣先はいまのところ極東地域に限られているが、モスクワなどの主要都市に拡大するのも時間の問題とみられる。
東南アジアほか
ベトナム
☆ 次の中国を探す中国の工場
米国の高率関税が中国の輸出を阻むなか、トランプ政権1期目から始まったベトナムへの製造業の移転が加速していると、5月10日ニューヨーク・タイムズが伝える。記事は、中国企業がトランプ大統領の不利な関税から逃れるために近隣諸国に軸足を移していると以下のように報じる。
ジーンズからクリスマス商品まで、あらゆるものを製造する中国の工場がベトナムへの進出を急いでいる。すでに進出している工場は、その勢いを増している。中国のeコマース・プラットフォームであるアリババとSHEINは、ベトナムに製造拠点を置く企業を支援している。中国からの脱出競争は、ここ数週間で急ピッチに進んでおり、ベトナムだけでなく、タイやマレーシアのような場所を経由して商品を迂回させる方法のヒントを提供するフィクサーのソーシャルメディアが急浮上している。ここ数週間、米国に製品を送るコストが高騰しており、工場は新たな貿易ルートを探す必要にも迫られている。金曜日に発表された中国政府データによると、先月、アメリカへの出荷が急減するなか、中国の東南アジアへの輸出が急増した。
トランプ氏は中国に145%の関税を課したが、ベトナムや他のアジア諸国への新たな関税は7月上旬まで一時停止した。このためアジア全域の工場は大忙しだ。ベトナム北部に7つの工場を所有し、中国企業からの依頼が殺到しているヴー・マン・フン氏は、「誰もがベトナムのパートナーを見つけようと急いでいるように感じる」と語った。こうした中国企業は彼の工場が、高関税の中国国内では不可能な注文を請け負ってくれることを望んでいた。しかし、彼はどんな取引にも応じなかった。その理由のひとつは、アメリカの顧客から7月までに注文を納品するようプレッシャーを受け、彼の製造ラインがすでに忙しくなっていたからだ。
このような中国のサプライチェーンにおけるパニックは、これまでにもみられた。2018年に多くの多国籍企業が商品を製造する代替地を探すことに迫られたが、当時の米関税は国外脱出を引き起こすほど厳しいものではなかった。しかし今回のトランプ関税は非常に高く、米中間の貿易を全面的に停止させ、中国企業を中国から追い出してさえいる。中国企業にとって、ベトナムは長短期両方での解決策になっている。両国は国境を接しており、ベトナムには工場での肉体労働に意欲的な若者が多い。しかし、ベトナムには課題もある。関税が保留されている他の数十カ国とともに、ベトナムは米国と貿易協定を結ぼうとしているが、米国政府関係者は対米輸出の迂回手段として中国がベトナムを利用することを制限したいと考えている。第一次米中関税戦争の間、中国企業はベトナムに工場を建設した。現在、それらの工場の多くは受注を拡大している。
その一例が2019年にベトナムで操業を開始したQISスポーツグッズ社だ。同社は、キックボード、サーフボード、スタンドアップパドルボードなどのウォータースポーツ製品を中国南部の東莞市とベトナム北部の2つの工場で製造している。中国で約150人、ベトナムで約400人を雇用しており、さらなる雇用を急いでいる。もうひとつの中国企業、東莞ボックスは最近、ティファニーやホールマークといったアメリカ人顧客のためだけにベトナム工場に生産ラインを完成させた。マーケティング・マネージャーのリタ・ペンによれば、アメリカの顧客から電話がかかってくるようになったのは、トランプ氏が中国製品への関税をエスカレートさせ始めた4月からだという。彼らはこう尋ねた。生産拠点をベトナムに移せないか。ペンは喜んで引き受けたが、そう変えてもほとんど意味がないと付け加えた。紙でできた花が描かれ、両面開きの精巧な赤いギフトボックスを手に取り、この箱全体をベトナムで作るとなると、コストはとても高くなるからだとその理由を説明した。中国では1ドルで作れる箱がベトナムでは1.20ドルになる。ペンは、ベトナム工場は米国向けだけとして、ヨーロッパ顧客への注文には引き続き中国の工場を使うことを望んでいると語り、今の状況は一時的なものだと考えていると述べる。「アメリカはすぐにこれらの問題を解決してくれると信じている」。
eコマース・プラットフォームは、中国の工場が代替品を見つけるのを助ける役割を果たしている。ある工場経営者によれば、ファストファッション・プラットフォームのSHEINは、中国の工場のベトナム移転費用を支援するインセンティブを提供しているという。また、eコマース大手のアリババは、ビジネスパートナー探しを支援するためベトナムに従業員を派遣し、ベトナムでの関税一時停止が終了する前に企業が中国に代わる選択肢を見つける手助けをしていると、アリババのベトナム人アカウント・マネージャーは語る。中国のソーシャルメディア上では、貿易ルールを回避するためのヒントを提供するエージェントが次々と現れている。例えば、「小紅書(RedNote」としても知られる中国のアプリ「シャオホンシュー」に最近投稿されたものでは、製品をマレーシアや近隣の国に発送し、米国に送る前に再梱包することでメイド・イン・チャイナの原産地を隠す方法が紹介されている。
最近、ベトナムへの関心は中国南部の都市広州で明らかになった。ある縫製工場の経営者によれば、同業者の何人かがベトナム進出を始めたという。クリスマスのリボン、ストッキング、リース、ギフトバッグを製造する中国企業、賈越科技(Jia Yue Technology)は、すでにベトナムへの進出を果たしている。ホーチミン市で開催された見本市で同社代表の通訳をしていたジャック・シュー氏は、「過去3年間で、生産量の半分以上を中国からシフトした」と語った。そして今、顧客のほとんどが米国にいるため、ベトナムでさらに生産するかどうか思案中だという。
以上のように、対中輸入品に対する高率の米関税を回避するためベトナムやタイやマレーシアなどを経由して米国に輸出する迂回取引が増加しているが、同時に工場自体を近隣諸国、とりわけベトナムに移す動きが加速している。こうした動きは、雑貨品を生産する中小企業のみならず、中国のeコマースやソーシャルメディアまで巻き込み、関税回避のためのヒントを提供するエージェントなどが現れているという。ただし米政府は今回、ベトナムに対して46%という特別な高関税を課しており、ベトナム内生産の競争力は限られていると思われる。その一方で、ベトナム企業経営者の一部に米関税は一時的で米政府が解決してくれるのではないかという期待感があるのが注目される。
インド
☆ 再燃する印パ戦争の懸念
先月、インド統治下のカシミールで過激派による襲撃事件が発生し、これがインドとパキスタンの両国間に再び激しい対立を引き起こした。カシミールをめぐってインドとパキスタンは数十年にわたる紛争を繰り返してきた。5月10日付ワシントン・ポストによれば、襲撃事件に関連してインドは、パキスタンが分離主義武装勢力を支援していると繰り返し非難、今週、この半世紀以上で最も大規模なパキスタン国内への攻撃を開始した。さらにワシントン・ポスト記事は、これを受けてトランプ米政権が即時停戦に動き、印パ両国も停戦を受け入れたと伝えるとともに米国は印パ両国の停戦に貢献したが、それは維持されるだろうかと疑問を提起する。記事によれば、この4日間、両国の主要都市の空では、ミサイルや無人機が飛び交い、核武装した隣国同士が全面戦争に突入するかと思われるような神経をすり減らす夜が続いていたが、トランプ大統領が突然、即時停戦を発表したという。
さらに同紙は11日付記事で次ように伝える。インドとパキスタンは完全かつ即時の停戦に合意したとトランプ大統領は土曜日、トゥルース・ソーシャルに投稿した。しかし両国が祝賀ムードに包まれ、米政府が自画自賛する中、カシミール地方はまたもや一晩の暴力に耐え、双方が違反を主張した。米国が仲介した停戦の突然の発表は、4日間にわたる地域ライバル国の対立の着実なエスカレーションに続き、米国が仲介者としての伝統的な役割を再び果たすかどうかをめぐって複雑なシグナルを発した。
事情に詳しいある人物は匿名を条件に次のように語った。JDバンス副大統領は金曜日の正午ごろ、米政府高官らが事態の悪化を懸念するなか、インドのナレンドラ・モディ首相にワシントンから電話をかけ「停戦」の可能性を提示し、パキスタン当局者もそれを受け入れるだろうと米政府高官は理解したとされる。その後12時間から18時間にわたって、米政府高官たちは双方の相手方と電話会談を行った。マルコ・ルビオ国務長官も金曜日夜、インドとパキスタンの高官の間を行ったり来たりして、取引を成立させたという。
パキスタン政府は土曜日、アメリカの役割をすぐに認めた。あるパキスタン政府高官は、今回の合意は2つの要因に基づくものだと述べた。「ひとつは、対立がエスカレートする深刻な危険性、もうひとつは米政権、つまり外部からの介入だ。これに対してインド政府関係者は、米国の役割についてはあまり積極的な関心を示さなかった。インド政府のコメンテーターの中には、インドがパキスタンとの「広範な問題についての協議」に合意したというルビオ国務長官の主張を公然と問題視する者もいれば、インドが伝統的に紛争地カシミールに関する第三者の仲介に反対しており、二国間で問題を処理することを好んでいると指摘する者もいた。しかし、土曜日の停戦は、たとえ微妙なものであったとしても、ウクライナとガザでの戦争を終わらせるというトランプ大統領の選挙公約が今のところ実現できていない政権にとっては勝利である。
介入は最終的に成功したが、それはインドもパキスタンも大規模な戦争へのエスカレートを望まず、双方が勝利を主張するのに十分な損害を相手に与えたからである。インドはパキスタンの基地に損害を与え、ラホールの航空レーダーシステムを破壊し、さらなる越境攻撃が計画されているとする「テロリスト・キャンプ」を破壊したと主張している。パキスタン当局は、インド奥地の軍事目標を攻撃し、敵の戦闘機を5機撃墜したと主張している。本紙のビジュアル分析によると、インドは水曜朝のパキスタン国内での最初の攻撃で少なくとも2機のフランス製戦闘機(ラファールとミラージュ2000)を失ったようだ。インドのミスリ外務次官は記者団に対し、両軍事作戦局長が月曜日に再び話し合うと述べたが、他の問題を話し合う予定はないと指摘し、現在の平穏のもろさを示唆した。
以上のように、カシミールをめぐり数十年にわたる紛争を繰り返してきたインドとパキスタンは先月、過激派によるカシミールでの襲撃事件を契機に再び激しく対立した。しかしトランプ米政権の仲介で停戦に合意した。合意に至った背景としては、米政権、つまり外部からの介入の他に紛争エスカレーションの深刻な危険性と、双方が勝利を主張するのに十分な損害を相手に与えたことが挙げられている。ただしカシミール地方ではまたもや暴力事件が発生し、双方が違反を主張しているが、停戦はたとえ微妙なものであったとしてもウクライナとガザでの戦争を終わらせるという選挙公約を今のところ実現できていないトランプ大統領にとっては勝利だと記事は指摘する。記事が報じるように停戦前夜、米政府高官が忙しく動き回った様子からみて、トランプ政権発足後の、数少ない成果の一つと言えるかもしれない。
§ § § § § § § § § §
主要紙の社説・論説から
トランプ関税をめぐる日米交渉について-交渉の先頭に立った日本の役割と責任
発足して100日余りが経ったトランプ米政権は、この間に数十カ国に対して「相互関税」を課し、各国と交渉を開始した。そうした対米交渉の先頭に立ったのが日本である。以下は、交渉に臨む日本の置かれた立場や責任に関するメディアの論調を要約したものである。(筆者の論評は末尾の「結び」を参照)
まず日本の置かれた立場に関して、4月3日付ニューヨーク・タイムズ記事「Japan Lacks a ‘Viable Option’ for Retaliating to Trump’s Tariffs (トランプ関税に報復する「有効な選択肢」に欠ける日本)」は、対米輸入品への報復関税はインフレに苦しみ選択肢が限られている日本経済にとって自滅的であり、日本は融和的な戦略をとると、以下のように論じる。
米国から2桁パーセントの関税をかけられた日本は、報復の選択肢がほとんどないことに気づいている。トランプ大統領が1月に広範な関税をかけると脅し始めて以来、日本は融和的な戦略をとってきた。石破茂首相は2月、対米投資を1兆ドルに引き上げると公約した。水曜日にトランプ氏が関税を発表する前日まで、著名な企業経営者たちは、日本が関税を免れることを期待していたが、その期待は、トランプ氏が日本からの輸入品に24%の関税を課すと発言したことで打ち砕かれた。先週には、日本の対米輸出品のトップにある自動車に25%の税金がかかると通告された。欧州連合(EU)、カナダ、中国など、米関税の影響を受けている他の国々は、米国製品への課税で報復する意向を表明しているが、日本の政府関係者は同様の動きについて語ることを控えている。それは日本経済の現状と対米貿易の重要性から、そうすることが難しいからだとアナリストは言う。
ここ数年、日本ではエネルギーと食料品の高騰を主因とするインフレが急伸し、経済を圧迫している。日本がアメリカから輸入しているのは、天然ガスや農産物など、ほとんどがコモディティである。ムーディーズ・アナリティックス東京のシニアエコノミストは、「対米輸入品への報復関税は自滅的であり、全く実行可能な選択肢ではない。唯一残る戦略は、シナリオを転換し、日本がより多くの商品を輸入する意欲があることを強調することだ」」と語る。トランプ氏を含む米政府高官は、日本の非関税障壁について繰り返し懸念を表明してきた。具体的には、コメのような農産物の輸入制限や自動車規格を挙げている。木曜日の記者会見で、林芳正官房長官は日本が対米貿易交渉で譲歩することについてコメントを避け、首相を含む他の政府高官は報復措置について言及を避けた。日本が国内で使用する自動車認証基準は、国連が定めたものに基づいていると林長官は述べる。また日本のコメ輸入政策の背後にある詳細と論理を米政府のカウンターパートに説明したと語り、「にもかかわらず、アメリカ政府が今回のコメの相互関税措置を発表したことは非常に遺憾だ。いずれにせよ、日本は米国に対し、その措置を見直すよう引き続き強く求めていく」と付言した。
さらにニューヨーク・タイムズは、4月23日付記事「Japan in a Tight Spot (窮地に立たされた日本)」で、日本は長い間、米中両方と深い経済的関係を維持してきたが、貿易戦争のためにこのアプローチが覆されるかもしれないと、以下のように指摘する。
日本は米国に大量の自動車を中国にはコンピューター・チップとチップ製造装置を販売し、過去20年間、日本の輸出先は米国と中国が交互に上位を占めてきた。それに匹敵する国は他にない。今、トランプ大統領が米国の貿易相手国を中国に対抗させようとし、中国がその呼びかけに応じる国々を脅すなかで、日本はジレンマに直面している。どちらの側にも背を向けることは、日本経済を深く動揺させる危険性がある。先週行われた初の対面関税協議にトランプ政権は日本を選んだ。トランプ氏は、数十カ国に課した「相互関税」の脅威を維持し、7月上旬まで一時停止している。日本の場合、その関税は24%で、政府高官は日本経済に危機をもたらすだろうと述べている。過去10年間、日本は2つの経済大国の間に挟まれ、微妙な道を歩んできた。中国への依存をヘッジする一方で、米国の政治から距離を置くというステップを踏んできたのだ。専門家たちは、日本を急速に追い込んだり、中国との経済的なつながりを強引に縮小させようとしたりすれば、大きな抵抗に直面するだろうと指摘する。
最近、スコット・ベッセント財務長官をはじめとするトランプ政権の高官は、中国とそのいわゆる経済的強制力に対抗するためのアメリカの政策に沿った貿易相手国との合意を目指すことを示唆している。こうしたトランプ政権の動きに注目している中国政府は月曜日、他の国々に対し、米関税からの猶予を得るために中国との貿易を抑制しないよう警告し、そのようなことをした国には報復すると宣言した。人口減少を背景に日本企業は海外進出の必要性に迫られているが、そのため中国に代わる選択肢を見つけることが難しくなっている。一方、エコノミストたちは、米国が脅す24%の関税は、日本の経済成長と国内産業に壊滅的な結果をもたらすだろうと警告している。米国と中国が互いに100%をはるかに超える水準まで関税を引き上げる中、日本が貿易関係を維持できるかどうかは、世界第4位の経済大国である日本の経済にとって重大な意味を持つ。
4月9日付フィナンシャル・タイムズ記事「Japanese market walks a geopolitical tightrope (地政学的な綱渡りをする日本市場)」は、日本がライバル同士の米中の間で、それぞれから忠誠を求められて不安定な状態に陥っていると以下のように論じる。
世界的な貿易摩擦のドラマが展開されるなか、日本は再び米国の圧力にさらされている。しかし、日本からの自動車や電子機器の輸出によって増大するアメリカの貿易赤字が対立の中心であった1980年代とは異なり、今日の利害関係ははるかに複雑である。当時は対米関係の境界線が明確で、中国はその枠外にいた。今、日本は、それぞれが忠誠を求める2つのライバルの間で不安定な状態に陥っている。ここ数日の日本株の乱高下は、楽観と失望の波が交互に押し寄せている。月曜日に石破茂首相とドナルド・トランプ米大統領が電話会談を行い、関税交渉の突破口が開かれるとの期待が高まった。米国の通商当局トップは日本との正式な交渉開始の準備を進めており、貿易摩擦の緩和に向かって潜在的に進展の気配がある。しかし、円高が輸出企業のセンチメントに重くのしかかり、市場の意欲を削ぎ、先行きに新たな不透明感をもたらしている。
中国とのぎくしゃくした関係とは対照的に、米国と日本の関係はおおむね協力的である。しかし、日本はますます居心地の悪い立場に立たされている。経済的には、最大の貿易相手国であり、特に機械や電子機器などの高価値輸出品の買い手である中国と深く結びついている。しかし戦略的には、日本は最も重要な安全保障上の同盟国である米国と強固な関係にある。人工知能チップの需要が急増した昨年第1四半期、日本のチップ製造装置輸出の約半分は中国向けだった。公式データによれば、8月の輸出は60%以上も急増した。台湾の調査会社トレンドフォースによると、チップ生産に関連する機械類の多くは、日本の対中輸出総額の4分の1近くを占めており、日本が中国の製造業サプライチェーンにいかに深く組み込まれているかを浮き彫りにしている。
こうした利害のバランスはより複雑になっている。米国政府は日本に対し、先端チップ製造装置や関連部品を含む中国への技術輸出を制限するよう圧力をかけている。米中の緊張が深まるにつれ、日本は難しい選択を迫られている。要求に抵抗すれば米国との戦略的同盟関係を危うくしかねない。一方、米国に譲歩すれば中国との経済関係にひずみが生じかねない。日本経済は現在より脆弱になっており、外圧に特に敏感になっている。米国への主要自動車輸出国として、自動車や自動車部品への関税が小幅であっても企業収益に打撃を与えかねない。政府が需要を刺激し、貿易ショックをより効果的に吸収できる中国とは異なり、日本は低成長、低インフレの環境で数十年を過ごしてきたため、政策決定者の柔軟性ははるかに低い。日本は米国と中国の間に位置する戦略的要衝であるため、市場はメディアの人質となり、ファンダメンタルズは軽視され、ボラティリティが新たな常態となるだろう。
そうした状況のなか、日本が対米関税交渉の先頭に立つことになる。4月16日付フィナンシャル・タイムズは「Japan set for ‘guinea pig’ trade talks with US after Donald Trump’s tariffs (トランプ関税発動後、米国との「モルモット」貿易交渉に臨む日本)」と題する記事で、日本が最初に臨む対米交渉は米国政府の貿易戦争戦略のテストケースとして注視されていると以下のように論評する。
日本との交渉はホワイトハウスが貿易相手国と関税に関する協定を結ぶ意思があるかどうかの最初のテストのひとつとなる。米大統領が今月初め、数十カ国に対する厳しい「相互」関税を発表し、その後90日間同関税を一時停止した後、日本はトランプ政権との直接会談を認められた最初の国となった。水曜日、トランプ大統領は自身のプラットフォーム「トゥルース・ソーシャル」に、スコット・ベッセント財務長官とハワード・ラトニック商務長官とともに自ら会談に出席すると書き込んだ。日本は今日、関税、軍事支援費用、そして「公正な貿易」について交渉するためにやってくる」と書き、こう付け加えた。「日米とって良い(素晴らしい!)何かが達成されることを願っている!」。
外交関係者は、トランプ政権が何を達成したいのか不透明なままではあるが、協議における日本の「モルモット」としての地位は、他の国よりも有利になるかもしれないと述べた。日本の対米貿易黒字は世界で10本の指に入る。「ここ数週間のすべての不確実性、関税の武器化、貿易戦争という言葉、これらすべてにおいて、トランプ大統領が何を望んでいるのか、きちんと見えていない」と、会談の準備に近い人物は語った。「日本はこの立場を喜んでいないかもしれないが、状況が明らかになったときに最前線に立つことは大きな貢献になるかもしれない」と、その関係者は付け加えた。
経済同友会の新浪剛史代表幹事は、アメリカの交渉責任者にベッセント氏が選ばれたことは、米政府が円安に対処するよう日本に圧力をかけることを示唆していると語る。アメリカはまた、日本が外貨準備として約1兆1,000億ドルを保有している米国債市場の安定化を望んでいる。事情に詳しい関係者によれば、アメリカは日本が液化天然ガスの輸入を増やす方法を話し合うなど、会談での優先事項をいくつか示したという。また、コメや小麦のような米国産農産物の日本市場参入を促進し、米国が日本での販売を困難にしていると考えている自動車安全基準に対処することも望んでいるという。
日本政府関係者によると、日本はアメリカからの武器購入、日本へのインフラ投資、造船に関する協力など、様々な問題について話し合う用意があるという。2019年、日本の安倍晋三首相(当時)は、大統領との親密な関係から「トランプの耳元でささやく人(心が通じ合える人)」(“Trump whisperer”)として知られるようになり、米国との貿易協定を締結した。安倍首相が実現できたのは、一部の米国産農産物に対する規制緩和と、デジタル商取引に関する合意だけだった。
複数の専門家は、日本はアメリカの自動車関税を優先リストの上位に置くだろうと語った。「日本はおそらく、自動車関税を一時停止させることに集中するだろう」と、外交問題評議会の日米経済関係専門家マット・グッドマン氏は言う。「しかし、自動車関税はおそらくトランプ大統領に撤回させるのが最も難しいものになるだろう。ポリティカル・リスク・アドバイザリー・ジャパン・フォーサイトの創設者であるトビアス・ハリス氏は、会談におけるアメリカ側の目標が明確でないため、日本と石破氏は安倍政権下と比べて難しい立場に置かれていると指摘した。「手っ取り早いものはないだろう。日本側には、日本にとって不利な取引に応じようという気持ちは感じられない。石破氏にとっては、本当に難しい一線だ。アメリカの意向に沿うなら、国内的には代償を払うことになろう」。テンプル大学のアメリカ外交専門家、ジェフ・キングストン氏は、アメリカに対する日本国内の不安によって、会談の利害関係がさらに高まっていると語った。
こうした日本政府の対米交渉に臨む姿勢について、4月18日付ワシントン・ポストは、「Trump’s trade war leaves China’s neighbors walking a fine line (トランプ貿易戦争によって微妙なラインを歩くことになった中国の近隣諸国)」と題する記事で、同様の立場に置かれている韓国と対比しつつ、以下のように論評する。
日本と韓国はトランプ大統領に対して統一戦線を張ろうとの中国政府の提案を拒絶した。トランプ大統領が世界貿易システムの再構築を目指し、同盟国も敵対国も関税の対象とするなか、中国は隣国である日本と韓国、そして安全保障上の同盟国である米国との間にくさびを打ち込むチャンスだと考えている。しかし、日本と韓国は、少なくとも今のところはその気にならず、新たな措置を撤回するようトランプ政権を説得することに集中している。日本の加藤勝信財務相は木曜日、ワシントン・ポスト紙のインタビューで、「関税が日本経済、企業、国民生活、さらには世界経済に大きな影響を与えることを深く懸念している。日本の基本的なスタンスは、アメリカに対して一連の関税措置の再考を強く求めることだ」と語った。日本と韓国は、交渉が行われている間、10%の一律関税と、鉄鋼、アルミニウム、自動車輸出に対する25%の課税に直面している。
日本の代表団は今週、ワシントンで協議を行っている。トランプ大統領は木曜日、会談に直接介入し、その後双方は「大きな進展」を得たと主張した。韓国の通商代表団は来週、トランプ大統領と会談する予定だ。日韓両政府は、米中の間でバランスを取る必要がある。 安全保障の面で米国に依存しているが、最大の貿易相手国である中国にも依存している。中国は近隣諸国を自国の方向に向けさせようとしている。中国国営メディアは今週、各国が米国と交渉することに反対はしないが、自国を犠牲にして交渉することには警告を発していると伝えた。中国国営放送CCTVのブログ「Yuyuan Tantian」によれば、「中国の立場は非常に明確である。誰かが中国の利益をアメリカへの忠誠の証として利用するなら、中国は決してそれを受け入れないだろう」。
アナリストは、日韓両政府はトランプ政権との交渉に臨むにあたり、アラスカでの大規模な天然ガスパイプラインプロジェクトへの投資や、非関税貿易障壁の引き下げを提案する可能性があると指摘する。加藤財務相は、中国の魅力攻勢についてコメントを避け、米国の関税政策の影響について他の7カ国グループや他のアジア諸国と連絡をとりたいと述べる。関税の直接的・間接的な影響は、日本全体、そして世界全体に波及する可能性があるという。日本はまた、米中貿易戦争が国内市場に与える影響を分析する必要がある、と加藤氏は語る。日本も韓国も、中国が毎年4,000億ドル以上の製品を米国に販売しているため、安価な中国製品の氾濫を懸念している。
日韓両国の専門家は、トランプ大統領の関税措置が、グリーン・テクノロジーや共同研究、先端技術への投資など、いくつかの分野で日中両国がより緊密に協力することにつながる可能性があることを認めている。そして、日韓の中国製品の氾濫に関する計算が現実のものとなる可能性も指摘する。しかし、日韓が米国を疎外するのではなく、米国と協定を結びたいと考えている今、三国間の協調的な対応は政治的・安全保障的リスクとなり、米政府に誤ったメッセージを送ることになるという。「韓国、中国、日本が力を合わせてアメリカに対抗するというメッセージを送れば、韓国だけでなく日本にとっても重荷になる。私たちはバランスを保つ必要がある。韓国にとって、一方に傾けば外交的、経済的リスクは甚大だ」と語った。
日本の外務省は声明でこう述べた。「米国による関税措置に中国と共同で対処するつもりはない」。韓国の韓悳洙(ハン・ドクス)大統領代行も今月、CNNの取材に対し、中国や日本と経済的に手を組むという考えを真っ向から否定した。「そのようなルートは取らない」。政府系機関である対外経済政策研究院の韓中貿易専門家、チェ・ウォンソク氏は「われわれはバランスを保つ必要がある。韓国にとって、一方に傾けば外交的、経済的リスクは甚大だ」と語る。日本の外務省は声明でこう述べた。「米国による関税措置に中国と共同で対処するつもりはない」。
なお4月9日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、ドナルド・トランプ米大統領が4月8日、米政権が日本および韓国と関税を巡り「高度にテーラーメードされた協定」について交渉する方針だと述べたと報じる。記事によれば、同大統領は最近、鉄鋼業界幹部らと協議したことも明かにすると共に、ホワイトハウスのルーズベルトルームで行われた石炭採掘関連のイベントで、日本および韓国との協定について「既製のものではなく、テーラーメードの取引だ」と語ったという。米国側の日韓交渉に対する姿勢を示すニュースとして参考になろう。
こうした状況の中で第1回目の日米関税交渉が開かれるが、その結果について4月17日付フィナンシャル・タイムズは「Donald Trump weighs in on Japan trade talks but Tokyo team leaves without deal (ドナルド・トランプ氏、日本の通商協議に参加するも東京チームは合意なしに退席)」と題する記事で概略以下のように報じる。
日米協議は、世界貿易戦争をエスカレートさせるトランプ大統領の戦略を探る手がかりとして、世界中の政府によって注視されている。アメリカにとって最大の対外投資国であり、アジアで最も親密な同盟国である日本は、ワシントンとの関係が悪化すれば、経済面でも安全保障面でも大きなリスクを抱えることになる。アメリカはすでに日本の自動車、鉄鋼、アルミニウムに25%の関税を課し、日本政府による免除要求を相次いで拒否している。トランプ大統領の相互関税体制の下、24%の追加徴収が行われるとの見通しは日本企業を震撼させ、石破茂首相は「国難」を宣言するに至った。 財務省が木曜日に発表した3月期の日本の対米貿易黒字は630億ドルで前年比1.3%減少した。またトランプ大統領は会談に先立ち、日本が米軍基地の財政負担を増やすべきかどうかという問題を提起することを示唆した。トランプ大統領は同盟国の安全保障条約を繰り返し「不公平」と表現している。因みに日本は米軍駐留経費として年間約14億ドルを支払っている。
日本の貿易交渉代表は、米国の厳しい関税撤廃交渉の一環としてトランプ大統領と会談したが、その後直ちに合意することなくワシントンを離れる予定だ。米大統領は水曜日に赤沢亮正氏と会談し、ソーシャルメディア上で「大きな進展があった!」と述べた。日本は、世界経済に混乱を引き起こしたトランプ大統領の関税からの猶予を確保する最初の主要経済国になろうとしていた。日本政府関係者は、トランプ大統領との予期していなかった個人的な会談は、中国が世界貿易への関与を深めようとしているなか、大統領が同盟国との貿易協定を打ち出そうとする意欲の表れである可能性があると述べた。赤沢代表は会談後、記者団に対し、双方は今月中に2回目の会談を開き、早期解決を目指すことで合意したと語った。同氏はトランプ関税について「極めて遺憾だ」と述べ、ホワイトハウスに対し、両国経済を強化するような合意を追求するよう求めた。また、スコット・ベッセント米財務長官、ジェイミーソン・グリア通商代表とも会談した。ベッセント長官は木曜日、Xに「貿易に関する話し合いは非常に満足のいく方向に進んでいる」と記し、「日本の友人たち」とのさらなる話し合いを楽しみにしていると述べた。
結び:以上のようなメデイアの論調を次の4つの観点からまとめてみたい。第1は対米関税交渉に臨む日本の置かれた立場、第2は日本の対中関係における立ち位置、第3は日本に対する米国政府の対応、第4は日本として考えるべき戦略である。
第1は日本の置かれた立場である。日本は基準関税の10%と相互関税24%、それに対米輸出品のトップにある自動車に25%の関税が課されている。メディアは、欧州連合(EU)、カナダ、中国など他の国々は、米国製品への課税で報復する意向であるが、日本政府関係者は同様の動きについて語ることを控えていると指摘し、それは日本経済の現状と対米貿易の重要性から報復措置が難しいからだ、との見方を紹介する。日本がアメリカから輸入しているのは、天然ガスや農産物など、ほとんどがコモディティである。対米輸入品への報復関税は自滅的であり、インフレに苦しむ日本にとって融和的な戦略をとる以外に選択肢はないと論じる。こうしたメディアの論調は、そもそも報復関税そのものが、米国のみならず自国や他国、そして世界経済にとって有害な結果をもたらすことを考えれば、日本固有の理由があるとしても、報復措置を控えるのが得策であるのは間違いない。
第2は日本の中国との関係における立ち位置である。メディアは、日本は長い間、米中両方と深い経済的関係を維持してきたが、貿易戦争が激化するなか、このアプローチが覆されるかもしれないと警告する。日本は米国に大量の自動車を中国にはコンピューター・チップとチップ製造装置を輸出し、過去20年間、米国と中国が交互に日本の輸出先の上位を占めてきた。トランプ大統領が米国の貿易相手国をして中国に対抗させようとする一方、中国がそうした呼びかけに応じる国々を脅すなかで、どちらの側にも背を向ければ、日本経済を深く動揺させる危険があり、日本はジレンマに直面していると述べる。人口減少を背景に、日本企業は海外進出の必要性に迫られているが、そのため中国に代わる選択肢を見つけることが難しくなっている。一方、エコノミストたちは、米国が脅す24%の関税は、日本の経済成長と国内産業に壊滅的な結果をもたらすだろうと警告している。専門家たちは、日本を急速に追い込んだり、中国との経済的なつながりを強引に縮小させようとしたりすれば、大きな抵抗に遭うだろうと指摘する。
確かに日本は米中の間で地政学的な綱渡りをする不安定な状態におかれている。1980年代におけるアメリカとの対立は貿易赤字が中心にあり、中国は埒外にあった。しかし今は、日中は経済で互いに深く結びついている一方で、中国が地域で存在感を増し、日中はぎくしゃくした関係となっている。米国と日本の関係はおおむね協調的であるとはいえ、米国政府は貿易面で日本に対し、先端チップ製造装置や関連部品を含む中国への技術輸出を制限するよう圧力をかけている。その中国は隣国である日本と韓国、そして両国の安全保障上の同盟国である米国の間にくさびを打ち込むチャンスだと考えている。しかし日本と韓国は今のところ、統一戦線を張ろうとの中国政府の提案を拒絶している。だが、日本は対米交渉に当たり対中関係にも配慮した難しい対応に迫られているのは間違いない。この点については別途後で取り上げる。
第3は対日交渉に臨む米国政府の方針である。トランプ大統領が日本および韓国とは「高度にテーラーメードされた協定」について交渉する方針だと述べたと報じられている。米国側が対日交渉を自国に有利なモデルに仕立て上げようと手ぐすね引いている様子が端的にみてとれる。現に、自ら会談に出席するという予想外の行動に出ると共に、自身のプラットフォームに、日本は、関税、軍事支援費用、そして 「公正な貿易 」について交渉するためにやってくる、と書き込み、議題の枠組みを自ら提示してみせたのである。メディアは、こうした日本の立場を「モルモット」と表現するが、それが他国よりも有利になるかもしれないと述べると共に、状況が明らかになったときに最前線に立つことは大きな貢献になろうと評する。そうしたパオニア的役割を日本は担うことになったが、トランプ政権の意図や目標が不透明な中で、具体的な交渉事項として次のようなことが考えられる。
日本側からは、トランプ関税の除外、とりわけ自動車関税の免除、米国からは、米国債市場の安定化への協力、対米投資増、液化天然ガスの輸入増大、コメや小麦のような米国産農産物の日本市場参入の促進、自動車安全基準の修正変更、造船に関する協力、武器購入増、米軍駐留経費負担増など。米国側の要求事項が多く、交渉は明らかに朝貢的要素が強いものとなろう。米国は高関税という脅威を振りかざし、それを一旦先延ばしし、これを梃子にして交渉上の優越的立場を確保している。この手法は、かつて北朝鮮が核の脅威を作り出して、その脅威を軽減することで代償を得た歴史を思い起こさせる。なお第1回の話し合いで、米代表のベッセント長官はXに「貿易に関する話し合いは非常に満足のいく方向に進んでいる」と記したと報じられているが、具体的な成果に言及はなかった。第2回交渉もすでに開催されたが、取引成立には至っていない。交渉は長引くとみられる。日本としても拙速は絶対に禁物である。
最後に第4として、上記のような立場に置かれた日本は、いかなる戦略で対米交渉に臨むべきか。日本は融和的な戦略を基本としており、石破首相は2月の訪米時に対米投資を1兆ドルに引き上げ、対米輸入の増大などを強調、米政府に対しては、一連の関税措置の再考を強く求め、両国経済を強化するような合意を追求するよう促したとされる。コメのような農産物の輸入制限や自動車規格などの日本の非関税障壁については、日本のコメ輸入政策の背景や論理の詳細、日本の自動車認証基準は国連制定のものに基づいていることなどを説明して対応しようとしている。それで米国を納得させられるかは極めて疑問だが、双方にメリットがある結論を対話によって実現しようとする努力は欠かせないだろう。当然のことだが、不合理な譲歩は絶対に避けるべきだ。また日本としては中国との貿易への影響を極力避ける戦略となろう。
一つの鍵は、加藤財務相が米国の関税政策の影響について他の7カ国グループや他のアジア諸国と連絡をとりたいと述べていることや、米中貿易戦争が国内市場に与える影響を分析する必要がある、と語っていることにある。中国が毎年大量の製品を米国に輸出しているため、米国市場を失った安価な中国製品が押し寄せてくるという懸念がある。その一方で、専門家はトランプ大統領の関税措置が、グリーン・テクノロジーの共同研究や、先端技術への投資など、いくつかの分野で中国との緊密な協力につながる可能性も指摘している。ただし中国との協調は政治的・安全保障的リスクとなり、米政府に誤ったメッセージを送ることに注意すべきだろう。その意味で日本政府が「米国による関税措置に中国と共同で対処するつもりはない」と述べているのは当然だろう。
以上のような状況を考慮しつつ今後、日本の方針として大きく次のような3つの方向性が考えられると思われる。
第1は米国が自由貿易の旗手としての地位を投げ捨てるなかで、日本がそうした役割を果たすべきではないかということである。事態を放置すれば、その役割は中国が独占することになりかねない。日本は東南アジア諸国、インド、韓国、台湾、豪州それに地理的には離れているとしても欧州連合などの自由諸国との連携を緊密にして、その先頭に立てる立場にある。第1次トランプ政権下で米国が環太平洋経済連携協定(TPP)から撤退した後、それを引き継いで包括的先進的TPPの成立に導いた安倍元首相の努力を思い起こすべきだ。
第2にその具体化策として低関税連合の組成が考えられる。米国の高関税で苦しむ諸国、例えばインドなどのグローバルサウスと呼ばれる諸国を巻き込み、関税を相互に引き下げて米国外に一つの関税圏を組成するのである。すなわち、米国の関税を無視して米国を回避する道を探し、世界貿易システムの再構築に取り組むことである(注)
第3に米中の今後の動きに対する備えである。米中は目下、激しく対立し互いに100%以上の関税を課す貿易戦争の状態にあるが、これは持続不可能である。現にトランプ大統領は再三にわたって中国に対話を呼びかけたが、中国は長らく慎重姿勢を崩さなかった。これは米国の関税作戦がいずれ自壊し、米国が譲歩に迫られると見越して最適の話し合いのイミングを探っていたためとみられる。いずれにしても米中は対話を開始するはずであり、現に米中は5月に入りスイスで高官協議を開催し、相互関税の大幅引き下げで合意した。その際に二つの超大国が、それぞれの利益だけを考慮した主張を他国に押し付けてくるリスクがある。その意味で、今回の米中合意の内容を慎重に点検する必要がある。そして、これに対抗する方策としても第1、第2の施策が欠かせないであろう。
日本は1989年末のバブル崩壊以後、10年毎に経済危機に見舞われてきた。すなわち1998年のアジア通貨危機と日本独自の銀行証券危機、2008年の米国発世界的金融危機(いわゆるリーマンショック)、そして2019年に発生した新型コロナウイルス感染症に端を発する世界的経済危機である。今回のトランプ関税に起因する経済ショック、トランプ・ショックとも言うべき衝撃は今後数年のうちに、早ければ来年にも世界的経済危機を引き起こすかもしれない。それはリーマン・ショックに次ぐ、「トランプ・ショック」と呼ぶべき米国発のまぎれもない世界的経済危機の再来となろう。それを防止し、あるいは、それによるダメージを最小限に止めるためにも日本は先に述べた3つの方向性を堅持していくこと、とりわけ自由貿易の旗印を高く掲げていくことが求められる。
(注)この提言は、本年2月号の本シリーズ(「英文メディアで読む」第2次トランプ米国政権の発足)で、1月16日付ワシントン・ポストの「There’s another way to fight a trade war (貿易戦争に対抗するには別の方法がある)」と題する社説の意見を参考にしている。社説は、米関税の標的となっている国々は報復や譲歩に打って出るのではなく、アメリカ市場に代わる選択肢を見つけるべきだと以下のように論じる。
自分で自分の足をすくうよりも、中国がトランプ大統領の第1次政権時代に関税を課された際に取った行動を真似たほうがいい。中国は他国からの輸入品に対する関税を引き下げたのだ。これによりアメリカの輸出企業は不利になり、中国経済は世界から安い輸入品を引き寄せて利益を得た。2018年以降、中国の対米輸出は激減しているが、輸出全体は持ちこたえている。その教訓は明確だ。米国が暴走するなら、他の国々は互いに緊密な貿易関係を築くのが賢明なのだ。このような戦略は、トランプ大統領が手を緩める可能性さえある。米国は大きな市場だが、世界の輸入の13%を占めるにすぎない。多くの国々は、米国へのアクセスを失っても、かなり簡単に埋め合わせできるだろう。そうすれば、トランプ大統領が始めようとウズウズしている貿易戦争の無意味で自滅的な性質を納得させられるかもしれない。
§ § § § § § § § § §
(主要トピックス)
2025年
4月16日 マレーシアを訪問中の中国の習近平国家主席、アンワル首相と会談。人工知能(AI)など先端技術分野の協力拡大で合意。
17日 中国の習近平国家主席、カンボジアの首都プノンペンでフン・マネッ
ト首相と会談。米国への対応で共闘を促す。
21日 米軍とフィリピン軍、南シナ海で合同軍事演習、挙行。
中国とインドネシア両政府、北京で外相と国防相による「2プラス2」
の初会合を開催。南シナ海情勢の平和と安定で一致。海上警備機関による安全保障協力の協定に署名。
23日 台湾外交部(外務省)、ローマ教皇フランシスコの葬儀に頼総統の特使として陳建仁・元副総統が参列すると発表。バチカンは欧州で唯一、台湾と外交関係を維持。
世界最大級の自動車展示会「上海国際自動車ショー」、中国・上海市で開幕。
公明党の斉藤鉄夫代表、北京で王滬寧(ワン・フーニン)全国政治協商会議主席と会談。王氏、自由貿易体制は共通の利益につながると表明。
25日 中国共産党、中央政治局会議を開催。超長期の特別国債や地方政府によるインフラ債(専項債)の発行と活用の加速を決定。
26日 中国と中央アジア5カ国、カザフスタンのアルマトイで外相会合を開催。貿易規模の拡大で合意。
28日 石破茂首相、ベトナム首相府でファム・ミン・チン首相と会談。ベトナムの脱炭素事業に最大200億ドル(約2兆9000億円)を官民で投じると表明。
高市早苗前経済安全保障相、台湾の頼清徳(ライ・チンドォー)総統と台北市で会談。日台で供給網作りを提唱。
29日 石破茂首相、フィリピン大統領府でマルコス大統領と会談。「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」の締結に向けた協議の開始で合意。
訪中した日中友好議員連盟(会長は森山裕自民党幹事長)、中国共産党序列3位の趙楽際(ジャオ・ルォージー)政治局常務委員と会談。中国によるレアアース(希土類)の輸出管理に緩和を要請。
30日 赤沢亮正経済財政・再生相、米国と2回目の関税交渉のために訪米。
タイ中央銀行、政策金利(翌日物レポ金利)を0.25%引き下げ、
年1.75%にすると決定。米関税政策による景気悪化を織り込む
5月 1日 韓国最高裁、公職選挙法違反に問われた最大野党「共に民主党」の
李在明前代表に対する二審の無罪判決を破棄。
2日 韓国の韓悳洙(ハン・ドクス)大統領権限代行兼首相、辞任し、大統領
選への立候補を正式表明。
3日 中国海警局のヘリコプター、沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領空を侵犯。
航空自衛隊の戦闘機が緊急発進。外交ルートで中国に抗議。
シンガポールの総選挙(一院制、定数97)で与党・人民行動党(PAP)が圧勝、建国以来の政権を維持。
豪州総選挙で与党、労働党が大勝。アルバジーニー首相続投。
6日 英国とインドの両政府、自由貿易協定(FTA)の締結に合意したと発表。
7日 中国人民銀行(中央銀行)、主要政策金利を0.1%引き下げ、トランプ米政権が課す関税で打撃を受ける経済を下支え。
インド政府、シミールのパキスタン支配地域とパキスタン領内にある「テロリストの拠点」を攻撃と発表。
10日 米中両政府、トランプ関税を巡る初の閣僚級協議をスイスで開催。
韓国の与党「国民の力」、次期大統領の公認候補を金文洙(キム・ムンス)前雇用労働相から韓悳洙(ハン・ドクス)前首相に交代させる党員投票を否決。金氏が大統領候補に復活。
インド、パキスタンの両政府、領有権を争うカシミール地方を巡る軍事的衝突について即時停戦で合意。
11日 韓国の韓悳洙前首相、大統領選への出馬取りやめを発表。
12日 米中両政府、スイスで開催した閣僚級協議で100%を超える高関税の応酬を一時停止することに合意。
訪中したブラジルのルラ大統領、北京でビジネスセミナーを開催。貿易や投資拡大に向けた関係強化を推進。
13日 中国、中南米カリブ海諸国共同体(CELAC)との閣僚級会議を北京で開催。ブラジルのルラ大統領やコロンビアのペトロ大統領らが参加。
15日 アジア太平洋経済協力会議(APEC)貿易相会合、韓国・済州島で開幕。グリア米通商代表部(USTR)代表.が参加。
オーストラリアのアルバニージー首相、初の外国訪問先としてインドネシアを訪問。プラボウォ大統領と会談、安全保障での協力強化を確認。
以上
主要資料は以下の通りで、原則、電子版を使用しています。(カッコ内は邦文名) THE WALL STREET JOURNAL (ウォール・ストリート・ジャーナル)、THE FINANCIAL TIMES (フィナンシャル・タイムズ)、THE NEWYORK TIMES (ニューヨーク・タイムズ)、THE LOS ANGELES TIMES (ロサンゼルス・タイムズ)、THE WASHINGTON POST (ワシントン・ポスト)、THE GUARDIAN (ガーディアン)、BLOOMBERG・BUSINESSWEEK (ブルームバーグ・ビジネスウィーク)、TIME (タイム)、THE ECONOMIST (エコノミスト)、REUTER (ロイター通信)など。なお韓国聯合ニュースや中国人民日報の日本語版なども参考資料として参照し、各国統計数値など一部資料は本邦紙も利用。
バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教授 前田高昭
PDF版