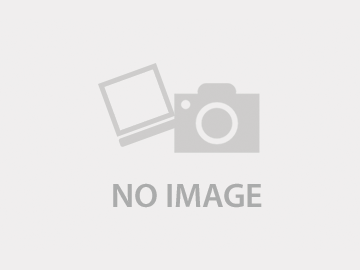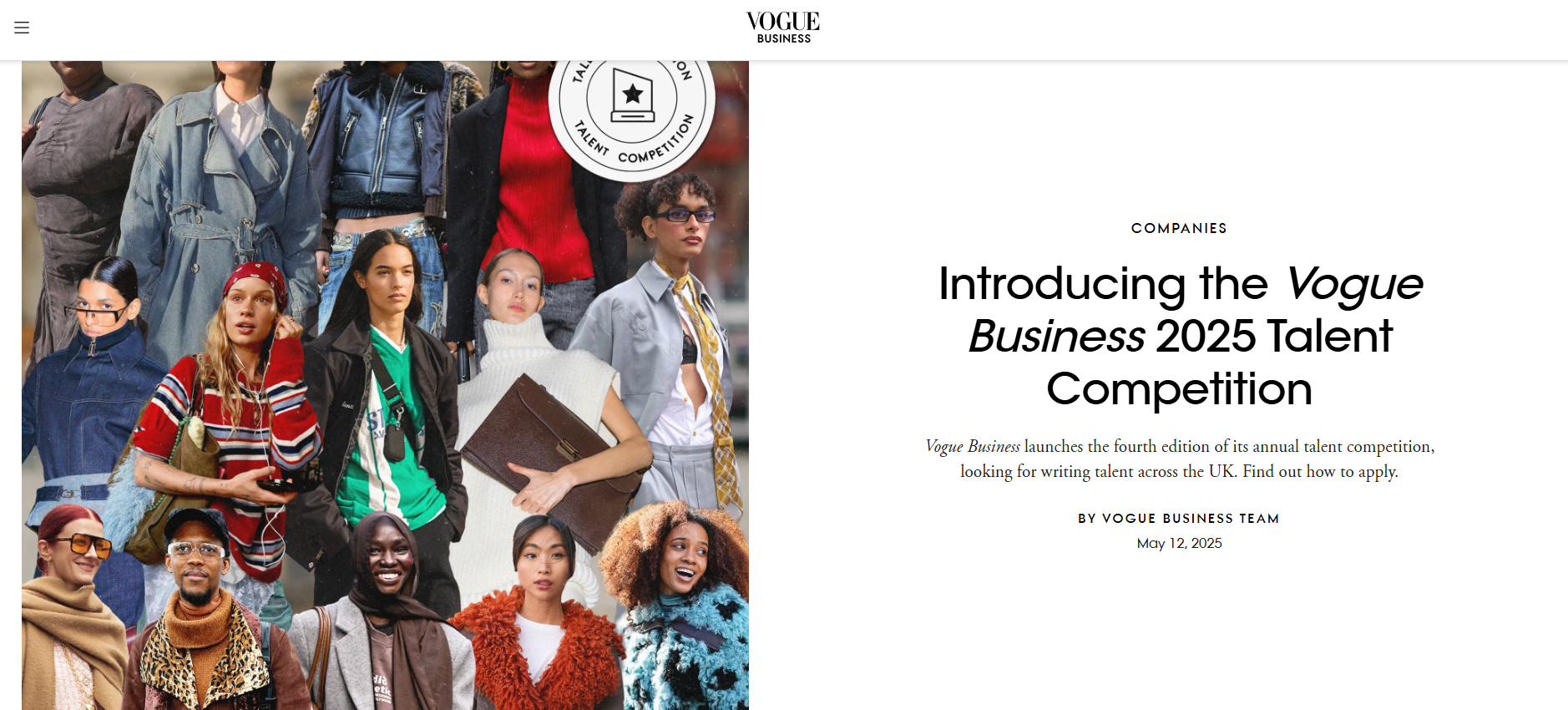戦時中、米軍の空襲や爆撃から逃れるために、都市に住む人々、とりわけ学童や女性が一時的に地方へ移り住みました。いわゆる疎開です。私も母と兄姉妹と共に父の故郷である寒村で避難生活を送ったことがあります。親しくしていた友人らとの別れは寂しかったが、その多くも別な場所に疎開していました。移住先で新しい友達と会えるかもしれないという期待もありました。しかし、新しい友人はなかなかできなかった。それどころか、想定外の正反対の出来事が起きたのです。
村の小学校に登校した初日、お前の足は細いな、といって同級生の一人が、半ズボン姿の私をいきなり蹴とばしてきたのです。当時、特に都会地では食糧事情が悪く満足に3度の食事がとれなかった。体はやせ細り、足も当然ながら細かった。私は身をかわす余裕もなく、見事に蹴られて生傷を負ってしまった。彼の友人と目される何人かの仲間も、ざまを見ろ、と言わんばかりに薄笑いを浮かべ、誰一人助けようとも、取り成そうともしなかった。それから数日後のことです。学校からの帰途、狭い山道を通り抜け、やや広い原っぱに出ると、突如、5,6人の学童がぱらぱらと姿を現した。待ち伏せをしていたのです。先日、足を蹴飛ばした悪童も白目で睨んでいる。取り囲まれた私は、今度は足を蹴られる程度ではすまないだろうと覚悟した。しかし、これも突如、一緒に疎開していた兄が藪の中から飛び出してきたのです。兄は、てめら、そんなに集まって何をしようというのだ。俺が相手になってやる、と大声で啖呵を切った。5歳程度上の兄は鼻っ柱が強く、体もひときわ大きかった。悪童連も意外な展開に度肝を抜かれたのだろう、あたふたと引き上げていきました。
低学年の小学生だった私には、なぜ彼らが悪さをするのか、理解できなかった。また、そうした疑問すら抱かなかった。悪さを受けたことも誰にも話さなかったのですが、おそらく兄だけに打ち明け、心配した兄がひそかに私を守ってくれていたのでしょう。田舎の学童連の立場になって考えると、ある日突然、都会から何人かのよそ者がどやどやと狭い村に押しかけ、近所を徘徊し、学校まで侵入してきたのです。小さい村に生まれ育ち、外の世界を未だ見聞きしていない彼らにとって、私たち兄姉妹は、まさしく目障りなよそ者だった。身なりも村の子供たちとどこか変わっており、話す言葉も村の方言と違っていた。いわば別世界からの移住者、つまり移民のような存在だったのではないか。こうした既存の秩序を乱しかねないよそ者は力で排除するのみ。それが、彼らの思いつく唯一の解決策だったのでしょう。
学童連を追い払った兄は一昨年、他界しました。91歳余だった。棺桶に収まり花束に囲まれて、安らかな顔をしていました。啖呵を切った時の芝居がかった形相を思い出しながら、私は軽く手を振って別れを告げました。
前田 高昭
金融 翻訳 ジャーナリスト
バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教授
現在、The Professional Translatorのコラムに『英文メディアを読む』と『東アジア・ニュースレター』を毎月寄稿。