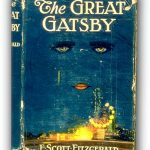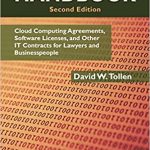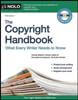第17回 海外の出版業界情報(2025年9月)
日本企業の「本読みプロジェクト」と生成AI書籍Q&Aサービス「Bookleverage」
今回は、日本で進められている新たな取り組みをご紹介します。
「Bookleverage」の概要
NTTドコモは、社員の主体的な学びを促す社内読書施策「本読みプロジェクト」を展開しています。本プロジェクトでは、選書支援、読書コミュニティの運営、成果共有イベントなどを通じて、社員の読書習慣と学習意欲を高めています。
この取り組みの一環として、日本企業Qureka(キュレカ)が開発した生成AIによる書籍Q&Aサービス「Bookleverage」を活用し、読書体験を拡張・深化させる実証実験を2025年8月下旬から10月中旬にかけて実施中です。参加者はNTTドコモの社員100〜150名で、7社の出版社が協力しています。
「Bookleverage」の価値と意義
このサービスの主な価値として、以下の3つが挙げられています。
時間と労力の削減
現代のビジネス環境では、書籍で知識を得る時間の確保が難しい状況です。要約機能により書籍の全体像を短時間で把握でき、さらに「知りたいポイント」を質問すれば、AIが該当箇所に基づいて即答します。
信頼性のある深い洞察
書籍という「閉じた情報源」に基づくため、インターネット上の不特定多数の情報ではなく、信頼できるソースから専門的で一貫性のある回答が得られます。
アウトプットを即時転用
AIの回答をそのまま思考整理や企画書作成に活用でき、学びを迅速に成果へとつなげられます。
出版業界において、既存の書籍データを活用しながら読者体験を広げ、深めるアプローチが模索されています。大規模言語モデル(LLM)の進歩によって、その実現環境が整いつつある点も重要です。本実証は「AI × 書籍」のユースケースとして大きな意義を持ちます。
海外の類似プロジェクトとの比較
海外でもAIによる書籍・文書の要約や情報検索サービスは数多く存在します。ただし、データの取り扱いは個人の裁量に委ねられ、著作権面でグレーな事例も少なくありません。
一方、「Bookleverage」では、参加出版社7社が書籍データを提供し、著者の許諾も得たうえで実証を行っています。また、企業内という限られた環境での使用となっています。このため、ユーザー側と情報提供側が互いに安心と信頼感を持つことができます。
今後の展望と課題
「Bookleverage」のようなQ&A型サービスは、読者に「本と対話する」ような体験を提供し、購読促進や継続的な読者層の形成につながる可能性を秘めています。また、書籍をデジタルツールと連動させることで、教材・研修・社内教育など新たな展開も期待されます。
ただし、次の課題への対応が不可欠です。
• 版権・著作権の明確化:出版社・著者の適切な許諾と権利処理が大前提です。
• 回答品質と正確性:AIによる誤った回答や偏りを防ぐための厳密な検証体制が求められます。
• 導入コストと運用負荷:システム構築・社内展開・継続改善にかかる負担をどう最適化するかが鍵となります。
________________________________________
NTTドコモとQurekaの取り組みは、AIと出版を融合させた新しい「読書体験」のモデルケースです。海外でも同様のサービスや研究が進む中、出版社が自社コンテンツを活かして展開する意義は大きく、読者との関わりやビジネスモデルの進化につながる転換点となる可能性があるでしょう。
参照:PR TIMES ニュースリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000165907.html
村山有紀(むらやま・ゆき)
IT・ビジネス翻訳歴10年以上。国内外の様々な場所での生活と子育ての
経験をふまえ、自分らしい発信のスタイルを模索中。