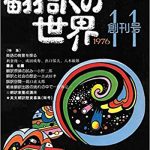2025年8月7日 第369号 World News Insight (Alumni編集室改め) 日本もまた「ヨーロッパの自死」を繰り返すのか?! バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
移民・難民政策における曖昧な現実への警鐘
2017年に世界的な話題となった一冊の本がある。英国のジャーナリスト、ダグラス・マレーによる『ヨーロッパの自死(The Strange Death of Europe)』である。本書は、イギリス、ドイツ、フランスといった西欧諸国において、移民・難民の大量流入がもたらした文化的衝突、治安の悪化、そして社会統合の失敗を克明に描き、「ヨーロッパが自らのアイデンティティを見失い、死に向かっている」と警告を発した。
この「自死」とは、単なる外部からの圧力ではなく、ヨーロッパが自らの歴史と文化を恥じ、自己否定の末に“開かれすぎた社会”を選び、結果として社会的秩序や共同体意識を失っていった過程を意味する。そして今、日本もまた、この「ヨーロッパの自死」の道を、知らず知らずのうちに歩み始めてはいないだろうか。
メルケルの寛容政策とその反省
ドイツのアンゲラ・メルケル元首相は2015年、シリア内戦や中東危機を背景に100万人を超える難民を受け入れ、「Willkommen(ようこそ)」の精神を掲げたことで、世界中の賞賛を集めた。しかしその後、ドイツ社会では移民による暴行事件、テロ未遂、文化摩擦などが相次ぎ、右派政党AfD(ドイツのための選択肢)の台頭を招く結果となった。
メルケル氏自身も引退後、「善意が必ずしも良い結果を生むとは限らない」と語り、移民政策に一定の反省を示した。彼女の行動は人道主義に基づくものであったが、国家の制度や社会のキャパシティを超えた「開放」がもたらすコストの大きさを、世界は学ばなければならない。
日本の“見て見ぬふり”政策
翻って日本を見れば、移民国家を名乗ってはいないにもかかわらず、すでに多くの外国人労働者を受け入れている。技能実習制度、特定技能制度、難民申請中の仮滞在者など、名目こそ違えど、事実上の“移民政策”が静かに進行している。
しかし、ここには重大な問題がある。それは、日本の制度が「受け入れる」と「定着させる」ことのあいだで、著しく曖昧なままであるという点だ。技能実習生は建前上“研修”の名で雇用され、3~5年で帰国を前提としているが、実態は深刻な人手不足を補う労働力にほかならない。待遇は劣悪で、失踪者は年間数千人にのぼり、不法滞在者へと“落ちていく”構造が温存されている。
さらに、近年注目を集めているのが埼玉県川口市の「クルド人問題」である。トルコから逃れてきたクルド系住民が難民認定を受けられず、仮放免状態で何年も生活し、就労も教育も保障されないまま、法のグレーゾーンに放置されている。このような人々が地域に集住し、やがて摩擦や治安不安を引き起こすのは時間の問題である。
「不法移民」問題の顕在化
2025年7月、佐賀県で外国籍の若い男性が日本人母娘を殺傷する事件が発生した。警察は「単独犯」として捜査を進めているが、報道の段階で「外国籍の容疑者」という点が強調され、SNS上では「移民=治安悪化」という短絡的な意見が飛び交った。
もちろん、犯罪に国籍は関係ない。しかしながら、移民政策が不透明なまま拡大し、不法滞在や制度の抜け道を利用した居住者が増えれば、治安リスクや摩擦が増すのは当然の帰結である。ここにこそ、制度設計の不備が生み出す「静かな危機」が存在する。
文化の継承と“壁”の必要性
ダグラス・マレーが言うように、国家とは「記憶と継承の共同体」である。開かれた国際社会という理想を追い求めるあまり、自国の文化や秩序、そして国民の安全を犠牲にしてしまえば、やがて共同体は“死”に向かっていく。
日本は、世界的に見ても稀有な均質社会を長らく保ってきた国である。だからこそ、異文化との摩擦や制度的統合の難しさを、ヨーロッパ以上に慎重に考えなければならない。開国は必要だが、無防備な開放は自殺行為である。健全な国境管理、明確な在留制度、帰還政策の整備、そして「同化」ではなく「共存」の仕組みを整えることが急務だ。
おわりに――警鐘の先にある選択
今、日本は選択の岐路に立たされている。
労働力不足を補うため、あるいは人道的配慮の名のもとに外国人を受け入れることは、国際社会の一員として避けられないだろう。しかし、その受け入れに際して、制度、教育、地域社会の備えが不十分なままでは、「ヨーロッパの自死」と同じ道をたどる可能性がある。かつてのメルケル氏のように、善意をもって政策を進めても、その先に“分断”と“衝突”が待っているならば、それは国家としての怠慢であり、歴史への背信である。日本がいま必要としているのは、「現実から目を逸らさない覚悟」と「未来の社会を見据えた制度設計」である。