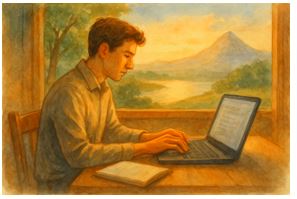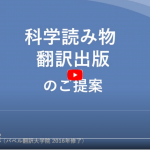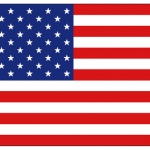東アジア・ニュースレター
海外メディアからみた東アジアと日本
第175 回

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教
中国の習主席の政策について、メディアは対内的にはソ連崩壊の主因をイデオロギーの衰退と政治支配力の喪失にあったと認識し、中国共産党による支配のいっそうの強化を、そして対外的には、中国が米国に追いつく時間を稼ぐために持続的な均衡状態の実現を夫々目指していると述べる。習の「多極化」政策はそうした時間稼ぎの戦略の一環だと指摘する。
台湾ドルが今年に入って対米ドルに対して11%以上急騰し、輸出セクターに大きな脅威となっている。要因として、多額の米国債を持つ台湾生保による大掛かりなヘッジ取引、広範な米ドル安、中央銀行の介入などが挙げられている。生保は、他通貨を介して米ドルを空売りする「プロキシ(代替)ヘッジ」も講じていたが、再び自国通貨でのヘッジに回帰し始めている。
韓国が黄海で中国との領有権争いに巻き込まれている。メディアは、台湾を巡り米中紛争が起きた場合、米軍の機動力が制限されかねない戦略的重要性を持つ問題として、東アジアにおける新たな火種となると警鐘を鳴らす。中国政府も韓国領海での示威的行動を強化するよう指示を出したとされ、黄海での中国の活動を今後注視する必要が出てきた。
北朝鮮が国連制裁回避策の一つとして、数千人のサイバー工作員を西側企業に入り込ませ、企業秘密や資金を盗み出している。グローバルなスキルを持つ技術者を訓練し、そうした技術者への需要とリモート勤務の増加を悪用し、グローバルなデジタル労働力に溶け込ませている。地域は米欧、東アジアの広範囲に及んでいる。
東南アジア関係では、ベトナムが米国と暫定貿易協定で合意した。メディアは、トランプ米政権は各国に対して対中貿易削減やサプライチェーンからの中国排除を求めており、今回の合意は同目標に向けた重要な一歩だと指摘する。またトランプ政権は東南アジア諸国に対して外国投資審査や半導体への技術輸出規制の導入を促している。
インドでは経済が世界最大の成長率を誇るなか、株式市場が急成長し株価も急騰、高リスクのオプション取引や短期取引に市民が殺到している。専門家はその状況を賭博が違法な国でのギャンブルに例えている。事実、こうした市場構造を利用して米証券会社が巨額の利益を得ている。当局はデリバティブ取引の規制強化を急いでいる。
主要紙社説・論説欄では、イスラエルとイランとの間の12日間戦争についての論調を有力メディアの社説から観察した。
§ § § § § § § § § §
北東アジア
中 国
☆ 米中冷戦に向け数十年の準備を重ねた習主席
米中は目下、トランプ関税をめぐり白熱の貿易交渉を続けているが、7月8日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナル論説記事は、習近平国家主席は米中冷戦に向け数十年の準備を重ねてきたと述べ、その戦略はソ連崩壊をどう理解するかが起点になっていると、概略以下のように論じる。筆者は、WSJ中国担当チーフコレスポンデントでWSJ Chinaニュースレターの執筆者も務めるリンリン・ウェイ氏。
米中の対立関係において、トランプ米大統領が経済的な攻撃を仕掛ける一方で、中国の習近平国家主席は「冷戦」を戦っている。習氏は長年準備してきた大がかりな戦略の下で通商交渉に臨んでいる。中国の政策顧問らによると、それは最初の冷戦でソ連が犯した過ちを習氏がどう理解しているかが起点になっている。習氏は米国の経済的・軍事的優位性が続くことを十分認識した上で、直接的な対立を避けつつ、長期にわたる包括的な競争の中で中国の立場を固守することを目指している。かつて毛沢東が「戦略相持」と呼んだものを習氏は実現しようとしている。それは米国からの圧力が制御可能で、中国が米国に追いつく時間を稼げるような、持続的な均衡状態である。
季刊誌チャイナ・リーダーシップ・モニターの編集者を務めるクレアモント・マッケナ大学のミンシン・ペイ教授は「中国にとって『戦略相持』は近い将来において最も現実的かつ望ましい結果である」と述べる。「こうした膠着(こうちゃく)状態を達成するために戦略的忍耐・リソース温存・戦術的柔軟性の全てが非常に重要となる」。中国はある意味、一種のゲリラ戦を展開している。それは紛争の非対称性に関するヘンリー・キッシンジャー氏の分析に触発されたものだ。「正規軍は勝たなければ負けだ。ゲリラは負けなければ勝ちだ」。
習氏がソ連崩壊から導き出した教訓の重要な柱の一つは、経済を巡るものだ。ソ連は経済的な賭けの全てを重工業に投じ、特にエネルギーと兵器に集中させた。一方、中国はあらゆる製品を生産することを目指し、米国の課す通商制限や技術的制限に対抗して中国経済を強化しながら、世界市場の中国製品に対する需要を喚起し続けている。もう一つの柱は地政学を巡るもので、孤立したソ連の轍(てつ)を踏まないことが目標だ。すなわち米国の同盟関係を弱体化させながら、中国が「多極化」と呼ぶ、各国が単一陣営を選ぶのではなく複数の世界の大国と関与する状態を促進することだ。この戦略のカギは、中国の軍事力増強を続ける中でも、コストのかかる米国との軍拡競争を避けることにある。中国の正式な国防予算は過去3年間、7.2%前後の安定した伸びを示している。このペースは中国の経済成長率を上回るが、国内総生産(GDP)比は1.5%を下回っている。そして決定的に重要なのは、主要な柱として社会のあらゆる側面で中国共産党の支配をさらに強化することだ。
だが習氏が有望な政治家として台頭した2000年代後半には、ソ連はすでに崩壊し、同氏の見解は変化していた。党のエリート養成機関である中央党校の校長として、ソ連崩壊を悪い手本として用い、崩壊の主な理由はイデオロギーの衰退と政治支配力の喪失だと強調した。2012年に権力を掌握した後、習氏はソ連の終焉(しゅうえん)に関するドキュメンタリーを制作させ、その中でソ連最後の指導者ミハイル・ゴルバチョフ氏を、党を見捨てた悪役として描いた。ただ、当時でさえ中国の冷戦研究はいかに自国が同様の崩壊を避けるかが中心であり、習氏はまだ中国を超大国間の対立における米国の競争相手とはみなしていなかった。
転換点となったのは、第1次トランプ政権が2018~19年に仕掛けた対中貿易戦争だった。トランプ氏のスローガン「米国を再び偉大に」は、米国の覇権維持への決意を習氏に思い知らせた。中国の顧問らによると、トランプ氏の圧力戦術に不意を突かれた習指導部は冷戦の再評価に取りかかった。新たな焦点は、米中新冷戦をどのように戦い、最終的に勝利を収めるかということだった。2020年に新型コロナウイルス流行により2国間関係がほぼ断絶した頃、習氏は新たな冷戦戦略の最初の主な要素を打ち出した。「双循環」という曖昧な名称の下、中国が必要とするものを国内で生産し、さらに外国に輸出する方針を打ち出し、外部ショック、特に米国からのショックに対する中国の防御力を高める全面的な取り組みを開始した。
トランプ氏の対中強硬姿勢を後任のバイデン政権が引き継いだことで、米国との長期戦に臨む習氏の決意はいっそう緊急性を増した。この時、中国政府は一段と強く、米国に対等な扱いを求めていくことを明確にした。その一方で、決定的に重要だったのはロシアとの関係をさらに緊密にしたことだ。2022年初め、ロシアによるウクライナ侵攻直前に中国とロシアは両国の友好関係に「限界はない」と宣言した。だが習氏は、おおむね孤立した東側陣営を形成したソ連の戦術の模倣は慎重に回避した。中国は米国と距離を置くべきかもしれないと認識しつつも、世界の他地域からは切り離されないことに留意し、グローバル経済に組み込まれた状態を特に低所得国との間で極力維持した。中国がスリランカやザンビアといった国々に略奪的な融資を行い、わなにはめることで影響力を手に入れているとの批判に対抗するため、習指導部は1兆ドル規模の巨大インフラ整備構想「一帯一路」を見直し、中国の資金の受け取り手にとっての融資の持続可能性を高めた。「中国の経済・外交政策は全て自らの態勢を米国との長期的な闘争に向けて整えることに主眼がある」。オバマ政権下で国家安全保障会議(NSC)アジア上級部長を務め、現在はジョージタウン大学教授のエバン・メデイロス氏は述べる。
顧問らによると、習氏は党機構への助言として忍耐を説いている。世界のパワーバランスは必然的に中国有利に傾くと信じているためだ。この一貫した冷静さは、米国の混乱状態やトランプ政権の絶えず変化する対中姿勢(と習氏がみなすもの)と対比させたい意図がある。ホワイトハウスはこの数カ月間中国に最大限の関税圧力を課し、世界2位の経済大国を孤立させる試みを始めたかと思えば、今や双方が譲歩する幅広い合意を目指す姿勢へと転換している。それは中国が都合よく利用でき、将来の競争に備えて条件を設定できるような環境だ。
トランプ政権は米国の対外援助機関を解体し、地政学的競争が激しさを増すさなかに中国が介入するチャンスを与えた。また米国が中国人留学生の査証(ビザ)を標的にし、政府傘下の国際放送局「ボイス・オブ・アメリカ(VOA)」のような活動を縮小する一方で、中国はソーシャルメディアで活躍する米国のインフルエンサーに無償の旅行を提供し、「クールな今の中国」を宣伝してくれることを期待する。
通商交渉に加え、中国は米政府が時間の無駄とみなす定期的な「対話」の復活も求めている。習氏にとってそれは時間稼ぎの策略だ。「彼らは強気な態度を取り、時間を引き延ばそうと心に決めている」。クレアモント・マッケナ大学のペイ氏はそう指摘した。
中国がこの戦略で勝てるかどうかは全く未知数だ。中国を大国間競争にさらに巻き込む習氏の政策は、同国の経済的苦境を悪化させる恐れがある。党による指揮統制は民間セクターの活動を圧迫し、特にあらゆる製品の生産を目指す政策はデフレの深刻化を招いている。
だがそれら全てが習氏にとっては、米国を疲弊させる長期的目標のために許容できる副作用なのかもしれない。「習氏の目標は、技術的に際立った優位性を確立し、この長期的な競争においてさらに影響力のある役割を果たすことだ」。1970年代にキッシンジャー氏の上級経済顧問を務めたロバート・ホーマッツ氏はこう述べた。
以上のように、習主席は対米貿易交渉には長年準備してきた大戦略の下で臨んでいる、と記事は論じる。米国との直接対立を避けつつ、長期にわたる包括的な競争の中で中国の立場固守を目指し、毛沢東が「戦略相持」と呼んだものを実現しようとしている。それは米国の圧力が制御可能で、中国が米国に追いつく時間を稼げるような持続的な均衡状態である。そのために戦略的忍耐・リソース温存・戦術的柔軟性が非常に重要となると記事は指摘する。まさに、今の中国の交渉姿勢を的確に表現していると言えよう。
他方、習主席はソ連崩壊から学ぼうとしている。ソ連は経済的に全てを重工業、特にエネルギーと兵器に集中させた。一方、中国は全製品生産を目指し、世界の対中製品需要を喚起し続け、「多極化」と呼ぶ、各国が複数の世界大国と関与する状態を促進している。この戦略のカギは、軍事力増強を続けながら米国との軍拡競争を避けること、そして主要な柱として社会の全側面での中国共産党の支配強化にあると指摘する。これも今の習政権の政策を言い当てているが、注目されるのは、それが「双循環」という政策で必要品を国内生産し輸出する方針を打ち出し、特に対米ショックへの防御力向上を打ち出したことであろう。またソ連崩壊の主因をイデオロギーの衰退と政治支配力の喪失にあるとしている点もまさに習政策の本質を表現している。対ロ友好関係に「限界はない」と宣言しながらも習氏は、孤立した東側陣営を形成したソ連の戦術の模倣は慎重に回避している。
中国の経済・外交政策は全て自らの態勢を米国との長期的な闘争に向けて整えることに主眼を置き、米政府が時間の無駄とみなす定期的な「対話」の復活も求めている。それは習の時間稼ぎの策略だと記事は指摘する。ただし、中国がこの戦略で勝てるかどうかは全く未知数だとし、中国を大国間競争に巻き込む習氏の政策は、その経済的苦境を悪化させる恐れがあると述べ、党による指揮統制は民間セクターの活動を圧迫し、特にあらゆる製品の生産を目指す政策はデフレの深刻化を招いているとの批判は十分留意しておく必要があろう。
要約すると、習主席の政策の核心は、対内的にはソ連崩壊の主因をイデオロギーの衰退と政治支配力の喪失にあると認識し、中国共産党による支配力をいっそう強化することにある。対外的には、中国が米国に追いつく時間を稼げるような、持続的な均衡状態の実現を目指している。「多極化」と呼ぶ、各国が複数の世界大国と関与する状態の実現は、そうした習の時間稼ぎの戦略の一環と言える。ただし、こうした内外の政策は、デフレの深刻化や民間部門の活力圧迫などの副作用があり、苦境にある中国経済をさらに悪化させる懸念があると言えよう。そうした習主席に最近、健康不安説、さらには権力基盤弱体化の噂が流れている。発端は、7月6日にブラジルで開催されたBRICSサミットを欠席したことにあるようだ。真偽不明ながら注視していきたい。
台 湾
☆ 急騰する台湾ドル
台湾の生命保険各社がドル安ヘッジを急ぐなか、台湾ドルが急伸していると7月1日付フィナンシャル・タイムズが報じる。台湾ドルは5月上旬の急伸以来、1日で最大の上昇を記録したと記事は以下のように伝える。
生命保険各社は、1973年以来最悪の年初来安値スタートを切った米ドルの大幅な下落リスクにさらされており、巨大生命保険各社と輸出セクターが通貨安による影響を食い止めようと躍起になっている。台湾ドルは7月1日の不安定な取引で2%以上跳ね上がり、対米ドルで2.5%高の29.16台湾ドルで取引を終えた。これは5月初めの急激なドル高で生命保険会社が米国資産で巨額の損失を被って以来、1日で最大の上げ幅となる。生命保険会社は170億ドルの海外資産を保有しており、そのほとんどが米国債であるため、1973年以来最悪の年明けを迎えたグリーンバックの下落で大きな為替差損をこうむるリスクにさらされている。台湾ドルは対米ドルで今年に入ってから11%以上上昇している。
BNPパリバの新興国市場金利・為替ストラテジストのチャンドレシュ・ジェイン氏は、1日の動きは、生命保険会社が台湾ドルを先物で買うことで米ドル安へのエクスポージャーをヘッジしたことが原因の可能性が高いと語る。メイバンクの外為調査責任者のサクティアンディ・スパアト氏は「生命保険会社によるヘッジに関するシナリオが現実になりつつある可能性があり、また、広範な米ドル安の要素もある」と述べた。「これらのテーマは自ずと強まっていく傾向にある性格のものだ」。台湾ドルの上昇は、多くのアナリストが中央銀行の介入と指摘したことを受けて、月曜日に2.5%安で取引を終えた後に起こった。「市場は中央銀行が介入を開始したとの疑念を抱いている」と、バークレイズの外為・新興国市場マクロストラテジスト、レモン・チャン氏は述べた。
急激な通貨高は、台湾の大規模な輸出セクターにとって脅威となる。世界銀行によると、昨年の台湾の輸出額は4,750億ドルで、GDPの約60%を占め、世界平均の29%を大幅に上回っている。先月、台湾中央銀行は、為替レートの投機をしないよう国内の輸入業者と輸出業者に警告し、「為替レートの変動を激化させ、最終的には自らの利益を損なう可能性がある」と指摘した。米ドル安は、海外資産を大量に保有する日本、韓国、シンガポールなど他のアジア諸国の通貨の上昇圧力を強めている。NPのジェイン氏は、過去2か月間、生命保険会社が韓国ウォンやシンガポールドルが台湾ドルよりも速く上昇する可能性に賭け、他通貨を介して米ドルを空売りする「プロキシ(代替)ヘッジ」を使用していたが、現在、再び自国通貨でヘッジし始めていると指摘した。「台湾ドルは、プロキシヘッジよりも速く動き続けた」とジェイン氏は語る。
アナリストらは、生命保険会社が韓国ウォンを代替ヘッジ手段として使い続けるとみており、これが通貨高につながる可能性があると述べた。ウォンは今年、米ドルに対して8%以上上昇しており、これは韓国株への資金流入と、先月の新政権選出後の財政拡大への期待によるものだ。「韓国は台湾で起きたことを繰り返す可能性があると人々は考えている」とバークレイズのチャン氏は述べる。ANZのエコノミスト兼外国為替ストラテジストのディラジ・ニム氏は、生命保険会社を含む外国人投資家は、リスクをヘッジしているものの米国資産を売却していないようだと述べ、投資家が時間の経過とともに資産を新興国市場に回すようになると予想していると付け加えた。「問題は代替手段だ」とニム氏は指摘し、「米国債の代替手段は何だろうか」と疑問を提起する。
以上のように、台湾ドルが急騰している。対米ドルで7月1日には1日で2%以上跳ね上がり、今年に入ってから11%以上上昇している。要因として、台湾の保険会社による大掛かりなヘッジ取引、広範な米ドル安、中央銀行の介入などが指摘されている。多額の米ドル建て国債を抱える生命保険会社は、韓国ウォンやシンガポールドルなど台湾ドルよりも早くかつ大幅な切り上げが予想される他通貨を介して米ドルを空売りする「プロキシ(代替)ヘッジ」という手法も講じているようだが、今は再び自国通貨でヘッジし始めているという。問題は、こうした急激な通貨高が台湾経済の約60%を占める輸出セクターに対して大きな脅威となることである。事態を注視したい。
韓 国
☆ 黄海で新たな火種
中国が黄海で領有権主張を強め、中韓の新たな火種となっていると7月7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルが報じる。記事は冒頭で、中国の黄海における一連の挑発行為の最新例を以下のように伝える。
2月のある日、韓国の調査船は中国が黄海(韓国名:西海)の中ほどに設置した異様な大型構造物に近づいた。黄海は両国の間に位置する狭い海域だ。中国海警局の大型船舶2隻と中国の小型船3隻が韓国調査船の進路を素早く遮った。中国小型船の乗組員らは、韓国の船を追い返そうと刃物を振りかざした。2時間後、韓国船は同国沿岸から約370キロに位置する謎の構造物の詳しい調査を断念し、引き返した。その構造物は、改修済みの多層式石油掘削装置の隣に水産養殖用の黄色いケージが設置され、救命ボートやヘリ発着場を備えつけたものだった。
記事はさらに次のように報じる。中国がアジア地域での自らの影響力に近隣諸国や米国が盾突くのも許さないという明確な意思を示す広範な活動を繰り広げるなか、黄海は最も新しい火種として浮上している。中国はこうした挑発と並行し、世界貿易に不可欠な海上交通路である南シナ海の全域でも領有権を主張している。中国軍の戦闘機が台湾周辺に出撃する頻度が増える一方、先月には軍事演習中、警戒監視を行う日本の海上自衛隊の哨戒機を追尾した。今年はオーストラリア沖で実弾演習も実施している。
だが黄海における摩擦は、台湾を巡って将来、米中両国の紛争が起きた場合、戦略的重要性を持つことから特に警戒されている。中国が台湾占拠を試みる場合、海軍のミサイル火力を配備するためにこの水域への自由なアクセスを求める可能性が高い。韓国の黄海沿岸から16キロ内陸に入った場所には、軍関係者2万8,500人が駐留する米軍の国外最大基地が位置する。また約800キロ離れた日本の各地には数万人の米兵が駐留している。トランプ米政権は、台湾を巡る中国との衝突が起きれば日韓両国の駐留米軍を展開する可能性があると示唆している。だが中国が黄海でプレゼンスを高めることで紛争発生時の米軍の機動力が制限されかねない。
他方、中国海軍能力の大部分と主要なミサイル発射基地は中国の黄海側に位置しており、インド太平洋地域の米軍からの攻撃には脆弱(ぜいじゃく)だ。中国はここ2、3年、米国と緊密な関係を結ぶアジア諸国への圧力を徐々にエスカレートさせている。韓国軍によると、中国軍艦による韓国領海への侵入は2017年以降3倍に増え、航空機の侵入も急増している。中国政府は3月、韓国の領海でより示威的な行動を取るよう指示を出したと、台湾治安当局の高官は現地の機密情報を引用して述べた。中国はさらに同海域で海上構造物を増設することを目指しているという。「中国は米同盟諸国の反撃能力を弱めるため、もう1カ国に圧力をかけ始めた」。米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)の中国パワープロジェクトの副責任者ブライアン・ハート氏はこう指摘する。
黄海は非常に狭く、中国と韓国の排他的経済水域(EEZ)が重なっている。そのため両国は20年余り前に「暫定措置水域(PMZ)」を設定し、違法漁業の取り締まりや海洋保護活動のルールを定めた。20年が経過した今、韓国軍によるとPMZでは中国の挑発行為がほぼ毎日起きており、2024年には中国軍艦による韓国領海への侵入が約330回確認され、17年の3倍に増えた。最近の韓国のデータでは、23年には中国の航空機が韓国の領空に130回侵入し、前年の2倍以上に増えた。中国機の多くは黄海の上空を飛行し、韓国は戦闘機を緊急発進させて対応した。中国は5月、PMZ内に航行禁止区域を設定し、韓国に衝撃を与えた。その後、中国は黄海で最新鋭航空母艦(空母)「福建」を投入した前例のない規模の軍事演習を実施。これに対し、韓国は海軍を派遣して軍事演習の監視と情報収集を行った。
黄海に点在する中国の構造物群は、韓国当局を警戒させている。2月の事案の中心になった養殖用ケージと石油掘削装置は、中韓が共同管理するPMZの西側に位置し、中国本土に近い。中国はこれらを海洋調査用だと繰り返し主張している。中国が黄海に設置した石油掘削装置は救命ボートやヘリ発着場を備えている。CSISの分析では、この掘削装置は科学的用途だけでなく軍事目的にも利用可能とされている。「これらのプラットフォームが中国のひそかなプレゼンス拡大を目的とするデュアルユース(軍民両用)ではないかとの懸念は根拠がないわけではない」と指摘する。中国が気象観測用だと主張するブイについては、韓国の国会議員であるユ・ヨンウォン氏が、ブイ群を近接して設置しているのは科学的データの収集が目的ではなく、中国がこの海域を支配するためだろうと示唆している。
中国には領有権主張のため海上に構造物を建設してきた過去がある。南シナ海の岩礁を人工島に変え、レーダーシステムや滑走路を設置している。「中国はどんなものにも必ず二重の目的を持たせる」。インド太平洋の安全保障問題に携わった米国防総省の元当局者デレク・グロスマン氏はこう話す。中韓の当局者は1日、2国間協議を開いた。韓国外務省はこの件に短く触れ、両国が黄海の状況を話し合ったと述べた。中国は黄海には言及せず、韓国と共通の課題について意見交換したと述べた。
以上のように、黄海が東アジアにおける最も新しい火種として浮上している。黄海での摩擦問題は台湾を巡って米中紛争が起きた場合、戦略的重要性を持つことから特に注目される。中国が黄海でプレゼンスを高めれば、紛争発生時の米軍の機動力が制限されかねないからである。中国政府は3月、韓国領海での示威的行動を強化するよう指示を出したとされ、中国軍艦による韓国領海への侵犯や航空機の侵入が急増している。最新鋭空母「福建」を投入し、大規模軍事演習も実施している。両国は20年余り前に暫定措置水域(PMZ)を設定し、違法漁業取り締まりや海洋保護活動のルールを定めたが、現在、中国のPMZ内挑発行為がほぼ毎日発生し、5月にはPMZ内に航行禁止区域を設定、韓国に衝撃を与えた。中国が黄海に設置した石油掘削装置は救命ボートやヘリ発着場を備え、軍事目的に利用可能とされ、領有権主張のための海上構造物建設という南シナ海での行動を再現している。東南シナ海と同様、黄海での中国の活動を今後注視する必要が出てきた。
北 朝 鮮
☆ 世界に浸透するテクノロジー従事者
北朝鮮のテクノロジー従事者が世界中の企業に浸透していると米当局が警告を発していると、7月2日付ニューヨーク・タイムズが報じる。記事によれば、北朝鮮のテクノロジー従事者は偽造や盗用した身分証明書を使用し制裁を回避しつつ、政権の資金調達に役立つ職を得ている。また、軍事技術に関連する企業秘密の窃盗も行っている。記事はさらに以下のように伝える。
国際的な制裁の重圧に苦悩する北朝鮮政府は、長年、米国や他の地域に偽造や盗用された身分証明書で偽装した技術者を配置し、必要資金を調達するため、企業に浸透させてきたと米連邦検察官は指摘する。グローバルなスキルを持った技術者への需要とリモート勤務の増加を悪用し、北朝鮮は核兵器プログラムに関する国連と米国の制裁を回避する手段を見出していると、マサチューセッツ州とジョージア州の連邦地方裁判所で開示された2件の起訴状で検察官は述べ、そのアクセスを利用して金銭と情報を盗み出したと報じる。マサチューセッツ州の連邦検察官は「北朝鮮のサイバー工作員数千人が政権によって訓練され、グローバルなデジタル労働力に溶け込むように配置されている」と語る。
6月30日、連邦捜査当局は16州で一連の措置を講じ、このスキームの摘発を目的とする行動に出た。数十の金融口座と詐欺サイトを押収し、北朝鮮の工作員が企業からリモート勤務する従業員に提供されるコンピューターにアクセスするための「ノートパソコン農場」を捜索したと、検察官は述べる。近年、北朝鮮が偽の身分を利用して制裁を回避する試みが懸念を招いている。グーグルのインテリジェンスグループが4月に発表した報告書によると、この作戦は地理的に拡大し、特に欧州を標的としている証拠があるという。昨年、米司法省とFBIは、北朝鮮の計画を支援していると疑われる米国在住者を特定する取り組みを開始した。一部の人物はその事実を知らずに協力していた可能性があるとされる。
今週、連邦検察官が提起した案件の一つでは、米国人、中国人、台湾人の市民が米国人の身分を侵害する約80件の計画に関与したとして起訴された。偽造された身分情報は、2021年から2024年にかけてリモート技術職に就くための北朝鮮労働者を支援するために使用された。これには多様な業界の数十の州にまたがる100社を超える企業がかかわっていた。検察官は、この計画が北朝鮮に約500万ドルの利益をもたらし、米企業に約300万ドルの損害と費用を発生させたとしている。また、軍事技術に関連する情報を含む機密情報が漏洩したとも述べている。被告らは、オンラインの身元調査サービスを利用して個人情報を収集、北朝鮮人が米国で働く資格があるように見せかけるための偽の身分を作成したとされている。検察当局は、数百人の個人記録を確認し、そのうち数十人の身分情報が盗まれたと述べる。偽造身分を強化するため、計画の参加者は偽の企業やウェブサイト、銀行口座を作成し、在米リモートワーカーに引き渡された企業用ノートパソコンを海外で活動する北朝鮮工作員が受け取る手配をしたと検察当局は語る。その後、当局はそうした北朝鮮工作員にノートパソコンへのリモートアクセスを許可したという。
今週開示されたジョージア州北部地区の2件目の事件では、4人の北朝鮮人が約90万ドルの暗号資産に関する窃盗と資金洗浄の罪で起訴されている。検察官によると、リモートワーカーはアラブ首長国連邦を拠点に活動し、マレーシアの偽の身分を悪用して計画を実行していた。起訴状によると被告らは暗号資産業界での就職を模索していた。1人はアトランタを拠点とする企業で開発者として採用され、もう1人はセルビアの企業で働いていた。彼らは雇用主から約100万相当の暗号資産を不正に流用し、共謀者とされる人物が資金を洗浄したと起訴状は指摘している。
米FBI、国務省、財務省は国際社会に対し2022年以降、この問題について警鐘を鳴らしてきた。主に北朝鮮、中国、ロシアで活動する工作員は海外の広範なネットワークを利用して就職先を探し、ヨーロッパと東アジアを標的としていたと警告文は述べる。米当局の警告後、北朝鮮労働者は他の地域で契約を求める傾向が強まったと、グーグル脅威インテリジェンスグループの欧州担当主要アドバイザー、ジェームズ・コリアー氏は4月報告書で指摘する。
以上のように、北朝鮮がIT技術を身に着けた数千人のサイバー工作員を使って西側企業に入り込み、企業秘密や資金を盗み出している。国連制裁を回避する新たな方策とされる。グローバルなスキルを持った技術者を訓練し、そうした技術者への需要とリモート勤務の増加を悪用し、グローバルなデジタル労働力に溶け込んでいるのである。地域的には米国、欧州、東アジアの広範囲に及び、暗号資産業界も標的にされている。こうした活動をする北朝鮮にとって身元情報が極めて貴重と考えられ、上記記事は日本との関連は報じていないが、この種の情報管理のいっそうの強化が日本としても求められよう。
東南アジアほか
ベトナム
☆ 米国と暫定貿易協定で合意―対中デカップリングの最前線に立たされたベトナム
ベトナム政府は7月2日、米国と暫定貿易協定で合意した。3日付ニューヨーク・タイムズは、トランプ米大統領は世界が中国を排除するよう求めており、その第一歩をベトナムから始めたと以下のように報じる。
ベトナムとの最初の貿易協定は、トランプ大統領が各国に中国との貿易を削減するよう迫っている様子を窺わせる。トランプ大統領は第1期の任期中、企業に中国への依存を減らすよう強制した。現在は各国にサプライチェーンから中国を排除するよう圧力をかけている。2日に発表されたベトナムと米国との暫定貿易協定は、その目標に向けた最も重要な一歩だ。詳細は少ないが、ベトナムの対米輸出には20%の関税が課せられる。これはトランプ氏が脅かした税率よりもはるかに低い。しかし注目すべきは、ベトナムから輸出される「転送(積み替え)貨物」——他の国で製造されベトナムを経由しただけの商品——には40%の関税が課せられる点だ。この措置は、ベトナムや近隣諸国を利用して米国関税を回避している中国を狙い撃ちしており、水曜日に発効する高額関税を迂回するため、他の東南アジア諸国との貿易協定でも採用される可能性がある。
トランプ政権の貿易交渉担当者は、インドネシアなど他の輸出依存型隣国に対し、サプライチェーン内の中国製品比率を削減するよう圧力をかけている。彼らはタイ政府に対しても外国からの投資を審査するよう求めており、これは中国企業の進出阻止が狙いである。さらに一部の国に対し、半導体などの技術輸出規制を検討するよう圧力をかけている。地政学コンサルティング会社APAC Advisorsの最高経営責任者(CEO)スティーブ・オクン氏は、「トランプ政権は『米国と貿易パートナーとなるなら、戦略的なデカップリングが必要だ』と主張している。問題は、各国がそれに同意するかどうかだ」。米国の中国封じ込め策は、中国にとって戦略的に重要な地域であり、既に中国のグローバル貿易と製造業の支配の最前線にある東南アジア諸国が直面している脆弱性をさらに高めている。木曜日、中国の商務省は米国とベトナムの合意について「評価を行っている」と表明し、中国利益を損なう合意には「断固反対」し、「正当な権利と利益を守るための対抗措置を講じる」と語った。
ベトナムは米国との貿易交渉に臨むにあたり、全てを失うリスクを抱えていた。トランプ氏は同国製品に46%の輸入関税を課すと脅しをかけ、靴、衣料品、電子機器など中国の代替地として頼りにしてきた産業に衝撃を与えた。その関税脅威による不確実性がベトナム企業に重くのしかかっていた。米国にほぼすべての製品を輸出する家庭用香料会社の幹部、トラン・クアン氏は「20%の関税は誰にとっても最良のシナリオではない。しかし、それほど悪いものでもない」と語る。同氏は、転送輸入に対するより高い関税を支持すると付け加え、これは中国企業がベトナムに投資して関税を回避し、ベトナム企業に不公正な競争を強いている状況に対抗する助けになると説明した。多くの小さな中国企業がベトナムに来て、製品にラベルを貼り替えてから米国に輸出している」と述べる。
中国企業による投資と貿易はベトナムと地域の経済成長を支えてきたが、東南アジアは中国からの大量の製品流入により国内企業が倒産する危機にも直面している。近年、中国経済が不動産危機に直面するなか、中国政府は工場などへの補助金を拡大し、世界的な中国製品の輸出急増を招いた。とはいえ、中国とのデカップリングは東南アジア諸国に連鎖反応を引き起こすリスクがある。専門家は米国とベトナムの合意に関する情報がまだ十分に公開されていないため、その影響を完全に評価することは不可能だと指摘している。例えば、転送とは中国で製造された製品を指す可能性があり、またベトナムで製造されたが一定割合の中国製部品を含む製品も含まれる可能性がある。しかし、中国製部品の制限が厳格になれば、米国企業はベトナムからの生産移転を検討する可能性があると、米国靴卸売・小売協会(FDRA)の会長であるマット・プリエスト氏は指摘する。「制限が過度に負担が大きかったり困難だったりすれば、米企業はベトナムでの調達拡大の機会を活用しないだろう。価格競争力があれば中国に戻ってしまう可能性もある」。
ベトナムとの合意は米企業にとって不確実性を残した。かれらは、他の東南アジア諸国がトランプ政権との潜在的な合意で中国に対する関税や制限措置にどう対応するかをみたいのである。また、輸出製品における中国製部品の割合に関する制限は、これまで輸出をこれほど厳格に審査したことがない現地の税関当局に負担を強いることになり、その効果に疑問が呈されている。一部の国では、米国向けの全く異なるサプライチェーンを構築する可能性も議論されている。米政府は、中国経済と深く統合された一部の国を中国の懐に追いやるリスクも抱えている。多くのアジア諸国政府は、中国企業を孤立させる合意に対し、中国がどのように反応するかを懸念している。中国は製品ボイコットや近隣国が依存する重要な鉱物の制限など、攻撃的な報復措置を講じる用意があることを示してきている。また、南シナ海での緊張をエスカレートさせるという選択もあり、同海域で広く軍事的主張を強化している。「政治的には2つの超大国の間で慎重に歩む必要がある」と、タイのタマサート大学国際ビジネス学部のパヴィダ・パナノン教授は語る。「中国は単なる商品の輸入国ではなく、投資の源であり輸出先としても重要な経済大国だ」
東南アジア諸国は最近数週間、転送貿易の監視と執行を強化する独自の措置を講じており、これらは米国との貿易協定で合意する可能性のある内容の一端を示している。タイでは、トランプ氏が36%の関税を脅かしたため、政府は転送目的の輸出を厳格に審査する措置により、米国への輸出が$150億減少する可能性があると推計している。これは昨年タイの対米貿易黒字の3分の1に相当する。また、中国企業が自社のサプライヤーをタイに誘致するために多額の投資を行っている電気自動車など、特定の分野における外国投資をさらに厳格に審査するとも約束している。マレーシアとインドネシアの当局は、米国向け輸出の正確な書類作成を確保するため、輸出規則を強化した。両国はまた、輸出証明書発行の権限を中央集権化している。
貿易協定が締結される前から、トランプ政権は地域が中国をどう見るかを再構築している。「目的は中国を排除することだ」と、貿易政策を専門とするヒンリッヒ財団のデボラ・エルムス氏は述べる。しかし、ベトナムのような国にとって、米国の要望に従うことは地政学的にリスクを伴う。「米国、中国、そして自国の企業がどう反応するかを予測するのは、あらゆる面で賭けとなる」とエルムズ氏は述べる。
以上のように、トランプ米政権は各国に対して中国との貿易を削減し、サプライチェーンから排除するよう圧力をかけており、今回のベトナムと米国との暫定貿易協定は同目標に向けた最も重要な一歩だと記事は指摘する。特にインドネシアやタイなどの東南アジア諸国に対して、外国からの投資への審査や半導体などへの技術輸出規制を導入するよう圧力をかけ、中国のグローバル貿易と製造業の支配の最前線にある東南アジア諸国を窮地に立たせている。これら各国は、中国企業を孤立させる合意に対し、中国がどのように反応するかを懸念している。ベトナムについては、中国製部品の制限が厳格になれば、米国企業がベトナムから生産移転を検討するかもしれないと指摘されており、大きなリスクにさらされていると言えよう。その反面、ベトナム企業からは、中国企業がベトナムに投資して関税を回避し、ベトナム企業に不公正な競争を強いている状況に対抗する助けになるとの見方も上がっており注目される。今後の動きとしては、米国向けの全く異なるサプライチェーン構築の可能性や米政府の中国排除の試みに対する中国の反発や対応を注視したい。
インド
☆ デリバティブ取引の規制を強化する当局
米証券会社ジェーン・ストリート・グループがインド特有の市場構造を利用して巨額の利益を上げたというニュースがインド証券市場を揺るがしている。この事件について、7月8日付ブルームバーグはインドでは現物株市場に比べてデリバティブの取引規模が300倍以上にも達しており、背景にはオプション取引を好む個人投資家の圧倒的な存在感があると概略以下のように報じる。
ジェーン・ストリートの取引戦略は、他の市場ではここまでうまく機能しなかった可能性が高い。ジェーン・ストリート事件を受けてインド証券取引委員会(以下、SEBI)の当局者は、デリバティブ取引の規制強化を検討中で、ジェーン・ストリートが他のインドの株価指数で行った取引を調査している。SEBIによれば、ジェーン・ストリートの戦略は市場を自社に有利な方向へ積極的に動かすというものだった。同社は24年1月17日、午前中にインドを代表する株価指数であるインドニフティ50指数の現物株と先物を買い入れて市場を下支えする一方で、大量のオプションに対して弱気ポジションを取っていた。後場になって同社は現物と先物市場でのポジションを一斉に解消したのである。これにより株価指数は下落し、保有していた弱気のオプションによって利益を得たとされる。
規制当局によれば、ジェーン・ストリートの戦略が機能したのはインド特有の市場構造に要因があった。具体的には、現物市場の参加者が少なく流動性が低い一方で、デリバティブ市場には高い流動性があり、短期的な株価指数の動きに反応する個人投資家が多く、さらにオプション取引では極めて高いレバレッジが可能だったことが挙げられている。SEBIの文書に記載された一例では、株価が100ルピーの銘柄について、権利行使価格100ルピーのコールオプション2株分がわずか1ルピーで購入可能だったという。実質的に100倍のレバレッジをかけることができた。こうした仕組みにより、短期的な利益を狙う一般的な個人投資家にとって、オプション取引は非常に魅力的な手段となっていた。
上記のように、当局はデリバティブ取引の規制強化と米証券会社の取り締まりに動き出したが、SEBIは既に昨年、問題を察知し対策に乗り出していた。この間の動きについて昨年10月2日付フィナンシャル・タイムズは次のように伝えている。資本市場規制当局は、同国の急成長する株式市場で高リスクのオプション取引や短期取引に殺到する数百万人の若年層小口投資家の熱狂を抑制するため、デリバティブ取引の参入障壁を引き上げた。インド証券取引委員会(SEBI)は火曜日、指数デリバティブの最低契約サイズを約3倍に引き上げ、少なくとも150万ルピー(約1万8,000ドル)に設定するなどの厳格な措置を講じた。また、11月から各取引所での週次オプション契約の取引可能数を1件に削減した。
インドの株式市場は近年、同国が世界最大の成長率を誇る経済大国となったことで急騰している。中間層の世帯数が増加し、国内株式への投資が急増するなか、アナリストはデリバティブ取引への熱狂的な関心を賭博が違法な国でのギャンブルに例えている。「インドでは株式ブームが拡大している」と、ムンバイのウエルスミルズ証券の株式戦略ディレクター、クランティ・バティニ氏は語る。問題は「情報不足で教育を受けていない投資家がこの小売投機熱の餌食になっている点だ。これが規制当局と財務省の懸念だ」と付け加えた。ムンバイを拠点とするアクシス・ミューチュアル・ファンドの調査によると、インドのアクティブなデリバティブ取引者の数は、新型コロナウイルスパンデミック前の50万人未満から、昨年400万人に急増した。その大半は国内の地方都市在住で40歳未満の若年層だった。この傾向は、インドの基準指数Nifty 50のオプションの想定価値がS&P 500を上回り、米証券会社ジェーン・ストリートが昨年同国のオプション市場で10億ドルの利益を上げたとの報道を受けて、世界的な注目を集めている。
以上のように、インドの株式市場は近年、同国が世界最大の成長率を誇る経済大国となったことで急成長し、株価も急騰するなか、株式市場で高リスクのオプション取引や短期取引に数百万人の若年層や小口投資家が殺到している。インドのアクティブなデリバティブ取引者の数は、新型コロナウイルスパンデミック前の50万人未満から、昨年400万人に急増しており、専門家はこうした状況を賭博が違法な国でのギャンブルに例えている。事実、こうした市場構造を利用して米証券会社が巨額の利益を得ている。当局は、熱狂する市場を抑制するためデリバティブ取引の参入障壁を引き上げるなど規制を強化しているが果たして抑え込めるのか。注視していく必要がありそうだ。
§ § § § § § § § § §
主要紙の社説・論説から
イスラエル・イラン12日間戦争について
イスラエルは去る6月13日、イランに対して突然、軍事攻撃を仕掛けた。不意を衝かれたイランは核ミサイル施設の損壊や軍首脳の犠牲など多大な物的人的被害を受けた。米国政府の対応が注目されるなか、トランプ大統領は6月22日、地中深くに建設されたイラン核施設に対する特殊爆弾による空爆に踏み切った。これを契機に6月25日、イスラエル・イラン間に停戦の合意が成立する。今回は、イスラエルによるイラン奇襲から停戦の合意に至る12日間の動きに関する主要メディアの論調を社説から観察した。以下は、その要約で末尾の「結び」は筆者の論評である。
上述のように、イスラエル・イラン紛争に対する米政府の動きが注目されるなか、6月16日付ワシントン・ポストは「Bomb Iran? Trump needs to think about what happens next (米国はイランを爆撃か、トランプ大統領は次に何が起こるかをよく考える必要がある)」と題する社説で、ネタニヤフ氏がテヘランの体制変革を迫る場合、米国は慎重に対応しなければならないと、以下のように論じる。
暴力の日々が続き、イスラエルとイランは激化する紛争に陥っているようにみえる。イスラエルの計画は、米国がどのように関与するかをめぐって依然として不透明なままだ。少なくとも現時点では、米国とイスラエルは異なる目標を持っているようだ。トランプ大統領は、イランに対して交渉の再開とイスラエルの激しい爆撃を終わらせるために核開発計画縮小に向け早急に合意するよう強く求めている。この爆撃により、イランの軍事指導部はすでに壊滅し、核施設は損傷を受け、エネルギー施設も打撃を受けている。しかし、イスラエルのネタニヤフ首相は、イラン指導部が核交渉の再開を約束したとしても攻撃を一時停止する意向を公に表明していない。
ネタニヤフ首相は攻撃をイラン全土に拡大し、空港、製造工場、地元警察署も対象とした空爆を継続する決意を固めているようだ。この作戦拡大は、イランの核プログラム妨害やイスラエルの町や都市向けの弾道ミサイル攻撃の停止という目的を超えている。これらの事実は、ネタニヤフの真の目的——同氏が公然と述べるかどうかに関わらず、そして達成に近いところまで来ている——が、イランを徹底的に弱体化し、そのイスラム共和国の崩壊を早めることにあるのを示している。ネタニヤフは、過去1年半にわたってイスラエル軍がイランの代理勢力を壊滅させたことから、目標達成が可能だと考えているようだ。また、シリアの独裁者バシャール・アル=アサドの崩壊と、より穏健な政権への交代により、イランは地域で最も強力で最も激しくイスラエルに敵対する政権として孤立している。任務を完了する誘惑は大きいに違いない。しかし、イスラエルには強化コンクリートで建設され、山腹に数百フィート埋められたとみられるイランの最も防護された核濃縮施設フォードウを破壊するのは困難である。
米国は、その任務を遂行できるバンカー・バスター爆弾を保有しているが、イスラエルにはその爆弾もそれを運ぶB-2ステルス爆撃機もない。米国はイスラエルがフォードウ施設を破壊するのを支援するため、米軍のB-2爆撃機にバンカー・バスターを搭載して派遣する可能性はある。しかし、それはイランとの戦争への直接参加を意味する。トランプ大統領は、米国を中東の終わりのない紛争に再度巻き込むことを避けているとみられるが、支持者の中にある2つの対立する派閥の間で揺れ動いている。イスラエル支持でイラン反対のタカ派は、米国がイスラエルの爆撃キャンペーンに参加すべきだと要求し、一方、孤立主義の「アメリカ第一」派は、イスラエルがこの戦争を始めたのだから放置すべきだと主張している。イスラエルはトランプに軍事介入を要請している。
驚くべきことに、イランはこれまで中東の米軍基地や資産に対して弾道ミサイルを発射していない。イラン指導部は、ホワイトハウスに介入する口実を与えないよう慎重に測っているとみられる。また、トランプが繰り返し「米国はイスラエルの空爆キャンペーンを支援していない」と主張したことが、イランの行動抑制を説得した可能性もある。米国は、いずれにせよ関与を余儀なくされている。イスラエルの主要な国際パートナーとして、米国はイスラエルの指導者に対して影響力を持っている。米国はほぼ確実に、イスラエルがイランのミサイル攻撃を回避するのを支援するだろう。
しかし、イランの体制変革を目的とする攻撃に介入することは、最近の歴史を教訓として警戒すべきだ。2011年の米欧の空爆キャンペーンでリビアのムアンマル・カダフィ政権を倒した結果、統治派閥が対立する国家が残されるという失敗を犯した。またアフガニスタンでの悲惨な20年間の経験は、空爆で政権を倒すのは容易だが、正当で穏健な代替政権の確立ははるかに困難なことを示した。ネタニヤフの目標がイランの体制変革であるなら、米国はイスラエル首相にそれがどのように実現可能か、そしてその後何が起こるかを説明するよう迫らなければならない——そしてトランプは、イランが過激主義と地域不安定を招くような無政府状態に陥るのを防ぐために自身が何をすべきかを自問しなければならない。現時点では、緊急の新たな核交渉を含む他の結果も可能性として残っている。だが、その窓は急速に閉ざされる可能性がある。
しかし、上記のようなワシントン・ポスト社説に挑戦するようにトランプ大統領はイランへの攻撃に踏み切った。この決断に対して早速、6月23日付フィナンシャル・タイムズは「Trump’s step into the dark (トランプの暗闇への一歩)」と題する社説で、イランにおけるアメリカの賭けは、世界をより危険な場所にすると以下のように論じる。
週末にイラン核施設への攻撃を決定したドナルド・トランプは、米国を中東での大規模な戦争に巻き込んだ。この攻撃を戦争ではなく限定的な軍事作戦と捉えて成功を誇張しても事実が変わるわけではない。米国はイスラエルの対イラン戦争に加わったのだ。米国の関与により、イラン政府は今や行動を起こすか将来行動を起こすかに関わらず、湾岸のエネルギー資産や中東全域における米軍の基地、艦艇を攻撃する正当な理由を得た。またネタニヤフ首相のイランの体制変革を求めていると思われる動きに欧米諸国を巻き込むリスクもある。トランプと米国は、危険な暗闇への一歩を踏み出した。西側世界は、イランによる核兵器開発の阻止と地域内の過激派代理組織への支援停止を求める点で正しく団結している。しかし、トランプによる数週間の外交は、軍事行動を正当化する信頼できるプロセスとは到底言えない。米国がイランのフォードウ、ナタンズ、イスファハンの施設を爆撃したことで、確実に重大な損害が生じているが、イランが未だ核能力を一部維持し、あるいは高濃縮ウランの備蓄を隠匿していた場合、核兵器の開発を急ぎ抑止力を確立しようとするかもしれないのだ。
イラン政府がどのように対応するかは、まだ不明だ。イスラエルとの戦争は、イスラム政権の脆弱性を防御面でも攻撃面でも暴露した。イランは、地域内の米資産を標的とすれば、米国による更なる攻撃を招くことは理解している。またイスラエルへの攻撃を抑制しても次の標的が体制自身となる戦争を延長するだけなのだ。報復の衝動は強くてもイランには良い選択肢は残されていない。指導部は後退し、エスカレーションを避けるべきだ。原油価格は急騰する見込みである。投資家は、イランによるホルムズ海峡封鎖の可能性について懸念を深めるだろう。同海峡は世界の海上原油貿易の四分の一が通過する要衝である。ただし、政権の封鎖を実行する能力と意思は不明確だ。
しかし、何が起こっても紛争を巡る不確実性が世界経済を阻害するだろう。終わりが見えなくなった作戦の拡大リスクは大幅に高まっている。イスラエルと米国の攻撃は、イスラム政権の崩壊につながる一連の出来事を引き起こす可能性はあるが、米国、イスラエル、西欧にとって受け入れやすい政権に置き換わる保証はない。むしろ真空状態が生じる可能性がある。イランの隣国が懸念するのは、9,000万人の多民族国家が崩壊し、分裂するリスクである。これは、2003年の米軍主導の侵攻後にイラクで起きた失敗の再現となるかもしれない。
米軍による攻撃のカウントダウンは、トランプ大統領が最初の任期中にイラン核合意から離脱した決定から始まっている。この合意はイランの核活動を大幅に制限していた。不完全な合意だったがイランは合意を遵守していたのだ。イランの核野心を制限するための外交努力は常に最良の選択肢だった。トランプ政権は、長年イランとの外交努力に反対してきたネタニヤフ首相に外交を無視させて、トランプが10年間望んできた戦争に米国を引きずり込んだのだ。制約のないイスラエルも地域における不安定要因であることが、過去数週間で示されたのである。米大統領は、イランの弱さとイスラエルの成功がイランを攻撃する独自の機会を提供したと判断した。おそらくトランプ氏は、その脅迫を実行に移さないとの批判に動揺し、またウクライナと中東での和平努力の失敗に挫折し、ネタニヤフのミッションと結びつくことで迅速な勝利を見出したのだ。しかし、そのことは自身の孤立主義的な支持基盤を驚愕させ、中東をさらに不安定と危機に陥れる大きな賭けとなったのだ。
さらに6月22日付エコノミスト誌は、「America’s attack (米国の攻撃)」と題する社説で、中東の大惨事をどのように防ぐかと問題提起し、トランプ氏はイランに爆弾、怒りと屈辱ではなく、それらを超えたものを提供しなければならないと、以下のように論じる。
トランプ大統領は、米国を外国との戦争から遠ざけるために選出された。しかし米軍は6月22日、イスラエルによるイランへの攻撃に加わり、3つの核施設を攻撃した。大統領の現在の課題は、イラン指導者に対して地域を破滅的な状況に陥れるような事態の悪化の回避と核兵器の入手という考えの放棄を迫り説得することである。どちらも容易なことではない。爆撃作戦は3つの施設に深刻な損害を与えたようだが、大統領は損害の程度を確信できていない。イラン自身もまだその全容を評価する時間がないからだ。
イランの報復を懸念するのは当然である。だからこそ、本誌は米国が行動に急いだのは誤った選択だと主張するのである。我々は、この局面における一得一失の関係(トレードオフ)は全体として失うものが大きくなると懸念している。空爆はイランの核プログラムを遅らせるかもしれないが不確実だ。またイランと代理勢力またはテロ組織が米軍兵士や民間人を殺害し、湾岸諸国を恐怖に陥れ、ホルムズ海峡をタンカーにとって危険な状態におきエネルギー価格を急騰させるなどのリスクがある。トランプ氏が急いで行動した以上、地域が制御不能に陥る可能性を最小限に抑える必要がある。幸い攻撃自体はまさにその目的を果たすように設計されているようだ。過去9日間、イスラエルは政治的、軍事的、経済的に攻勢を強め、核関連の標的を幅広く攻撃し、体制変革を誘発する可能性を示唆している。一方、米国は核施設にのみ焦点を当て、その一部はイスラエル空軍では到達不能な場所と考えられている。トランプ大統領は、少なくともイランが自制を示す限り、体制の転覆を試みるつもりはないことを明確にしている。
トランプ氏は、早急に外交に転換すべきだ。大統領は演説の中で、「今こそ平和のための時である」と宣言した。その言葉通りであれば、イランが米軍基地やアラブ諸国への報復ミサイル攻撃を行わないという代替案を直ちに提示すべきである。つまり、ピート・ヘグセス国防長官の呼びかけに従い、イランに代替計画案に関する協議への復帰を求めるべきである。イランに濃縮ウランの備蓄放棄と、徹底的な国際査察の受け入れを要求しつつ、イランがある程度の濃縮能力を持つことをおそらく国外で活動する地域コンソーシアムの一部として容認するという方針をトランプ氏が打ち出せば、協議はより実現しやすくなるだろう。即時に交渉を提案すれば、イランは面目を保つための攻撃に限定する可能性がある。その場合、トランプ氏はそれらを無視し、イランを交渉の場に引き出すべきだ。
最後に、トランプ氏は中東を継続的な戦争のパターンから脱却させるための取り組みを推進すべきである。空爆により、彼はアラブの同盟国を深く動揺させた。5月の湾岸訪問後、彼らはトランプ氏がイスラエルを抑制しつつイランとの交渉を続けると信じていた。イスラエルが米国の後ろ盾を得てイランを繰り返し攻撃する可能性は、繁栄を通じて平和を実現する地域のビジョンにとって重大な脅威となるのだ。
こうしたなか、イランとイスラエルは6月25日、停戦に向けた合意に達する。これについて6月25日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは、「 (日本版記事:【社説】トランプ氏と「12日間戦争)」と題する社説で、イランの弱々しい報復はハメネイ体制が受けたダメージの大きさ示すと、概略以下のように論評する。
イランは23日、カタールにいる米軍に向けて弾道ミサイル14発を発射するとともに米国がイランの3つの核施設を攻撃したことへの報復として「米空軍基地を破壊」したと、いつものやり方で主張した。しかし、イランの国力と決意を示す攻撃としては失敗した。トランプ米大統領はこれを「非常に弱い反応」とあざ笑い、「(イランは)自分たちの『システム』でできることをやり尽くした」と述べた。だが、われわれはトランプ氏が「第2のイラク戦争」を提案しているとは考えない。同氏は23日、地上侵攻でも占領でもなく、「平和と調和」を望んでいると投稿した。イランが停戦するなら、トランプ氏は「イスラエルにも同じことをするよう促す」だろう。そして案の定、トランプ氏は後に、イスラエルとイランが24時間以内に「完全かつ全面的な停戦」で合意し、同氏が「12日間戦争」と呼ぶものを終結させると発表した。報道によると、イスラエルはイランが攻撃を停止すれば停戦に合意する意向でロイターはイランも同様だと報じた。公平な結論は、イランが降伏しわずか12日間の戦争でもイスラエルと米国にとって大きな成果があったということだ。
イランは核濃縮・兵器化施設、主要な軍事司令官と核科学者、そしてミサイル生産・発射能力の大部分を失ったとみられる。イスラエルはもっと時間をかけてより多くの標的を攻撃したかったかもしれないが、自国の都市を守ることも考慮する必要がある。ネタニヤフ首相もイランとその代理勢力によってイスラエルの存続が脅かされてきた現状に戻るつもりがないことを明確にしている。イスラエルは、イランがミサイルや核能力の再建に固執するなら、再び同国を攻撃する構えであることを示唆している。先に殺害された革命防衛隊の精鋭「コッズ部隊」のカセム・ソレイマニ司令官が使ってきたのと同様の殺人犯的手法を取り続けられるとイランが考えているならば、イスラエルは今後、先制攻撃の道を選ぶだろう。
残る疑問は、イランの現体制がこの先どうなるかだ。独裁主義者は崩壊の瞬間まで揺るぎなくみえるものだ。軍事的に屈辱を受けたハメネイ師は、民衆蜂起の餌食になる可能性がある。体制幹部や軍幹部によるクーデターで失脚する可能性もある。これら幹部は、ハメネイ師の政策が国を崩壊させつつあると認識している。いずれの場合も、ハメネイ師の後継者が米国の利益および「平和と調和」に今より悪い影響をもたらすとは到底思えない。トランプ氏に関しては、停戦と「12日間戦争」という表現は、「イラクやアフガニスタンの二の舞いにはならない」と右派の孤立主義者を安心させる方法だ。トランプ氏がイランに一息つく余裕を与え、同国がひそかに保管している濃縮ウランの保持とその後の再武装を許せば、この戦争の成果を無駄にすることになる。だがこの2週間は、より平和な中東の実現に向けた希少な機会を生み出している。
結び:以上のような主要メディアの論調を次の4つの観点からまとめてみる。第1にイスラエルによるイラン攻撃の目的、第2に米国参戦の意図、第3にそれらの目的や意図の達成状況、第4に今後の中東情勢の展望という観点である。
第1のイスラエルによるイラン攻撃の目的について、メディアはイランの体制崩壊を目的とするとの見方でほぼ一致している。ネタニヤフ首相は攻撃をイラン全土に拡大し、空港、製造工場、地元警察署も対象とした空爆継続を決意しており、作戦拡大は、イランの核プログラム妨害やイスラエル向けの弾道ミサイル攻撃阻止という目的を超えていると指摘。イスラエルの真の目的はイランの徹底的弱体化とイスラム共和国の崩壊加速にあると分析する。
確かにイスラエルは既にイランの代理勢力を壊滅させている。代理勢力とは、パレスチナにおけるハマス、レバノンにおけるヒズボラ、そしてイエーメンにおけるシーア派などの軍事組織である。反イスラエルの一方の勢力だったシリアのアサド政権は昨年崩壊し、イランはイスラエルにとって残る最強の敵対勢力となったが、地域で既に孤立している。今回の中東動乱が昨年のパレスチナにおけるハマスのイスラエル攻撃に端を発し、レバノンにおけるヒズボラの動きを含めて、全てイランの支援を受けていることを考えれば、動乱の根源となるイランの存在そのもののせん滅、すなわち、イランの体制変革がイスラエルの最終目標となっていたのは当然と考えられる。イランの体制変革はイスラエルにとってその存亡をかけた不可欠かつ不可避の帰結と言える。
第2の米国参戦の意図について、メディアは米国はイスラエルとは異なる目標を持っているとし、トランプ大統領がイランに対して交渉の再開と核開発計画縮小に合意するよう迫っていると伝える。その一方で米国は、イランの防護された核濃縮施設フォードウを破壊できるバンカー・バスター爆弾とそれを運ぶB-2ステルス爆撃機を保有している。イスラエルにはその爆弾も輸送手段もないため、米国がバンカー・バスターを搭載した爆撃機を派遣する可能性があるとメディアは指摘する。トランプ大統領は「米国はイスラエルの空爆キャンペーンを支援していない」と繰り返し主張しているが、支持者の中にある2つの対立する派閥、すなわち、イスラエルの爆撃キャンペーンへの参加を要求するタカ派とイスラエルを放置すべきだと主張する「アメリカ第一」主義の孤立派の間で揺れ動いていると述べ、リビアのカダフィ政権転覆やアフガニスタンでの悲惨な体験、米軍主導のイラク侵攻後に起きた失敗例などを挙げ、イランの体制変革を目的とする攻撃への介入は歴史を教訓として慎重に対処すべきだと主張する。そのうえでメディアは、ネタニヤフの目標がイランの体制変革であるなら、それがどのように実現可能か、また、その後何が起こるかについて説明を迫り、トランプ自身もイランが過激主義と地域を不安定化する無政府状態に陥るのを防ぐために何をするかを自問すべきだと提言する。
確かに軍事力で政権を倒すのは簡単だが、正当で穏健な代替政権の確立はきわめて困難で過激主義を生み出し、地域を不安定化させる恐れがある。そうした懸念のなかでトランプ大統領はイランへの攻撃に踏み切った。メディアがこの行動を「暗闇への一歩」と評したのは当然であろう。攻撃は、湾岸のエネルギー資産や中東全域における米軍の基地や艦艇のイランによる攻撃を正当化し、欧米諸国を戦乱に巻き込むリスクを惹起させたのである。攻撃を戦争でなく限定的軍事作戦と表現しても事実は変わらない。イランが重大な損害を受けたとしても未だ核能力を維持し、高濃縮ウランの備蓄を隠匿している可能性も否定できない。ホルムズ海峡封鎖によるエネルギー価格の上昇や世界市場の混乱懸念、紛争を巡る不確実性による世界経済へのダメージ、そしてイスラム政権崩壊が引き起こす真空状態の出現などのリスクもある。体制変革によって米国、イスラエル、西欧にとって受け入れやすい政権が誕生する保証はないのである。
メディアはまた、米軍によるイラン攻撃のカウントダウンは、トランプ大統領が最初の任期中にイラン核合意から離脱した決定から始まったとし、イランの核野心を制限するための外交努力は常に最良の選択肢だったとトランプ決断を非難する。しかも外交を無視し制約を受けないイスラエルが地域の不安定要因となったと断罪する。そのうえで、今回の米国によるイラン空爆は外交を無視するネタニヤフ首相が、米国をトランプが10年間望んできた戦争に引きずり込んだとし、ウクライナと中東での和平努力の失敗に挫折したトランプ氏は迅速な勝利を見出すためにネタニヤフと結びついたと指摘する。こうした一連のトランプの決断と行動は、自身の孤立主義的な支持基盤を驚かせ、中東を不安定と危機に陥れる大きな賭けであることは間違いない。幸い事態はイスラエルとイランの停戦合意という方向に向かったが、それは薄氷の合意と言える。
そこで問題となるのは第3の問題点、すなわち、イスラエルによるイラン攻撃や米国の参戦目的や意図が達成されたのかどうかということである。メディアは、米大統領の現在の課題はイラン指導部に地域を破滅的な状況に陥れないことや、核兵器入手の考えの放棄を説得することだと述べ、米国が行動を急いだのは誤った選択だと主張。トレードオフの問題を取り上げ、イスラエルと米国の行動は全体として得るものよりも失うものが大きいと懸念を表明する。空爆にはイランの核プログラム遅延というプラス面があるが不確実だとし、マイナス面では、イランと代理勢力やテロ組織による米軍兵士や民間人の殺害、ホルムズ海峡を危険な状態におきエネルギー価格を急騰させる可能性などのリスクを挙げる。
メディアが懸念するようにトレードオフの観点からは、マイナス面の方が大きい。ただし、イスラエルは核関連の標的を幅広く攻撃し、体制変革を誘発する可能性を示唆しているが米国は核施設にのみ焦点を当て、体制の転覆を試みる意図はない旨を明らかにしている。イスラエルと米国の狙いは明らかに異なる。米国は、体制転覆による混乱を恐れていると考えられる。その意味で、メディアがトランプ氏は早急に外交に転換すべきだと提案しているのは適切だったが、結局、トランプはこうした考えを受け入れる前に空爆に踏み切った。これに対してメディアはトランプの決定を批判するが、トランプ氏が急いで行動した以上、地域が制御不能に陥る可能性を最小限に抑える必要があるのは間違いない。しかし、イランも結局、報復攻撃に出て米軍基地などを攻撃するが迫力に欠けるものだったこともあり、両陣営はやや唐突に停戦の合意に至る。こうした一連の事態の展開からイスラエルと米国は戦争や空爆の目的を達成したと考えていることが観察されるが、これは次の第4の問題と共に振り返るのが適切であろう。
停戦の合意の報を受け、メディアはイランの弱々しい報復は体制が受けた打撃の大きさを示し、イランの国力と決意を示す攻撃としては失敗だったと評する。そのうえで、停戦合意はイランの降伏を意味し、わずか12日間の戦争でイスラエルと米国は大きな成果を得たと断定する。こうしたメディアのイランが大打撃を受けたとの見方は間違いないと思われる。イランは、核濃縮・兵器化施設に加え、主要な軍事司令官と核科学者、そしてミサイル生産・発射能力の大部分を失ったとみられている。イランとその代理勢力によってイスラエルの存続が脅かされてきた現状に戻るつもりがないことを明確にしているネタニヤフ首相が、停戦に合意したのはこうしたイランの損害、とりわけ地中深く建設されたフォルドウの核施設もほぼ壊滅したと現時点では考えていることを示している。つまり、イスラエルも米国も目的を達成したと認識しているということである。イランがミサイルや核能力の再建に固執するなら、イスラエルが再び同国を攻撃する構えであるのは当然であろう。
最後の中東情勢の今後という問題は、イランの現体制がこの先どうなるかという問題と共に考えていく必要がある。イランの今後について、メディアはハメネイ師が民衆蜂起や体制幹部あるいは軍幹によるクーデターによる失脚の可能性を示唆するが、その後継者が今より悪い影響をもたらすとは思えないとし、12日間戦争が平和な中東の実現に向けた希少な機会を生み出したとの楽観的見方を示す。そうした機会が生み出されたことはまちがいないが、イランの核施設残存と濃縮ウラン一部備蓄の可能性、また米国参戦が引き起こしたアラブ同盟国の動揺などを勘案すると前途は予断を許さないと言わざるを得ない。トランプ政権の対応が特に重要だが、日本も欧州とアジアの有力諸国と共に建設的な役割を果たしていくべきだろう。
§ § § § § § § § § §
(主要トピックス)
2025年
6月16日 主要7カ国首脳会議(G7サミット)、カナダで開幕。石破茂首相、初参加。
現地でトランプ米大統領と首脳会談。ただし関税措置についての進展はなし。
18日 韓国国防省、日米韓3カ国による共同空中訓練の実施を発表。
李在明政権発足後初。
日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収、正式に完了。
20日 タイの上院議会、憲法裁判所にペートンタン首相の解任を求める請願書を提出。
カンボジアとの国境問題を巡る対応が憲法の規定に違反したと主張。
22日 東京都議会選挙で自民党、大敗。都民ファーストの会が第1党へ。
24日 日本政府、参院選を「7月3日公示―20日投開票」の日程で実施すると決定。
27日 赤沢亮正経済財政・再生相、ワシントンで7回目の日米関税交渉に臨み、ラトニ
ック米商務長官と会談。
29日 中国政府、東電福島第1原発の処理水放出を受けて止めていた日本産水産物
の輸入の即時再開を公表。
7月1日 タイ憲法裁判所、ペートンタン首相の解職是非について法的結論が出るまで
職務の一時停止を命じると発表。
2日 米国とベトナム、貿易協定の締結で合意。米国は相互関税を原則20%と当初計
画の半分以下に引き下げ。
4日 カンボジア政府、米国と相互関税を巡る貿易協定の枠組みに関する共同声明で
合意に達したと発表。関税率などの詳細は不明。
7日 トランプ米大統領、貿易相手国に8月1日から適用される新関税率の通知を
開始。日本と韓国に対し25%の関税をかけると通告。
10日 日本と東南アジア諸国連合(ASEAN)、マレーシアで外相会議を開催。
共同声明でトランプ米政権の高関税が「世界経済を分断する」と懸念を表明。
岩屋毅外相、訪問先のマレーシアで中国の王毅(ワン・イー)共産党政治局員兼
外相と会談。レアアース(希土類)の輸出規制の強化に懸念を表明。
13日 インドネシア、EUと包括的経済連携協定(CEPA)の締結で政治合意。
15日 トランプ米大統領、インドネシアとの関税交渉で「重要な合意を結んだ」と表明。
米国の対インドネシア関税率を19%にする一方で、インドネシアは関税を撤廃。
中国政府、電気自動車(EV)向けリチウムイオン電池の製造技術を輸出規制対
象に含めたと発表。
主要資料は以下の通りで、原則、電子版を使用しています。(カッコ内は邦文名) THE WALL STREET JOURNAL (ウォール・ストリート・ジャーナル)、THE FINANCIAL TIMES (フィナンシャル・タイムズ)、THE NEWYORK TIMES (ニューヨーク・タイムズ)、THE LOS ANGELES TIMES (ロサンゼルス・タイムズ)、THE WASHINGTON POST (ワシントン・ポスト)、THE GUARDIAN (ガーディアン)、BLOOMBERG・BUSINESSWEEK (ブルームバーグ・ビジネスウィーク)、TIME (タイム)、THE ECONOMIST (エコノミスト)、REUTER (ロイター通信)など。なお、韓国聯合ニュースや中国人民日報の日本語版なども参考資料として参照し、各国統計数値など一部資料は本邦紙も利用。
バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教授 前田高昭
PDF版