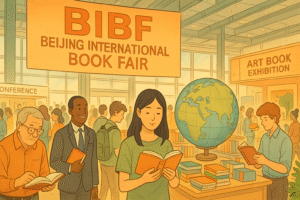2025年7月7日 第367号 World News Insight (Alumni編集室改め) ハーバード大学留学生ビザ問題から見える、
世界の大学と留学生戦略の真実 バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
2025年6月、アメリカではトランプ前大統領が、ハーバード大学に在籍する外国人留学生のビザを取り消すよう国務省に指示したと報じられました。文書には「国益に合致する場合は除外」という但し書きがついてはいるものの、単なる入国制限ではなく、背景には知識人層への圧力という政治的思惑が隠されています。
ハーバード大学は長年、アメリカにおけるリベラル知識層の象徴とされ、多くの民主党系の政治家や有力な学者を輩出してきました。ケネディ、オバマといった歴代大統領から、ノーベル賞受賞者に至るまで、アメリカ社会に与える影響力は計り知れません。共和党のトランプ氏にとって、こうした大学は自らを批判する牙城であり、攻撃の的になりやすい存在です。ハーバードだけでなく、ジャーナリズムで有名なコロンビア大学なども同様にターゲットとされています。
留学生を止めて大学を兵糧攻めに
留学生を制限する政策には、政治的な意味合いだけでなく、大学経営を直撃する側面もあります。ハーバードをはじめとする名門大学は、多くの外国人大学院生を受け入れており、彼らが支払う高額な授業料がアメリカ人学生の奨学金の原資になっています。もし留学生が減れば学費収入が減少し、さらに政府の補助金凍結が重なれば、大学は資金面で大きな打撃を受けます。つまり、トランプ氏はハーバードに対して経済面からの締め付け、いわば兵糧攻めを仕掛けている形です。
一方で、こうした措置の背景には安全保障の意図もあります。大学の研究成果や技術が他国に流出するリスクは現実の問題です。特に中国からの留学生がこの議論の中心にあります。アメリカは1980年代以降、中国の若者を大量に受け入れ、自由主義に触れさせることで、中国の民主化を後押しするという理想を描いてきました。しかし、現実にはそうした理想は思うようには進まず、むしろ逆に優秀な人材がアメリカで知識と人脈を獲得した後、中国に戻って共産党に忠誠を誓う構図が定着しています。
アメリカのソフトパワー戦略の誤算
中国では共産党幹部の子弟がハーバードをはじめとする名門大学に留学し、卒業後は中国国内の企業や政府機関で中枢を担います。帰国後は共産党の指示に従わざるを得ない事情もあり、アメリカが期待したように親米派にはならず、むしろ獲得した知識と技術を自国の発展に役立てる人材となっています。アメリカのソフトパワー戦略は、ある意味で中国の現実主義に上手く取り込まれてしまった形です。
実際に、こうした留学生の存在は中国国内の産業や研究開発の競争力向上に直結しています。中国側からすれば、優秀な若者を海外に送って一流の教育を受けさせ、最新の研究情報を手に入れて帰国後に活用するのは当然の国家戦略です。アメリカにとっては大きな誤算であり、今回のビザ制限には、そうした背景で失われた優位性を取り戻す思惑も見え隠れしています。
留学生制度を戦略に組み込むイギリス
こうした留学生制度を国家戦略として最初に体系化したのはイギリスでした。19世紀末に南アフリカでダイヤモンド事業で莫大な富を築いたセシル・ローズは、自らの遺産を基に「ローズ奨学金」を創設しました。これは旧大英帝国の植民地から選ばれた優秀な若者をオックスフォード大学に集め、イギリスと旧植民地のエリート層を結びつけるという仕組みです。この仕組みは100年以上続いており、米国のクリントン元大統領をはじめ、各国のリーダー層にローズ奨学生は少なくありません。
さらにイギリスは、メディア企業もこの戦略を活用しています。世界有数の通信社ロイターは、優秀な現役ジャーナリストを対象に独自のスカラシップを設け、オックスフォードで学ばせています。これにより、世界各地に自社記者だけでなく、協力関係を築いた記者ネットワークを広げ、どこで事件が起きても取材できる体制を整えているのです。
インドネシアやカンボジアにも及ぶ留学ネットワーク
企業が留学生を活用する例もあります。インドネシアでは、スハルト政権下で有力経済官僚の多くが米国のカリフォルニア大学バークレー校に留学し、「バークレーマフィア」と呼ばれる政策グループを形成しました。これにより、米企業は現地の経済政策に直接影響力を及ぼし、エネルギー資源の開発などを優位に進めました。カンボジアでも現首相の息子が米陸軍士官学校を卒業しており、アメリカは軍事面でもパイプを確保しています。
このように、留学生を通じて相手国の有力層とつながり、自国企業の進出を円滑にする―これが、英米が長年培ってきた国家戦略としての留学生政策です。
日本の課題とこれから
日本もかつては同様の取り組みをしていました。ビルマ(現ミャンマー)のアウンサン将軍や台湾の李登輝元総統が若い頃に日本で学んだことは有名です。戦前の日本は、留学生を通じてアジア各国の独立運動の指導者を育て、親日派を生み出しました。しかし戦後、日本の留学生政策は「教育の平等性」が重視され、国家戦略としての色合いは薄れていきました。
近年、東北大学がハーバードからの留学生受け入れを表明するなど、再び留学生を通じた国際戦略の再構築に舵を切る兆しが見え始めています。留学生の受け入れは単なる国際交流にとどまらず、将来の外交、経済、文化を形作る重要な布石でもあります。相手国のエリート層を自国で学ばせ、日本を理解し親近感を持たせることは、将来的に大きな財産になります。
アメリカやイギリスが築いてきたこの「見えない資産」を、日本も改めて国益として捉え、戦略として磨き直す必要があります。かつてのように一度生まれた親日派ネットワークを次世代に繋げ、国家としての競争力を支える大きな力にできるかどうかが、これからの大きな課題です。