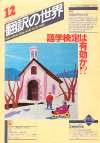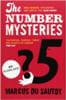2025年11月22日 第376号 World News Insight (Alumni編集室改め) AIが進化する時代に、「身体のリアル」が蘇る
―高岡英夫・押井守・最上和子に学ぶ、身体性の再起動 バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
ChatGPTをはじめとするAIの進化は、人間の知的活動の深部にまで踏み込もうとしています。文章をつくり、音楽をつくり、思考を模倣し、会話さえ人間らしく行うAIが次々と登場するなかで、多くの人が言語化しづらい不安を抱えています。
「私たちは、何によって“人間”であり続けられるのか?」
この問いに対し、静かに、しかし力強く応えるのが、「身体性」の回復という視点です。とりわけ、高岡英夫氏の「身体意識論」、そして押井守氏・最上和子氏が論じた「身体のリアル」の思想は、AI時代の人間の生存戦略を再構築する鍵となるものです。
思考はAIに、しかし“身体”は誰にも渡せない
高岡英夫氏は『身体意識を鍛える』の中で、「身体意識」という概念を提示しました。これは、筋肉や骨格だけでなく、動き・感覚・気配・エネルギーといった目に見えない身体の情報を、精妙に感じ取り、使いこなす能力を指します。人間は、言語を使う前に、身体で感じ、動き、世界と関わってきました。つまり、身体意識こそが人間の“最初の知性”であり、“最後の砦”なのです。AIは膨大な知識を記憶し、膨大な計算を高速で処理できます。しかし、「今ここ」に身体をもって存在し、感受し、共鳴し、判断するという力は持ち得ません。
「身体のリアル」とは何か?――押井守の問いかけ
映画監督・押井守氏は、身体感覚を喪失していく現代人の姿を、さまざまな作品を通じて描いてきました。『イノセンス』における“電脳化された身体”、あるいは『スカイクロラ』における“成長しない身体”は、いずれも「身体の実在感を失った人間は、果たして人間たりえるのか?」という深い問いを投げかけています。押井氏が語る「身体のリアル」とは、単に物理的な身体のことではなく、世界との関係性を自らの身体で構築し、感じ、受け止めることを意味します。それは、アスリートのように極限の肉体を鍛えることではなく、日常のなかで自分の重心の位置、足裏の感覚、息の深さ、他者との距離といった微細な情報をキャッチできるかという、“身体的自覚”の問題なのです。
“頭で生きる”時代に、身体から取り戻す
私たちは、幼い頃から“考える力”を鍛えるように教育されてきました。知識を得て、論理的に考え、言語で表現する。それらはもちろん重要な力です。しかしAI時代に入った今、それだけではもはや“人間らしさ”を支えるには不十分です。最上和子氏(身体論研究者)は、現代人が身体を「所有物」としてしか捉えられなくなっていることを危惧しています。彼女が言うように、「身体のリアル」は頭で観察する対象ではなく、“今ここ”で生きている身体とともにある自己感覚=Beingとしての身体です。この感覚が失われると、人間は“情報処理装置”と何ら変わらない存在になってしまいます。だからこそ、「身体を取り戻す」ことが、人間らしさの再起動につながるのです。
ゆるむことが、リアルな感受性を回復させる
高岡英夫氏が提唱する「ゆる体操」は、こうした身体のリアルを取り戻す方法論として、極めて有効です。力を抜き、身体の奥深くにある感覚をゆっくりと呼び覚ましていくこの運動は、外的な成果やスピードを競うことから解放され、「存在すること」そのものを取り戻すプロセスです。
- 無駄な力を抜いた滑らかな動き
- 呼吸の深さ、体幹の重さ、皮膚の感覚
- 心のざわつきの沈静化
- 他者との“共鳴”による空気感の回復
こうした現象は、AIには決して真似できない、“人間にしかできないリアル”の証です。
AI時代における「人間の開発」は、身体から始まる
もはや「もっと頭をよくしよう」「AIに負けない知識を身につけよう」というアプローチには限界があります。なぜなら、AIは人間の“知性”の領域を超えていくからです。
だからこそ、これからの人間開発は、「身体性の開発」へとシフトすべき時代に入っています。
- 感覚に目覚める
- 緊張をゆるめる
- 存在を感じる
- 他者と響き合う
- 意識のノイズを沈める
こうした身体からの変容こそが、AIでは決して実装できない“人間性の根幹”をつくる営みなのです。
人間が「人間であり続ける」ために
AIは人間のように“見える”言葉を操り、画像をつくり、感情的な返答を返すようになりました。それでも、AIには痛みも、重力も、気配も、葛藤もありません。それらすべてを感じながら生きている存在――それが「人間」です。そしてその感受性の核には、必ず「身体」があります。“ゆるむ”ことは、自分自身のリアルを取り戻すこと。身体を取り戻すことは、人間としての尊厳を守ること。この時代にこそ、私たちは「身体」という最も身近で、最も深遠な智慧の源に、立ち返るべきではないでしょうか。