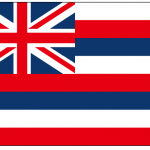2025年11月7日 第375号 World News Insight (Alumni編集室改め) フェミニズムの嘘と欺瞞
―アカデミアに巣食う「女性権力」のカラクリ バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
日本社会ではここ数十年、「男女平等」や「ジェンダーギャップ解消」といったスローガンが繰り返し唱えられてきた。大学やマスコミを中心に、フェミニズムを旗印とする言説が社会的正義のように扱われてきた結果、異論を差し挟むことすらはばかられる空気が形成されている。しかし、その主張の根拠とされてきたデータや論理を冷静に検証すれば、そこには驚くほどの矛盾と欺瞞が潜んでいる。 本稿では、アカデミズムに深く根を張ったフェミニズムの構造的問題と、それを支える「女性権力」のメカニズムを明らかにしたい。
「女性首相誕生」に冷淡なフェミニズム
2025年、高市早苗氏が自民党新総裁に選出されたニュースは、女性の政治進出を象徴する歴史的出来事として多くの国民に歓迎された。しかし意外にも、フェミニストの一部はこの出来事に冷ややかな反応を示した。代表的な論者である上野千鶴子・東大名誉教授は、「初の女性首相が誕生するかもしれないと聞いてもうれしくない」と語り、世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数が上昇しても「女性に優しい政治にはならない」と断言した。
一見もっともらしい批評に聞こえるが、これは明らかな自己矛盾である。なぜなら、これまで「日本は女性差別的な国だ」と訴え、ジェンダーギャップ指数をその根拠として振りかざしてきたのは、ほかならぬフェミニスト自身だったからだ。指数が低いときは「日本は遅れている」と非難し、改善の兆しが見えると「指標など関係ない」と言い放つ。これは科学的態度でも社会的誠実さでもない。イデオロギーに都合のよいときだけ数字を利用し、都合が悪ければ無視する。その恣意性こそがフェミニズム批判の核心にある。
ジェンダーギャップ指数という幻想
では、そもそもジェンダーギャップ指数とは何か。世界経済フォーラムが発表するこの指標は、政治・経済・教育・健康の四分野で男女の格差を数値化し、各国をランキングするものである。日本は常に下位に位置づけられ、「先進国中最悪の女性差別国」と報じられる。しかし、専門家の間ではこの指数の恣意性が以前から指摘されている。
たとえば、女性の労働参加率が低い国でも、男女賃金差が小さいというだけで高い評価を得ることがある。逆に日本のように女性が長寿で、教育水準も高く、社会参加の自由が保障されていても、政治家や企業経営者に女性が少ないという一点だけで大幅に減点される。結果として、女子割礼の風習が残るエチオピアや、女性の人身売買が深刻なガーナが、日本より「男女平等」と判定されるのだ。このような数値を根拠に「日本は女性差別大国」と断ずること自体、非科学的な政治プロパガンダにすぎない。
幸福度の逆転――「不幸な男性」「幸福な女性」
一方で、別の国際指標――たとえば「世界幸福度ランキング」――に目を向けると、まったく異なる風景が見えてくる。日本の女性の幸福度は世界でも上位にあり、しかも男女間の幸福度格差は「男性が不幸、女性が幸福」という形で極端に開いている。つまり、日本社会はフェミニストが描くような「女性抑圧社会」ではなく、むしろ女性の方が生活の安定や心理的満足度で優位に立つ構造を持っているのである。
それにもかかわらず、「女性は常に被害者である」と訴える物語がメディアで繰り返され、男性の疲弊や孤立は顧みられない。男性の自殺率が女性の2倍を超えるという統計も無視される。フェミニズムが真に「ジェンダー平等」を掲げるならば、男性の困難にも目を向けるべきだろう。だが現実には、フェミニズムは「女性の利益団体」化し、政治的資源を独占する手段として機能している。
アカデミアに巣食うフェミニズム権力
日本の大学では、フェミニズムが長年「批判されてはならない思想」として聖域化されてきた。ジェンダー研究という名のもとに、社会構造を「男性による抑圧」として単純化し、異なる視点を排除する風潮が広がった。助成金や研究ポストの配分においても、フェミニズム系の研究者が優遇される構造が出来上がり、「フェミニズム村」とも呼ばれる閉鎖的ネットワークが形成されている。
彼女たちは「女性の声を代弁する」と称しながら、実際には特定の政治的立場を代表しているにすぎない。自分たちと異なる考えを持つ女性――家庭を重視する女性、伝統を尊ぶ女性、政治的に保守的な女性――を「時代遅れ」や「内面化された差別」として切り捨てる。そこには多様性への寛容も、自由な言論への敬意もない。つまり、アカデミアの一部を支配するフェミニズムは「平等」の名の下に新たな差別を生み出しているのである。
「女性権力」という新たな構造的不平等
現代日本で進行しているのは、男女の逆転現象である。教育現場では女子の学力が男子を上回り、企業では女性活躍推進の名目で男性が昇進機会を奪われる事例も増えている。政治の世界でも、「女性比率」を上げること自体が目的化し、能力より性別で評価される風潮が強まっている。
こうした状況を支えるのが、フェミニズムを政治利用する「女性権力」である。メディアを通じて「女性を批判する者=差別主義者」というレッテルが貼られ、議論の余地を奪う。SNS時代には、わずかな発言を切り取り「炎上」させることで言論空間を制圧する。こうして「平等」を掲げながら実質的には「特権」を得る構造が作られている。この構図を指摘すること自体がタブー視されているが、社会が成熟するためにはタブーを恐れずに不均衡を直視する勇気が必要だ。
真の平等とは何か
本来、ジェンダー平等とは「性別にかかわらず能力と人格によって評価される社会」を目指す理念である。だが今日のフェミニズム運動は、その理想から遠く離れ、「被害者意識の政治化」「利権の制度化」へと変質してしまった。
社会が求めているのは、男性を敵視するイデオロギーではなく、互いの立場を尊重し、現実的な課題を共有する新しいジェンダー対話である。数字のマジックや感情的スローガンではなく、実証的データと冷静な議論に基づいた政策こそ必要だ。
いま問われているのは、「女性を守るか、男性を守るか」ではなく、「真実に誠実であるかどうか」である。フェミニズムの欺瞞を暴くことは、女性を攻撃することではない。むしろ、女性も男性も対等に尊重される社会を取り戻すための第一歩なのだろう。






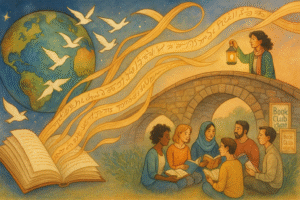


![第11回【2】オーストラリア絵本レポート[3]](https://babel.co.jp/gwg/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/658405-150x150.png)