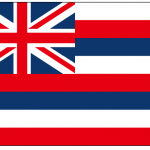第16回 海外の出版業界情報(2025年8月)
物語体験プラットフォーム:物語の没入体験へ
米国発のテクノロジースタジオHidden Doorは、従来の「読書」や「ゲームプレイ」といった枠組みを超え、物語を「体験」できるプラットフォームを公開し、早期アクセスを開始したと発表しました。
このプラットフォームでは、ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』、ライマン・フランク・ボームの『オズの魔法使い』、ジェームズ・オバーのコミックシリーズ『ザ・クロウ』などの世界を舞台に、AIと共に「自分で選ぶ冒険」スタイルの物語を共創し、没入型エンターテインメントを楽しむことができます。
「小説の新刊発売や映画の公開初日にファンが集まり、語り合うように、本や映画、番組のファンが集い、交流し、お気に入りのストーリーをリミックスできる居場所をつくっています」と、Hidden DoorのCEO兼共同創業者のヒラリー・メイソン氏はPublishers Weeklyで語っています。
プレイヤーは、例えば「高慢と偏見+吸血鬼」といったアレンジ版の物語を選び、キャラクターを作成して背景や特徴を設定します。システムから提示される冒頭のシナリオに応答する形で物語が進行し、これはまるでロールプレイングゲームにおけるゲームマスターとのやり取りに似ています。
まだ語り口が断片的だったり、処理に時間がかかったりと粗削りな面もありますが、このようなサービスの登場は出版業界に次のような示唆を与えているといえるでしょう。
「読む」から「没入する」へ
単に物語を読むのではなく、「物語の世界に身を置き、出来事を共に体験する」。これこそがHidden Doorが提示する新しい読書の形です。紙や電子書籍という媒体を超えて、没入型の物語体験を設計することにより、新しい収益モデルの創出や読者層の拡大が期待できます。
パブリックドメイン作品の再価値化
Hidden Doorは、著作権が切れた古典文学をAIで再構築し、誰もが没入できる体験へと「リミックス」しています。例えば夏目漱石や宮沢賢治の作品も、次世代の読者に「参加型の物語体験」として提供できれば、教育分野などにも広がる可能性があります。
現役作家との共同創作
パブリックドメイン外の作品については、Hidden Doorは「可能な限り限定的」なライセンス契約を結び、収益分配を行う方針です。現役の作家とも協働し、物語世界を没入型体験として展開することで、「書籍販売+没入体験権」という新しいライセンスモデルが生まれるかもしれません。
コミュニティでの物語共有
没入体験は「一人で読む」から「みんなで味わう」へと拡張できます。物語を共有し、語り合い、再解釈し合うコミュニティが形成されれば、作品の寿命は大幅に延び、より多くの人々に支持される可能性があります。
「制約」が生む物語のリアリティ
AIチャットボットとの対話でも同じことができそうですが、ChatGPTなどはユーザーの提案をほぼ無制限に受け入れてしまいます。そのため「ルールを破って即勝利」といった展開が簡単に成立してしまい、物語性が失われることも少なくありません。
Hidden Doorでは、物語ごとの論理の中で行動する必要がある点が特徴です。この「制約」は不満を生むこともありますが、逆に挑戦や物語としての手応えをもたらします。
Hidden Doorの事例は、出版業界にとって「物語体験産業」という新しい可能性のヒントとなります。アニメやマンガなどのコンテンツと組み合わせれば、その可能性はさらに広がるでしょう。
参照:Hidden Door
https://www.hiddendoor.co/
参照:Publish Weekly "Hidden Door Rolls Out Literary Roleplaying Platform"
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/licensing/article/98406-hidden-door-rolls-out-literary-roleplaying-platform.html
参照:The Verge "Hidden Door is an AI storytelling game that actually makes sense"
https://www.theverge.com/games/757816/hidden-door-early-access-ai-story
村山有紀(むらやま・ゆき)
IT・ビジネス翻訳歴10年以上。国内外の様々な場所での生活と子育ての
経験をふまえ、自分らしい発信のスタイルを模索中。