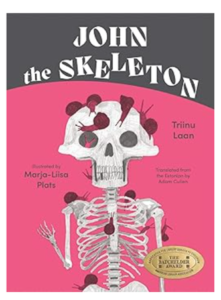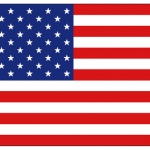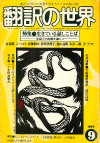2025年5月22日 第364号 World News Insight (Alumni編集室改め) 「自分を好きになる」より大切なこと ――行動して結果を出す力=自己効力感(self-efficacy)を育てよう バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
近年の日本では「自己肯定感(self-esteem)を高めよう」という標語が教育現場や子育て講座で合言葉のように語られている。しかし「自分が好き」と感じるだけで夢が実現するわけではない。本人が手と頭を動かし、試行錯誤を経て成果を積み重ねてこそ、自信は地に足の着いたものになる。ここで鍵となるのが、行動と結果の因果を自分で確かめる力――自己効力感(self-efficacy)である。
そもそも「将来の夢」や「誇れる個性」は、社会や他者との相互作用の中で磨かれてこそ本物になる。作文コンクールで入賞したり、地域のボランティア活動で感謝を受けたりと、外の世界に試してこそスキルも価値観も更新される。「自己肯定感さえあれば大丈夫」と子どもに言い聞かせるだけでは、挑戦という行動のステップが抜け落ちがちだ。課題に挑み、うまくいかなければ振り返り、作戦を立て直して再挑戦する――このプロセスを繰り返さなければ、根拠のない自信は失敗や批判にさらされた瞬間に崩れてしまう。
この点で参考になるのが米国の教育心理学である。そこでは自己効力感(self-efficacy)の育成が重視され、授業や課外活動に「目標設定→実行→振り返り→改善」のサイクルが意図的に組み込まれている。理科の探究学習では仮説を立てて実験し、結果を分析して条件を変える工程を子ども自身が管理する。コミュニティサービス学習では地域課題を調べ、チームで計画を立て、実行後に成果と改善点を発表する。いずれも「自分が動けば結果が変わる」という感覚を身体化させる仕掛けだ。一方、日本では情緒的な自己肯定感が強調されるわりに、こうした行動の練習場がまだ充実していない。
未来を本当に見通す教育には二つの力が欠かせない。一つは十年単位の目標を自分で描き、必要なステップを逆算できる力。もう一つは途中に現れる壁を自己調整しながら乗り越える力だ。これらを支えるエンジンこそ自己効力感(self-efficacy)であり、学力やコミュニケーション力を動かすモーターの役割を果たす。
では自己効力感をどう高めるか。第一に、子どもが少し背伸びすれば届く「適度にむずかしい課題」を系統的に提示し、成功体験を言語化させること。失敗を「能力不足の証拠」ではなく次の戦術を考えるためのデータとして扱う視点も欠かせない。第二に、仲間の成功例を参照し合い、相互フィードバックによって自己評価を現実につなぎ止める仕組みをつくること。第三に、動機を損なわない範囲で成果を見える化し、協働体験を通じて「自分の行動は周囲にも価値を生む」と実感させることだ。この循環が回り始めれば、称賛やご褒美に頼らない「続けられる自信」が育つ。
さらに教師や保護者には伴走者としての役割が求められる。問いかけと観察で試行錯誤を支え、成功も失敗も学習素材として共に整理する姿勢が必要だ。支援とは先回りして障害を取り除くことではなく、子どもが自力で越えられるよう“足場”を設けることである。
自己効力感(self-efficacy)を備えた子どもは、学習面だけでなく心の健康でも優位に立つと報告されている。スタンフォード大学の縦断研究では、自己効力感が高い児童ほどストレス場面での対処が上手く、不安や抑うつの発症リスクが低いという結果が示された。逆に、結果を伴わない過度の賞賛で育った場合、つまずいた瞬間に「才能がない」と早々にあきらめる“学習性無力感”に陥りやすいことも指摘されている、と言う。
こうしたエビデンスを踏まえれば、学校や地域はもちろん、企業の研修やスポーツ少年団など子どもが関わるあらゆる場で「挑戦→フィードバック→再挑戦」の文化を根づかせる必要があるだろう。日本社会全体が“失敗の許容度”をもう一段引き上げ、「次にどう生かすか」を語り合う風土へ転換できるかどうかが、未来への分水嶺となるか。
今、日本の教育が真に取り組むべきは「自己肯定感(self-esteem)の向上」ではなく、目標達成力と他者貢献を統合した自己効力感(self-efficacy)の醸成である。子どもが課題を選び、戦略を試し、結果を振り返り、次の挑戦へ踏み出す――このサイクルを回せるよう、エビデンスに裏づけられた実践的プログラムを早急に整備しなければ、世界との教育格差はさらに広がるばかりだ。「やればできる」という実感をすべての子どもたちへ――それこそが未知の時代を切り拓く確かな鍵となるだろう。