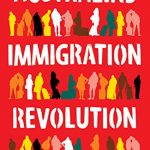2025年9月22日 第372号 World News Insight (Alumni編集室改め) 世界は揺れ、日本は常識を取り戻すとき
―グローバリズムからナショナリズムへの流れの中で バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
コモンセンスを取り戻すとき―グローバリズムからナショナリズムへ
世界を見渡すと、いま大きなうねりが走っています。その正体は「グローバリズム」と「ナショナリズム」のせめぎ合いです。グローバリズムは、国境を越えて人やモノや情報が自由に行き来することを善とする流れです。確かに便利でした。世界中の製品が安く手に入り、留学や旅行も日常化しました。けれども、その裏で「開かれすぎた扉」がもたらす副作用も大きくなってきました。受け入れた社会が教育・医療・治安の面で追いつかず、人々の不安が募る。そこで「やはり自分たちの暮らしを守らねば」という反動として、ナショナリズムが力を取り戻しているのです。
世界各地の「反動」
アメリカでは、トランプ前大統領を中心に「Make America Great Again―アメリカを再び偉大に」というスローガンが広がりました。移民制限や国内産業の保護を訴え、いわば「常識を取り戻そう」というムーブメントとして支持を集めています。暗殺未遂事件の衝撃もありましたが、むしろ人々の結束は強まっているように見えます。ヨーロッパも同じです。
イギリスの「改革UK」、フランスの「国民連合」、ドイツの「AfD」など、反グローバリズムや反移民を掲げる勢力が勢いを増しています。背景にあるのは、市民の実感に根ざした生活不安です。雇用が奪われる、街の安全が揺らぐ、文化が失われていくーそうした声が投票行動を変えているのです。さらに中東では、イスラエルとガザの衝突が続き、戦争の論理が人道の言葉と激しくぶつかっています。南アジアのネパールでは、SNS規制をきっかけに大規模な抗議デモが自然発生しました。背景には政治腐敗や格差拡大への不満があります。
カンボジアは国籍剥奪法を整備して越境犯罪を抑えようとし、ベトナムは税逃れ対策で数百万口座を閉鎖。メキシコも対中関税を強化するなど、各国がそれぞれの形で「国家の裁量」を取り戻そうとしています。まさに世界全体が、グローバリズムの行きすぎに対して修正を加えようとしているのです。
日本も無縁ではない
では日本はどうでしょうか。人口減少が進むなかで、外国人労働者や留学生の受け入れが急速に拡大しています。観光客も一気に戻り、街中では外国語が飛び交います。これ自体は経済を潤す側面がありますが、同時に地域では「学校現場が対応できない」「医療や住宅が逼迫する」といった不安の声も上がっています。これは排外主義ではなく、ごく当たり前の生活感覚から出てくるものです。「自分たちの暮らしがこのまま守られるのか」という素朴な問いかけです。つまり日本もまた、「開く」と「守る」のバランスを取る局面にあるのです。
コモンセンスを取り戻すとは何か
では、日本が取り戻すべき「コモンセンス」とは何でしょうか。それは、暮らしの当たり前を大切にする感覚です。子どもが安心して学校に通えること。病院で言葉が通じ、誰もがきちんと診療を受けられること。地域の安全が保たれていること。こうした基本的な安心感が揺らいでしまえば、社会は簡単に分断されます。だからこそ、受け入れの規模や制度を決める前に、まずは教育・医療・治安の土台を整える必要があります。費用負担をどうするのか、誰が責任を持つのかを明確にし、社会全体で支える仕組みを設計すること。それが「コモンセンスを取り戻す」ということに他なりません。
議論できる国に
世界各地で「言いたいことが言えない」という不満が爆発し、デモや衝突に発展しています。日本もまた、さまざまな課題を前に、意見の違いを隠すことはできません。大切なのは、異なる考えを持つ人を排除するのではなく、公開の場で堂々と議論できる国にすることです。意見が違うのは当然のこと。それを互いに言葉にしてぶつけ合い、解決策を探っていく。そんな討論文化を学校教育から育て、メディアや政治も「争いを整理する役割」を果たすべきです。これもまた、失われつつあるコモンセンスを取り戻す作業だと言えます。
自立の力を取り戻す
もう一つ大切なのは、日本の自立です。食料、エネルギー、医薬品や半導体―どれも海外への依存度が高すぎます。平時には問題なくても、ひとたび戦争や摩擦が起これば供給は止まります。だからこそ、農業の持続力を高め、再生エネルギーや省エネを進め、基幹技術を国内で育てることが欠かせません。これは単なる産業政策ではなく、私たちの暮らしを守る「生活の安全保障」です。
外交の現実主義
最後に、外交の舵取りです。日本は地理的にアジアの真ん中にあり、アメリカとも中国とも深く関わっています。大国の対立に巻き込まれすぎず、しかし同盟を実のある形に育て、地域全体と面でつながる。これが現実的な選択です。とくに教育や研究の分野では、世界から優れた人材を呼び込むことが欠かせません。ただし、言語や社会統合の仕組みを明確にして「共に暮らせる条件」を整えることが前提です。開かれた交流は、日本が信頼される力になります。
おわりに
世界はグローバリズムの光と影を経験し、いまナショナリズムの揺り戻しに入っています。アメリカもヨーロッパも、新興国も、それぞれの形で「自分たちの常識を取り戻す」動きを強めています。日本が学ぶべき教訓は明快です。常識を忘れず、常識を守り、常識のうえに未来を築くこと。「開く」か「閉じる」かという単純な対立を越えて、私たちはもう一度、自分たちのコモンセンスを見つめ直すときに来ています。