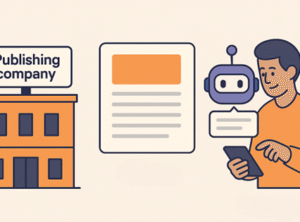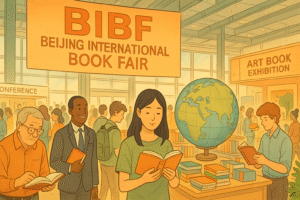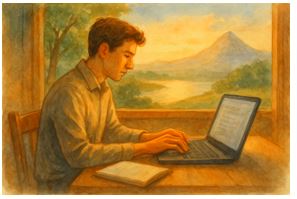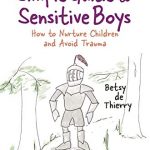第15回 海外の出版業界情報(2025年7月)
AI要約時代へ:出版社は「読まれなくなる未来」にどう備えるべきか
今回は、ニュース・ジャーナリズム系の出版社を中心としていますが、ひいては書籍出版業界にも大きく影響しそうな兆候に焦点を当てます。
生成AIの台頭により、読者の目がメディアから「要約」へ
2025年6月にThe Atlantic誌が発表した記事「The End of Publishing as We Know It」は、出版業界にとっての「赤信号」とも言える内容でした。ChatGPT、Claude、Google AI Overviewsなど、生成AIによる要約が当たり前になったことで、読者が元記事にアクセスしなくなっているというのです。
ある大手出版社では、AI検索導入後にウェブトラフィックが34%以上減少したとのこと。これは一時的な減少ではなく、出版社の収益構造を揺るがす大きな変化です。
AIが記事を「盗む」のではなく、手っ取り早い情報を先に届けてしまう
生成AIは、出版社の文章を全文コピーして提供しているわけではありません。しかし、記事を要約・加工し、ユーザーに「手っ取り早い情報」を届けてしまいます。しかも、それが検索画面やアプリ内で完結するため、元メディアに読者が来ないのです。
つまり、広告は表示されず、有料購読ページにも誘導できず、出版社にとって収益につながらなくなっています。
出版社の収益モデルは再設計を迫られている
これまで出版社は、以下のようなモデルで収益を確保してきました。
• 広告収益:ウェブページの閲覧回数を集めて広告収益を得る
• 課金モデル:有料記事や購読で読者から直接収益を得る
しかし現在、多くのユーザーは、AIによる「断片的な答え」だけを求めていて、記事を「読む」こと自体を回避するようになっています。
つまり、両方のモデルが危機に瀕しているということです。
では、このような状況で、出版社はどのような戦略を立てるべきでしょうか。
出版社が取り組むべき3つの戦略例
1. AI企業との積極的なライセンス交渉
すでに一部の大手出版社はAI企業と「ライセンス契約」を結び、一定の対価を得る動きに出ています。中小規模の出版社であっても、AI企業に対し「どのようなデータが使用されているのか」を明確に問い、使用条件の交渉に備えることが必要です。
2. 「読む」ではなく「体験する」コンテンツへ
要約では伝えきれない「体験」や「共感」に訴えるコンテンツづくりが、今後のカギとなります。単なる情報提供にとどまらず、読者が「その場にいるように感じられる」仕掛けが求められています。例えば、以下のような例があります。
• データ付きのビジュアルストーリー
• 会員限定のディスカッション型記事(読者コメントが価値になる)
• 記者の主観や現場感を伝える、人間味のあるレポートやエッセイ
など、「人の感性」に訴え、読者がアクセスしたくなる要素を持ったコンテンツを生み出すことが、ますます必要になります。
3. 読者コミュニティとの接点を築く
これからの出版社には、読者と直接つながる独自のチャネルの構築が欠かせません。
実践例:
• 記者の個性が伝わるコラム付きニュースレターの週1配信
• noteなどを使った有料会員制コンテンツの設計
• オンライン/オフラインの読者イベント、読書サロン、講座の開催
情報検索が生成AIで解決してしまい、読者との関係が希薄化してしまうという、出版社にとって非常に厳しい現実が突きつけられています。しかしこれは、新たな戦略・価値構築のチャンスでもあります。
読者が「知りたい」を超えて「感じたい」と思ったとき、AIではなく、人間の書き手が求められます。その瞬間に準備する必要があるでしょう。
参照:The Atlantic誌の記事
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/06/generative-ai-pirated-articles-books/683009/
村山有紀(むらやま・ゆき)
IT・ビジネス翻訳歴10年以上。国内外の様々な場所での生活と子育ての
経験をふまえ、自分らしい発信のスタイルを模索中。