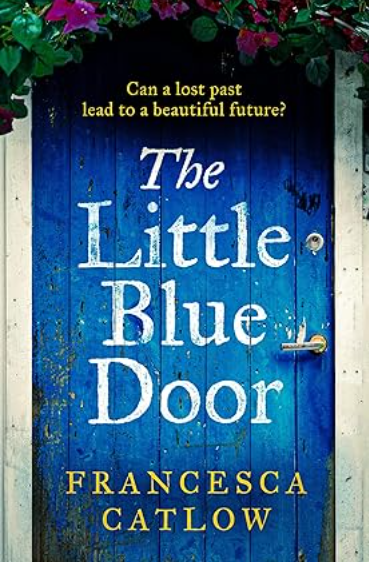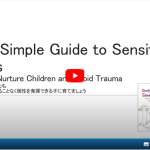2025年4月22日 第362号 World News Insight (Alumni編集室改め) 「危機に強い国家経営」への転換を バベル翻訳専門職大学院 副学長 堀田都茂樹
日本社会は、いま大きな転機に立たされている、と言う。少子高齢化、産業構造の転換、安全保障環境の変化、財政危機、教育制度の硬直化――こうした問題は個別ではなく、相互に連鎖する構造的な危機である。しかし、危機そのものが国家を滅ぼすわけではない。真に問題なのは、「国家経営」の能力がこれらにどう対応できているかである。
この視点を鋭く提示したのが、『世界は経営でできている』の著者、経営学者・岩尾俊兵氏である。1988年生まれの岩尾氏は、神戸大学大学院経営学研究科博士課程を経て、現在は慶應義塾大学総合政策学部で教鞭を執る気鋭の研究者である。専門は経営思想史、組織論、政治経済と広範で、歴史・思想・経営を縦横に読み解く洞察力で注目されている。
その岩尾氏が著書『世界は経営でできている』(英治出版、2020年)で展開するのは、「王朝や国家の栄枯盛衰を決めるのは軍事や経済の外的要因ではなく、“経営の巧拙”である」という大胆かつ実証的な主張である。この視点は、現代日本の進路を考える上でも極めて示唆に富んでいると思う。
本書の中核にあるのは、「危機は常に存在しており、国家がそれに対処できなくなったときに崩壊が起きる」という構造的視点である。すなわち、問題は“危機そのもの”ではなく、“危機対応力の低下”である。
この視点は、現代日本にそのまま当てはまる。たとえば、少子化、財政赤字、エネルギー安全保障などは、いずれも数十年にわたって指摘され続けてきた「予見可能な危機」である。
しかし、抜本的な改革は先送りされ、制度疲労が蓄積している。国家が“構造的課題を知っていながら放置している”という点で、歴史上の王朝の衰退するプロセスと酷似している。
また、岩尾氏が警鐘を鳴らすのは、「形式主義に陥ったエリート層」の存在である。かつてラテン語や儒教の経典暗記など形式的教養が評価された時代、そうしたエリートは社会の現実問題に対応できず、国家の劣化を招いた。現代日本でも、制度の硬直化や学歴偏重、前例踏襲型の政策判断が目立ち、実務力よりも形式的能力を重視する傾向が依然として強い。
彼は経営学者としての視点から、国家の運命を「経営力」で読み解く。たとえば、古代エジプトが“海の民”によって滅ぼされたという通説に対して、氏は「本当の敗因は経営体力の喪失にある」と読み替える。また、漢王朝の崩壊も、黄巾の乱など民衆反乱そのものより、それに対処できなくなった内部の制度劣化に原因があったと分析する。
つまり、岩尾氏の論旨はこうだ。「歴史を動かすのは戦争でも陰謀でもなく、“経営”である。世界の構造、社会の命運、国家の持続可能性は、誰がどう舵取りをするかにかかっている」。
これは決して過去の教訓ではない。むしろ現在の日本にこそ向けられた警告である。以下、岩尾氏の理論を踏まえた日本への具体的政策提言を提示する。
提言1:国家経営庁の創設と「未来戦略本部」の設置
縦割り行政を超えて、人口・エネルギー・教育・財政など複合的なリスクに対応できる新たな司令塔として、「国家経営庁」を創設。さらにその中に、次世代・異業種・地方の多様な人材を集めた「未来戦略本部」を設け、政策実験・地域実装・緊急対応計画を柔軟に行う。
提言2:官僚制度の経営化と人材流動化
各省庁のKPIを公開し、実務能力と経営成果に基づいた人事評価制度を導入。現場主義を徹底し、省庁横断のタスクフォース型組織と外部人材の登用を拡大。若手官僚の政策起案と裁量を強化する。
提言3:地方経営人材の育成と「地域CEO」の登用
各地方自治体に経営塾的プログラム(仮称:地方政策マネジメント・アカデミー)を創設し、地域資源を活用して再生を牽引できる“地域CEO”を育てる体制をつくる。中央と地方の間での人材循環制度も強化する。
提言4:教育の目的を「未来設計」に再定義
暗記型・知識偏重の教育から脱却し、中高・大学に「社会経営」「政策設計」「公共イノベーション」科目を導入。若者が「この国をどう再設計するか」を自ら考え、実践できる教育を整備する。
まとめ
岩尾俊兵氏は、歴史と経営を結びつけるユニークなアプローチで、「国家を動かすのは経営である」と繰り返し説く。国家は、戦争や革命によって滅びるのではない。内部の制度疲労と経営の劣化によって、自ら崩壊していくのだ。日本も例外ではない。いま求められているのは、「危機に強い国家経営」への転換である。岩尾氏の言葉を現代の羅針盤として、日本は未来に向けた国家再設計に踏み出すべきときにあると、言えるかもしれない。