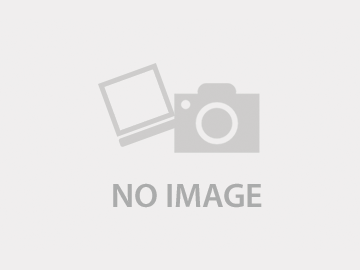「本を書きたいけれど、どこから始めたらいいのかわからない」──そんな悩みを抱える人は多いものです。自分史や体験記を残したいと願っても、テーマ決めや文章化の壁に阻まれて、途中であきらめてしまうケースも少なくありません。
けれども、もしAIが編集者のように質問を投げかけ、答えていくうちに原稿が形になっていくとしたらどうでしょうか。孤独な執筆作業が「対話」へと変わり、書けない人でも自然に書けるようになるのです。それが今回紹介する「インタビュー編集者AI」です。
筆者は、実際に「インタビュー編集者AI」を使って本を執筆してみました。それが『思い出を紡ぎ、未来へ手渡す』という作品です。筆者は「AIがいることで、書くことのハードルが下がり、創作が楽しくなった」と実感しています。この作品は実例編で全文公開します。
実践マニュアル編
- インタビュー編集者AIとは?
著者とチャットでやりとりしながら、回答を章立てや本文ドラフトに変換するAIです。
「質問 → 回答 → 追問 → 構造化 → ドラフト作成 → 品質チェック」までを一気に支援します。
- 基本の質問フレーム
AIはまず、次の5問を投げかけます。
- 読者像(年齢・職業・悩み)
- 読了後に得られる変化(どんな約束をするか)
- 経験や実績の裏づけ
- 再現可能な手順(3〜5ステップ)
- 今日すぐにできる最初の一歩
→ 著者はこれに答えるだけで、本の核が整理されます。
- 追問と具体化
回答が抽象的なときは、AIが短い追加質問を出して具体性を高めます。
例:「それは何人くらいの読者を想定していますか?」、「実体験に基づいたエピソードはありますか?」
こうして数字・具体例・反論への対応が自然に補われ、読者に届く内容になります。
- 構造化フォーマット
回答は内部で以下の形(JSON)に整理されます:
{
"chapter_title": "",
"core_claim": "",
"supporting_points": [],
"anecdotes": [],
"quotes": [],
"gaps": []
}
これにより章ごとに「主張」「根拠」「エピソード」が整い、原稿の骨格が可視化されます。
- 章立てと本文ドラフト生成
質問が終わると、AIはMarkdown形式で本文を提案します。各章は次の流れで展開されます。ちなみに「Markdown(マークダウン)」とは、文章をちょっとした記号で見やすく整えるための シンプルな書き方のルールです。難しいプログラミングを覚えなくても、テキストだけでキレイな文書を作れるのが特徴です。
- 導入
- 主張
- 根拠
- 具体例
- まとめ
- 次の一歩
例えば、作例の『思い出を紡ぎ、未来へ手渡す』では、定年後の人生をどう残すかというテーマが章立てに落とし込まれ、「テーマ決め」「プロット設計」「執筆」「推敲」「出版」と段階的に進む構成になります。
- 推敲と品質チェック
AIは完成したドラフトを「事実性・独自性・可読性・一貫性」の観点でレビューします。冗長さを削ったり、読者層に合わせた表現に直したりすることが可能です。
実例でも、AIによる推敲で文章量が2割減り、読みやすさが格段に向上したと報告されています。
まとめ:人生を本にする体験を、誰にでも
本を書くことは「自己表現」であると同時に「未来への贈り物」です。AIと対話しながら自分の体験を整理していけば、文章に自信がなくても、一冊の本に仕上げられます。
インタビュー編集者AIは、書く人の孤独を和らげ、伴走者として物語を形にします。あなたも「答えるだけで本が生まれる」体験をしてみませんか? 今始めることが、あなたの物語を未来へ手渡す第一歩になるのです。
--- 続きをご覧いただくには、ログインまたは会員登録してください。---