おすすめの記事
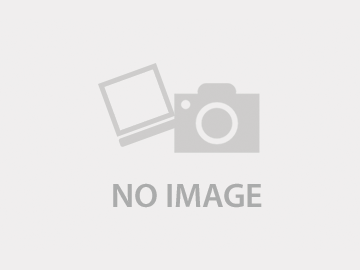
AI活用文章術
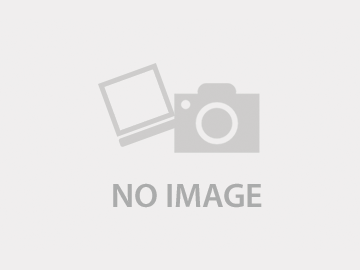
サンプル
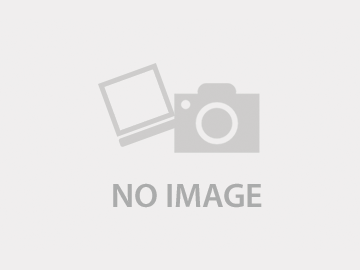
投稿スペース
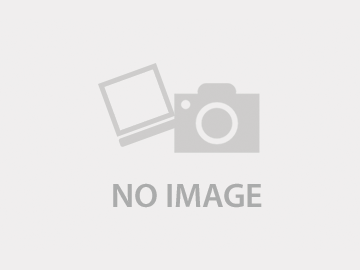
投稿スペース
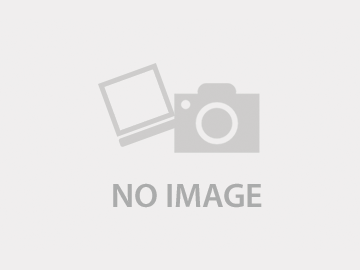
ライターズマーケット近況
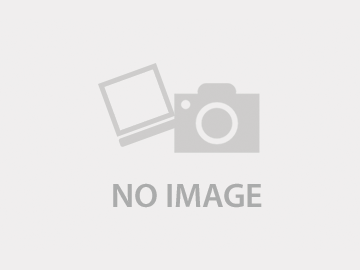
AI活用文章術
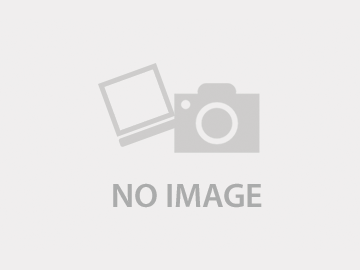
投稿スペース

ライターズマーケット近況