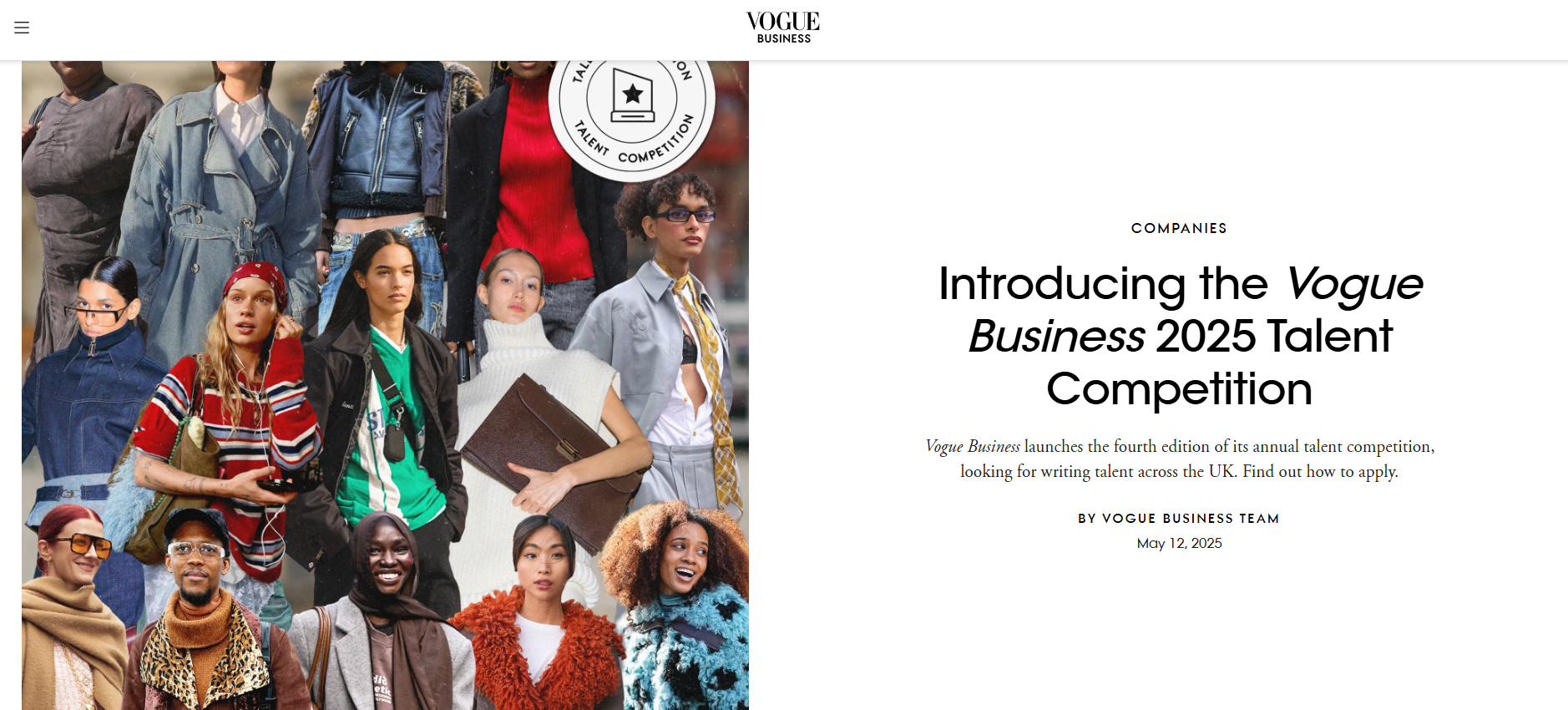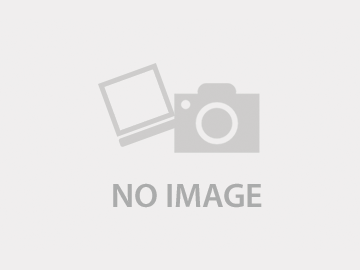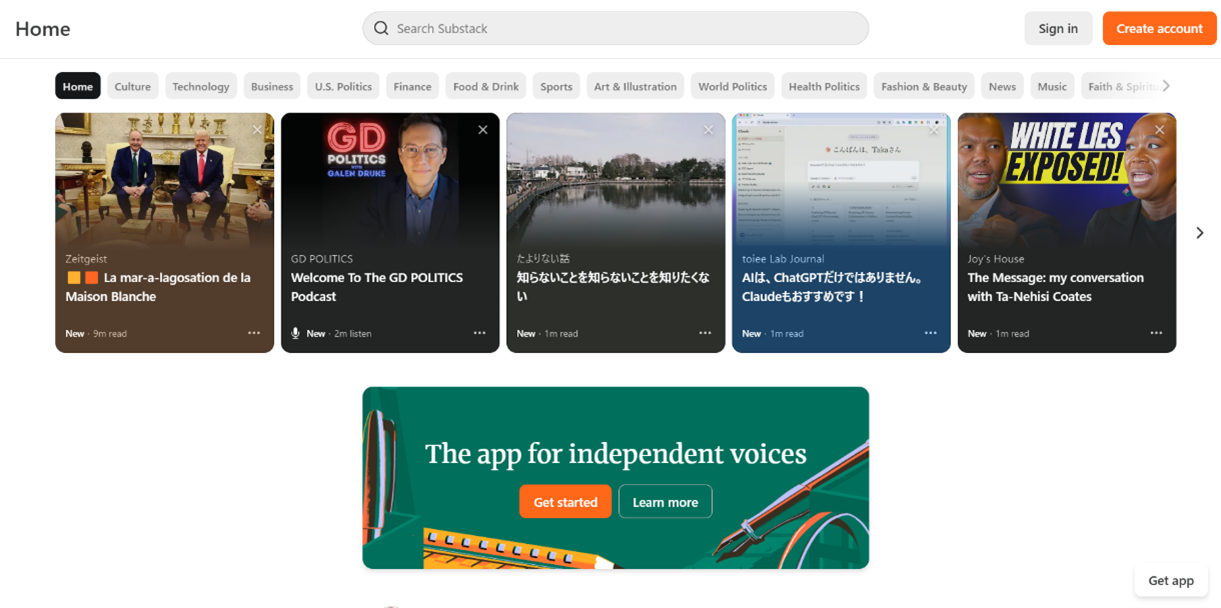はじめに
いよいよ連載がスタートしました!
今回は第1期として、全8回の内容を予定しています。
その概要を、まずはご紹介しましょう。
なお、内容は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第1回:AIライティングの基本:何ができるのか?
ChatGPTや他のAIライティングツールの紹介
AIライティングの得意・不得意
AIを使うべき場面・使わないほうがいい場面
簡単な実演(例:「商品紹介文を作る」)
AIライティングの得意・不得意
AIを使うべき場面・使わないほうがいい場面
簡単な実演(例:「商品紹介文を作る」)
第2回:AIを使った「発想術」:アイデアを量産する
AIを使ったブレインストーミング
タイトルや見出しの生成
記事の構成を考える(マインドマップ的な活用)
AIを活用したリサーチテクニック
タイトルや見出しの生成
記事の構成を考える(マインドマップ的な活用)
AIを活用したリサーチテクニック
第3回:AIと人間の共作:自然な文章を作るには?
AIが生成する文章の特徴
不自然な表現を修正する方法
AIの文章をより「人間らしく」するコツ
実践:「AIに書かせた文章を添削してみよう」
不自然な表現を修正する方法
AIの文章をより「人間らしく」するコツ
実践:「AIに書かせた文章を添削してみよう」
第4回:AIによる文章の推敲・リライト術
AIに文章をチェックさせる方法
簡潔で伝わりやすい文章へのリライト
文体の統一と整え方
実践:「リライト前後の比較」
簡潔で伝わりやすい文章へのリライト
文体の統一と整え方
実践:「リライト前後の比較」
第5回:AIを活用した説得力のある文章の作り方
説得力のある文章とは?(論理展開の基本)
AIに主張を整理させる方法
AIを使ったデータの引用・活用
実践:「説得力のある文章をAIと一緒に書く」
AIに主張を整理させる方法
AIを使ったデータの引用・活用
実践:「説得力のある文章をAIと一緒に書く」
第6回:AIで個性的な文体を作る方法
AIに「文体」を学習させる方法
自分らしい文章スタイルを確立するには?
AIで複数の文体を試す(例:「硬い文体」「ユーモアのある文体」など)
実践:「自分に合った文体を見つける」
自分らしい文章スタイルを確立するには?
AIで複数の文体を試す(例:「硬い文体」「ユーモアのある文体」など)
実践:「自分に合った文体を見つける」
第7回:AIによる要約&翻訳の実践テクニック
長文を簡潔にまとめる方法
要約の精度を上げるコツ(プロンプトの工夫)
AI翻訳の活用法と注意点
実践:「ニュース記事の要約&翻訳」
要約の精度を上げるコツ(プロンプトの工夫)
AI翻訳の活用法と注意点
実践:「ニュース記事の要約&翻訳」
第8回:AIライティングの未来と、人間が担う役割
AIライティングの進化と今後の展望
AIに頼りすぎることのリスク
AI時代に求められる「人間の文章力」
まとめ:「AIを賢く使いこなすには?」
AIに頼りすぎることのリスク
AI時代に求められる「人間の文章力」
まとめ:「AIを賢く使いこなすには?」
この連載では、AIを活用して文章作成や表現を効率化・改善したいライター、ビジネスパーソン、学生、翻訳者、SNS運用者など幅広い層を想定しています。
--- 続きをご覧いただくには、ログインまたは会員登録してください。---